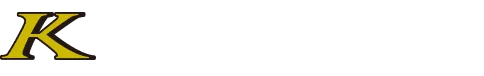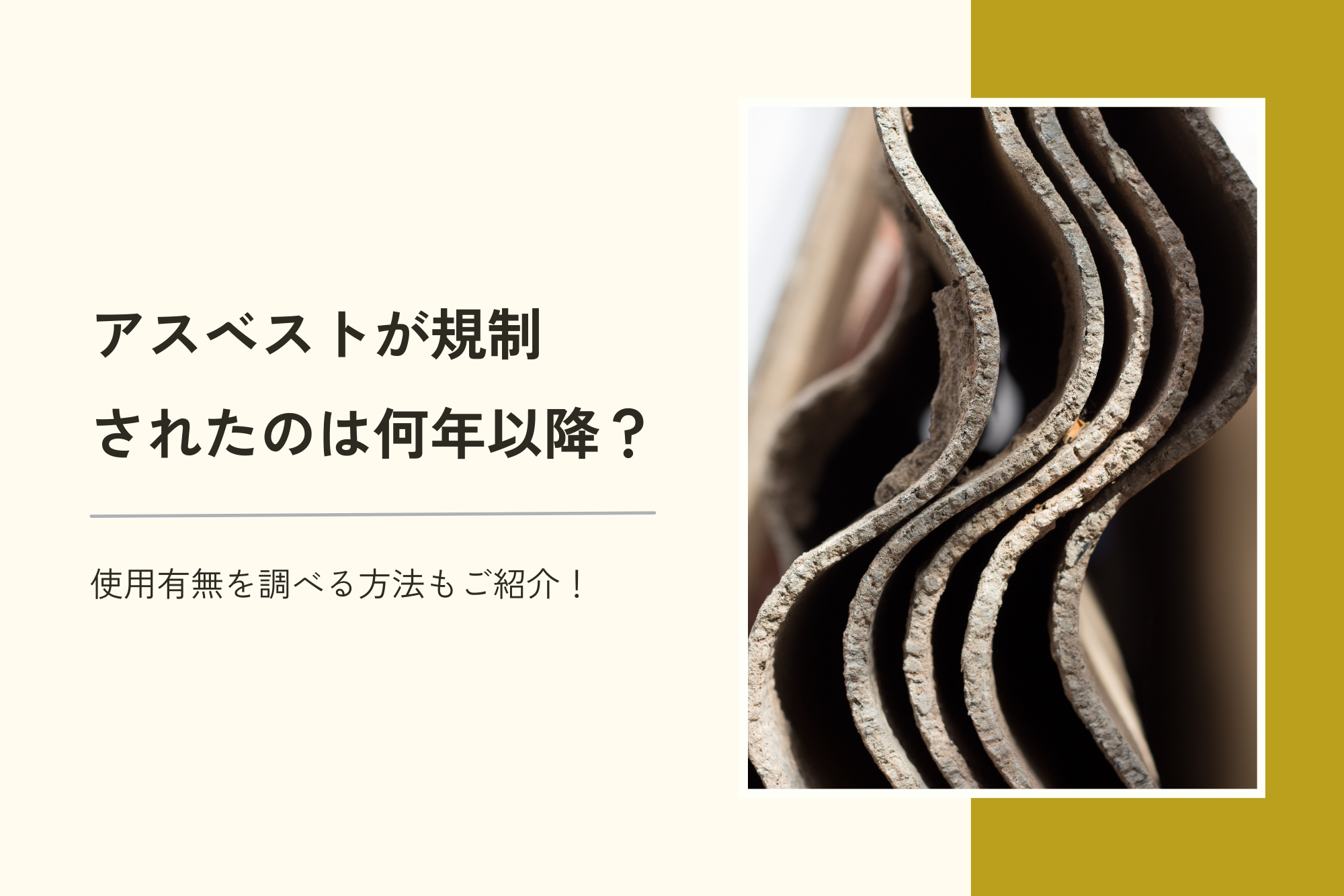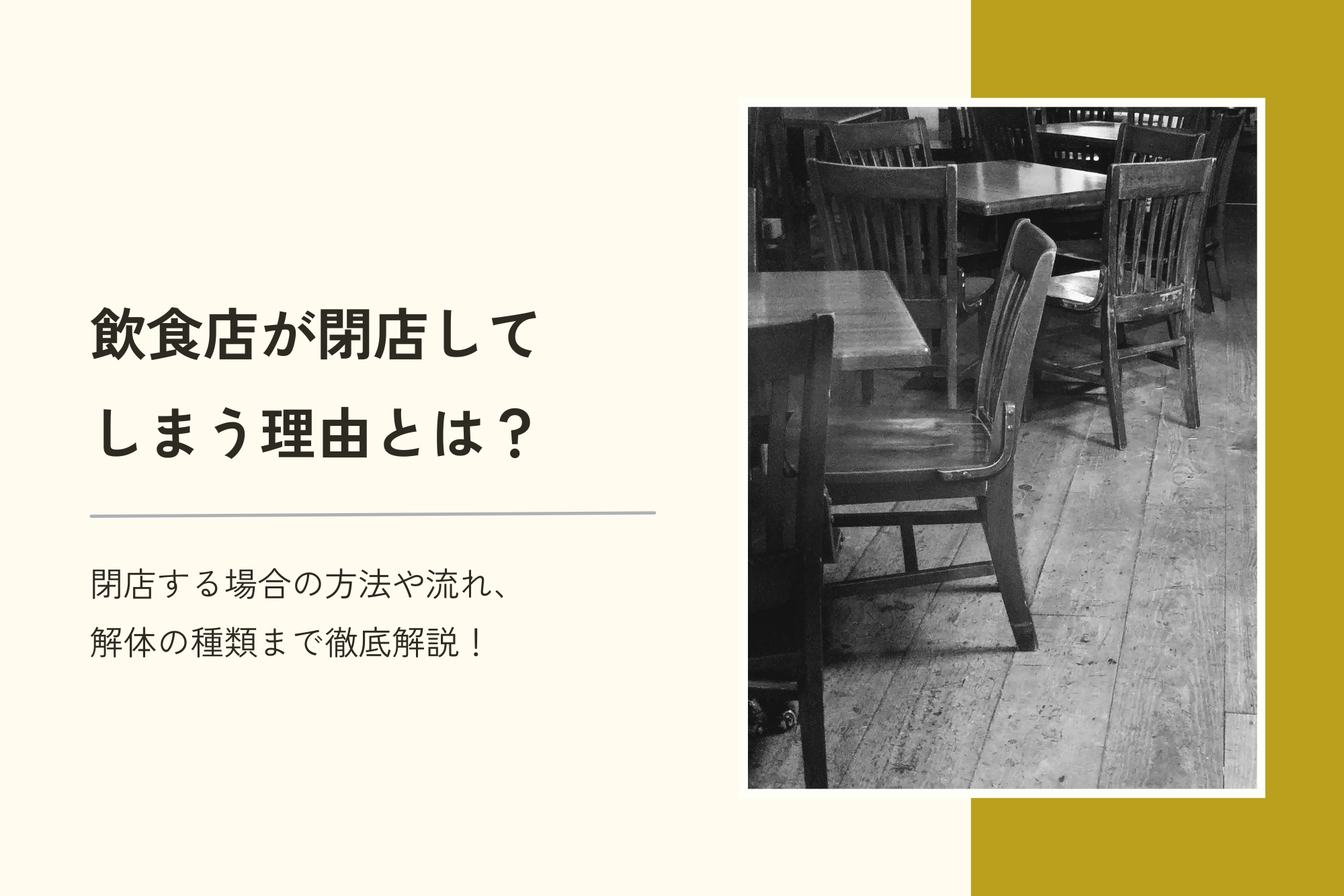飲食店を経営されている方で、業務用冷蔵庫の減価償却について詳しく知りたい方もおられるのではないでしょうか。業務用冷蔵庫を減価償却する場合、取得額によって処理方法が変わるため、この点を正しく理解しておく必要があります。
本記事では、業務用冷蔵庫を減価償却する場合の計算方法を解説します。また、仕訳例やよくある質問も解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。

減価償却とは?

減価償却とは、固定資産の取得費用をその資産の使用期間にわたって分割して計上する会計手法です。企業が購入した建物や機械などの固定資産は、使用するうちに価値が減少します。
その減少分を費用として計上すれば、資産の実際の価値が反映でき、収益と費用を適切に対応させられるようになります。これにより、企業は税務上の利益を正確に報告し、将来の資本投資計画を立てることが可能です。

減価償却の目的

減価償却の主な目的は、費用と収益を正しく対応させることです。固定資産は長期間にわたり使用され、その価値が徐々に減少するため、取得した年に一括で費用を計上すると、実際の経営状況が正確に反映されません。
そのため、固定資産の価値を耐用年数にわたって均等に分配し、毎年の収益と合致させる必要があります。この方法は、会計期間ごとの収益報告が現実の経営活動を正確に反映し、経営者や投資家が適切な判断を下すために欠かせない情報です。
また、減価償却の仕組みがなければ、利益が高い年に多額の資産を購入し、一度に費用計上して税負担を減らす可能性があります。そのリスクを避けるため、費用計上できる減価償却費は、「減価償却資産の取得価額を法定耐用年数で割った金額(償却限度額)まで」という決まりがあります。

減価償却の方法

次は、減価償却の方法について解説します。
- 定額法
- 定率法
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.定額法
定額法は、購入した資産に対して毎年一定の金額を減価償却費として計上する計算方法です。この方法の計算式は「減価償却費 = 取得価額 × 定額法の償却率」となります。
たとえば、1月1日に300万円で自動車を購入し、耐用年数が6年である場合、定額法の償却率は0.167です。そのため、1年あたりの減価償却費は300万円×0.167で50万1000円と計算されます。
定額法は、毎年の償却費がわかりやすい点がメリットです。しかし、定率法と比較すると、購入年に経費として計上できる金額が少なくなるデメリットもあります。
2.定率法
定率法は、1年目の償却額が大きくなり、その後は徐々に減少していきます。計算式は、「減価償却費 = 未償却の残高(初年度のみ取得価額)×定率法の償却率」です。
償却額が償却保証額を下回る場合は、計算方法が変更され、それぞれの算出方法は以下になります。
- 償却保証額=取得価額×保証率
- 減価償却費=未償却残高×改定償却率
償却額が保証額を下回った年以降は、償却額は毎年同額になります。また、定率法のメリットは、購入した年に定額法と比較して多くの金額を経費計上できる点です。
しかし、計算方法が複雑な点はデメリットになります。ただし、会計ソフトを利用すれば自動計算されるため、運用においては大きな問題とはなりません。

業務用冷蔵庫を減価償却する場合の計算方法

飲食店で利用する冷蔵庫は、「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気・ガス機器」に該当し、法定耐用年数は6年です。そのため、120万円の冷蔵庫は6年間使用される計算になり、1年あたりの減価償却費は20万円(120万円÷6年)です。
冷蔵庫は6年以上継続して使用できる可能性が高いため、7年目以降は経理上で減価償却する必要がありません。

【パターン別】業務用冷蔵庫の仕訳例

次は、業務用冷蔵庫の仕訳例について解説します。
- 10万円未満で取得した場合
- 10万円以上で取得した場合
- 一括償却資産として処理する場合
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.10万円未満で取得した場合
業務で利用する冷蔵庫を10万円未満で購入する場合、「消耗品費」の勘定科目を使用します。さらに、「少額減価償却資産の特例」の要件に該当し、30万円未満であれば、消耗品費として全額を経費に計上が可能です。
たとえば、オフィスに設置する8万円の冷蔵庫を購入した場合は、以下のように仕訳します。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 消耗品費 | 80,000円 | 現金 | 80,000円 | 冷蔵庫購入 |
2.10万円以上で取得した場合
10万円以上の冷蔵庫を購入したときは、原則として資産に計上し、6年かけて毎年減価償却します。購入時の勘定科目は、事務機器やオフィス家具などといった固定資産を計上する「工具器具備品」を使用します。
たとえば、オフィス用に36万円の冷蔵庫を取得した場合、備品として資産計上する場合の仕訳例は以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 工具器具備品 | 360,000円 | 現金 | 360,000円 | 冷蔵庫購入 |
さらに、決算期に減価償却後、当期分を費用として計上する場合の仕訳例は以下のようになります。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 減価償却費 | 60,000円 | 工具器具備品 | 60,000円 | 冷蔵庫の減価償却 |
3.一括償却資産として処理する場合
20万円以下の冷蔵庫を一括償却資産で処理する場合、購入時に全額を経費として計上し、決算期には3年間で均等に費用を配分します。たとえば、オフィス用に15万円の冷蔵庫を購入した場合、購入時の仕訳方法は、以下のとおりです。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 一括償却資産 | 150,000円 | 現金 | 150,000円 | 冷蔵庫購入 |
さらに、決算時に減価償却をします。
| 借方 | 貸方 | 摘要 | ||
| 減価償却費 | 50,000円 | 一括償却資産 | 50,000円 | 冷蔵庫の減価償却 |

減価償却 冷蔵庫でよくある5つの質問

最後に、減価償却 冷蔵庫でよくある質問について紹介します。
- 質問1.減価償却のタイミングは?
- 質問2.冷蔵庫を経費計上するのが難しいケースとは?
- 質問3.冷蔵庫の耐用年数は?
- 質問4.冷蔵庫の寿命を示すサインは?
- 質問5.減価償却の特例とは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.減価償却のタイミングは?
減価償却の開始は、資産の事業供用日からです。たとえば、期首に入手した資産が期中のいずれかの日に事業供用される場合、減価償却はその事業供用日を基準に月割りで計算されます。
資産の入手日と事業供用日が異なるケースは珍しくなく、資産が購入された期中に使用されずに、事業供用日が次の期に設定される場合もあります。
質問2.冷蔵庫を経費計上するのが難しいケースとは?
個人事業主が自宅を兼ねた事務所や社宅に設置する場合が該当します。自宅兼事務所では、日常生活で使用されるエリアにも冷蔵庫を設置するケースが多く、事業用と見なされにくいためです。
さらに、社宅に設置された冷蔵庫や家具は、事業に直接関連するものとは認められず、経費として計上できません。これらを会社が負担する場合は、現物給与として課税されます。
ただし、福利厚生費として処理することは可能ですが、すべての従業員を対象とするなどの特定の要件を満たす必要があります。
質問3.冷蔵庫の耐用年数は?
冷蔵庫の法定耐用年数は6年です。この法定耐用年数とは、事業における固定資産としての使用可能期間を国が定めたものであり、減価償却費を算出する際に重要な指標となります。
多くの場合、「耐久年数」と混同されがちですが、耐久年数は製造メーカーが独自に設定する期間です。家庭で使う場合には馴染みの薄い用語ですが、法定耐用年数は購入後の費用対効果を計る際のひとつの目安となります。
なお、厨房機器の耐用年数については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:厨房機器の耐用年数とは?減価償却の方法や買い替えるべきタイミングも解説します!
質問4.冷蔵庫の寿命を示すサインは?
冷蔵庫の寿命は一般的に9〜13年が目安ですが、使用状況によって変わる場合があります。買い替えのタイミングを見極めるには、単に年数だけでなく、冷蔵庫の性能に注目しましょう。
- 冷却性能が低下している
適切に使用していても冷却性能が落ちている場合、寿命が近づいている可能性がある。扉をしっかり閉めても冷えにくい場合や、冷凍庫で氷がうまく作れない、作った氷が固まってしまうといった症状がみられる場合は注意しなければならない
- 水漏れが発生している
水漏れが起きている場所によって原因が異なるため、具体的な場所を特定して対処する必要がある。水漏れは、冷気の流れに関連する部品の故障が原因であるケースが多い
- 異音が続いている
普段とは明らかに異なる音がする場合、内部のコンプレッサーなどが正常に機能していない可能性がある
質問5.減価償却の特例とは?
個人事業主で青色申請している場合は、「少額減価償却資産の特例」を利用でき、1個当たり30万円未満の備品は一括で経費として計上可能です。その年の利益額に応じて、一括で計上するか減価償却するかを選択して調整もできます。
ただし、対象の備品に一括で計上するか減価償却するかを選択すると、変更ができないため注意しましょう。また、白色申請している場合は、30万円未満ではなく10万円未満の備品の場合に特例が適用されます。

まとめ

本記事では、業務用冷蔵庫を減価償却する場合の計算方法や仕訳例を解説しました。
業務用冷蔵庫を減価償却するには、取得額によって処理方法が変わります。10万円未満もしくは「少額減価償却資産の特例」の要件に該当し、30万円未満であれば、「消耗品費」として費用計上が可能です。
また、10万円以上の場合は、「工具器具備品」で資産計上し、6年かけて毎年減価償却します。20万円以下の冷蔵庫を一括償却資産で処理する場合は、購入時に全額を経費として計上し、決算期には3年間で均等に費用を配分する必要があります。
減価償却には法定耐用年数の理解が欠かせないため、国税庁のホームページで公開されている耐用年数表で確認してください。