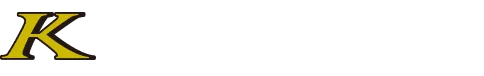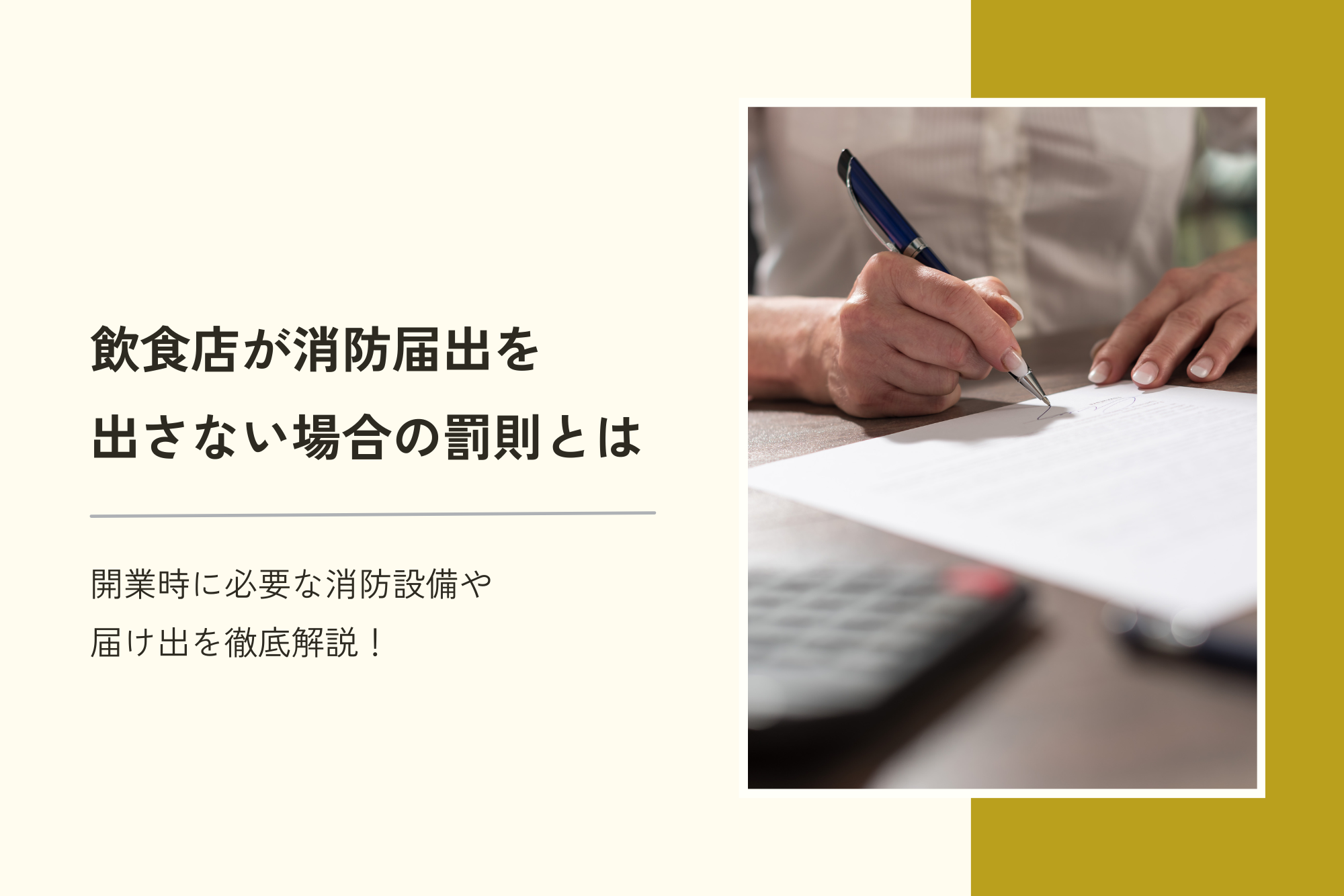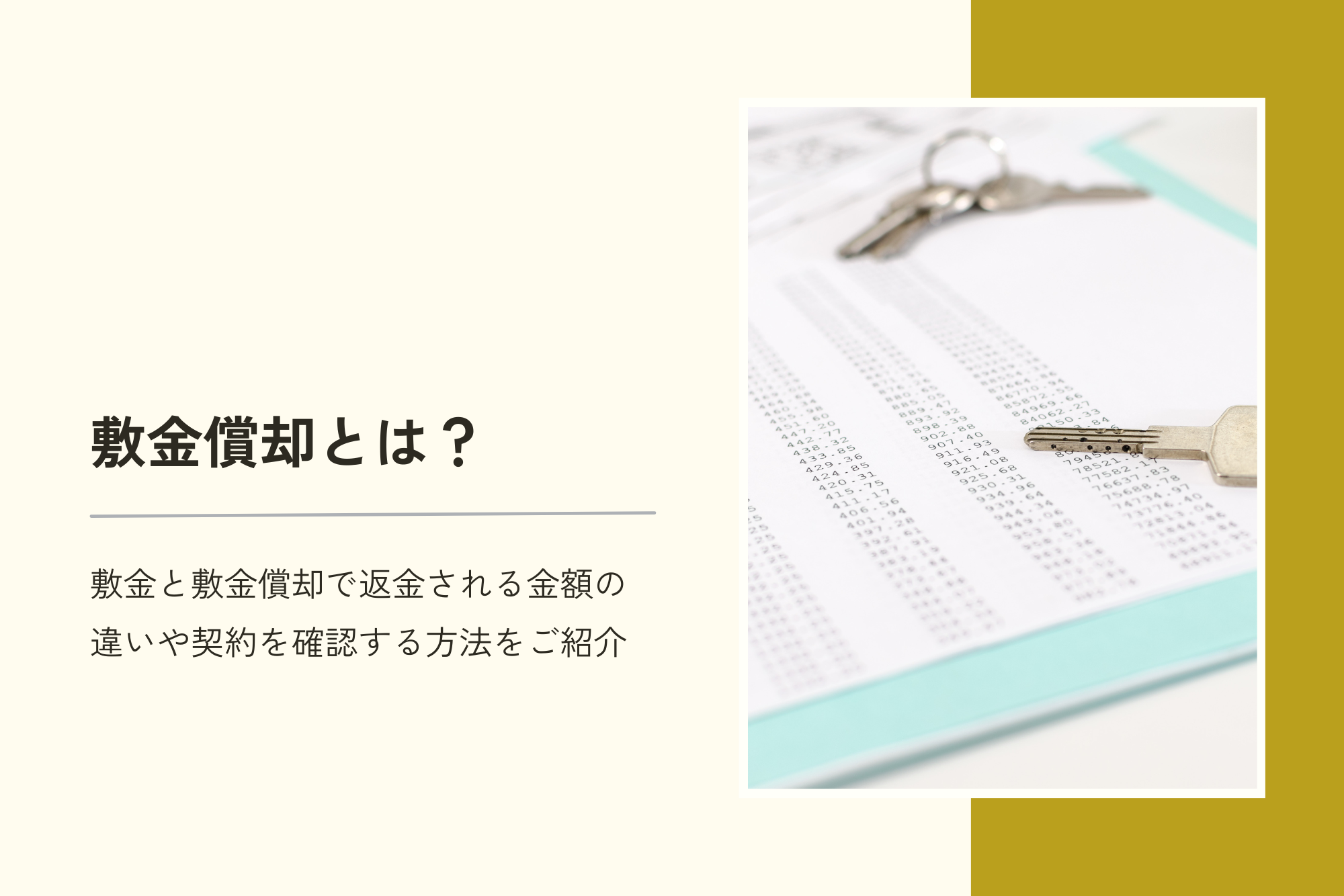建物を解体する際には、必ず提出しなければならない届出が6種類あります。届出を怠ると、罰則や罰金に科される可能性があるため、解体を検討している方は十分に注意してください。
本記事では、建物の解体に必要な6種類の届出や提出しなかった場合の罰則についてご紹介します。また、よくある質問も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。

建物の解体に必要な届出は6種類

まず、建物の解体に必要な届出について解説します。
- 建築物除却届
- 建物滅失登記申請
- 道路の使用許可申請
- 建設リサイクル法に関する届出
- ライフラインの停止
- アスベスト除去の届出
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.建築物除却届
建物の解体工事をする際には、建築基準法にもとづき、事前に都道府県知事に建築物除却届を提出しなければなりません。工事の前日までの提出が求められますが、例外として工事部分の床面積が10平方メートル以下の場合や、建て替えを目的とした解体工事の場合は届出が不要です。
また、届出が必要な場合に、施主が委任状を持参して業者に手続きを依頼することも可能です。届出する際には費用が発生するため、事前に業者と費用について話し合っておきましょう。
2.建物滅失登記申請
建物の解体後には、建築基準法に加えて登記法にもとづく届出も必要です。建物滅失登記申請は法務局に対して解体完了から1か月以内に行う必要があります。
この手続きは自分でもできますが、土地家屋調査士への依頼も可能です。ただし、申請を怠ると、解体後も固定資産税が課税されるリスクがあるため、忘れずに申請するようにしましょう。
また、申請には多くの書類が必要であり、災害で建物が消滅した場合にも同様の申請が求められます。法務局に出向くのが難しい場合は、司法書士へ依頼するのもおすすめです。
3.道路の使用許可申請
道路の使用許可申請の種類や提出先は、以下のとおりです。
| 書類名 | 届出先 | 届出時期 |
| 道路占用許可申請 | 道路管理者 | 解体工事着手10~14日前 |
| 道路自費工事許可申請 | 解体工事着手24~40日前 | |
| 特殊車両通行許可申請 | 解体工事着手20~30日前 | |
| 沿道掘削申請 | 解体工事着手20~50日前 | |
| 道路使用許可申請 | 警察署 | 解体工事着手2日~7日前 |
| 通行停止道路通行許可申請 | 解体工事着手2日前 |
道路使用許可申請には、解体業者が道路使用の目的や期間、場所などを明記した申請書と、道路使用場所の見取り図を添付します。また、道路使用許可申請には手数料が発生し、都道府県ごとに異なるため、詳細は事前に確認するようにしてください。
4.建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法に関する届出の種類は、以下のとおりです。
| 書類名 | 届出先 | 届出時期 |
| 解体建物の構造届 | 都道府県 | 解体工事着手7日前 |
| 着手時期や工期と工程表 | ||
| 分別解体計画 | ||
| 廃材量の見込み | ||
| 上記の変更届 |
建物を解体する際に、延床面積が80㎡以上で、鉄やアスファルトなどの特定の建材が使用できる建物の解体は建築リサイクル法の届出が求められます。提出義務は基本的に施主にありますが、手続きの煩雑さから解体業者に委任するのが一般的です。
5.ライフラインの停止
建物の解体前には、施主がライフラインの停止手続きをする必要があります。対象となるのは電気や水道、ガス、インターネットなどです。
解体の1か月〜3日前までに、電話やオンラインで手続きをしておきましょう。引っ越しシーズンの3月や4月は混雑するため、早めの対応が求められます。
依頼する際には、「解体工事のため」と伝えると、メーターや引き込み線などの解放がスムーズです。しかし、水道だけは解体工事中に使用する場合が多いため、停止せずに利用できる状態を維持しましょう
6.アスベスト除去の届出
アスベスト除去の届出の書類や提出先などは、以下のとおりです。
| 書類名 | 届出先 | 届出時期 |
| アスベスト使用建築物に係る事前調査報告書 | 市区町村 | 工事着手前 |
| アスベスト除去工事計画書 | 監督署 | 工事着手14日前 |
| 特定粉塵排出作業実施届 | 都道府県 | 工事着手14日前 |
| アスベスト使用建物に係る解体撤去工事完了報告書 | 市区町村 | 工事完了後 |
アスベストは、飛散状況に応じてレベル1〜3までに分類されており、それぞれに応じた提出書類が異なります。
また、解体工事の規模に関係なく、アスベストの存在を確認するための事前調査が義務付けられています。この調査結果によって、アスベストが含まれている建材が使用されている場合には、適切に届け出なければなりません。

必要な届出を提出しなかった場合の罰則

次は、必要な届出を提出しなかった場合の罰則について解説します。
- 建物滅失登記申請
- 道路の使用許可申請
- 建設リサイクル法に関する届出
- アスベスト除去の届出
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.建物滅失登記申請
建物滅失登記を忘れると、法律により10万円の過料が科せられます。登記が未完了の場合、登記簿上では依然として建物が存在する状態のため、土地の売却や銀行からの借り入れが困難になり、固定資産税の課税が続きます。
また、令和6年4月1日から、相続登記が義務化され、所有者不明の土地問題がより厳しく管理されるようになりました。なお、解体業者が代行できない手続きのため、建物滅失登記は自ら申請する必要があります。
2.道路の使用許可申請
許可を得ずに道路を使用した場合、法律により3か月以下の懲罰または5万円以下の罰金が科せられます。また、道路を占用する必要がある場合には、別途道路占用許可も取得しなければなりません。
無許可で道路を占用した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。手続きは解体業者に依頼できますが、施主としても確実に申請されたか確認する責任があります。
3.建設リサイクル法に関する届出
建設リサイクル法に関する違反事例や罰金は、以下のとおりです。
| 違反例 | 罰金 |
| 対象となる工事の違反 | 20万円以下の罰金 |
| 対象となる工事の変更違反 | |
| 分別解体等義務の実施命令違反 | 50万以下の罰金 |
| 再資源化等義務の実施命令違反 | 20万円以下の罰金 |
| 廃棄等の違反(解体業者) |
建設リサイクル法にもとづく届出は、解体の7日前までに自治体へ提出する義務があります。この義務を怠ると、審査や行政指導が入り、改善が見られなければ罰金が科されます。
なお、罰則は原則として施主に課せられますが、手続きを解体業者に委任している場合、責任は業者に移るのが一般的です。
4.アスベスト除去の届出
大気汚染防止法にもとづく規制は厳格であり、違反した場合の罰則も厳しいです。たとえば、レベル1およびレベル2のアスベスト撤去作業に関する「特定粉塵排出等作業実施届出書」の届出を怠ると、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。
法令を遵守するためには、作業前に必要な届出を確認し、確実に手続きを済ませておきましょう。

建物解体届け出でよくある3つの質問

最後に、建物解体届け出でよくある質問について紹介します。
- 質問1.アスベストの事前調査結果報告とは?
- 質問2.店舗を解体する場合の種類は?
- 質問3.解体工事の届出以外に施主がすべきことは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.アスベストの事前調査結果報告とは?
2022年(令和4年)から、解体工事の事前準備として、アスベスト含有建材の有無を調査し、その結果を報告する義務が法律で定められました。たとえ、アスベストが含まれていない場合でも、報告は必要です。
報告は、「石綿事前調査結果報告システム」を利用して、24時間オンラインで労働基準監督署と地方公共団体の両方に一度の操作にて提出可能です。この義務は、以下の場合に適用されます。
- 解体する建物の床面積が80㎡以上
- 請負金額が100万円以上の建築物の改修工事、工作物の解体・改造・補修
さらに、調査結果は工事現場の見やすい場所に掲示し、3年間保管しなければなりません。
質問2.店舗を解体する場合の種類は?
店舗の解体工事には3つの主要な手法があります。
- 内装解体
床や天井の主要部分を残し、内装部分のみを撤去する工事で、賃貸物件の退去時に実施される場合が多い
- 原状回復
賃貸契約にもとづき、改良した内装を元に戻す工事で、飲食店で多く見られる
- スケルトン解体
建物の骨組みだけを残し、内装や配管などすべてを撤去する工事で、建物を新たな用途に転用する際に実施される
なお、スケルトン解体については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【プロが教える】スケルトン解体とは?メリットや費用相場、安く抑えるコツを徹底解説!
質問3.解体工事の届出以外に施主がすべきことは?
解体工事を円滑に進めるためには、届け出だけでなく、他にも留意すべき事項があります。ここでは、その具体的なポイントについて説明します。
- 近隣住民への配慮
解体工事中は騒音や振動が避けられないため、近隣住民への挨拶は欠かせない。工事開始の1週間前~10日前までに、工事の詳細を説明できる担当者とともに挨拶するのが望ましい
- 工事前に不用品を処分する
残置物の処理は原則として所有者の責任であり、解体業者へも依頼できるがコストがかかる。このため、事前にできるだけ不用品を整理・処分しておくのがおすすめ
なお、残置物については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:賃貸物件における「残置物」とは?トラブルにつながりやすいケースや防止策を徹底解説!

まとめ

本記事では、建物の解体に必要な6種類の届出や提出しなかった場合の罰則についてご紹介しました。
解体工事前に、解体業者は「道路の使用許可申請」「建設リサイクル法に関する届出」の申請が必要です。また、解体工事の規模に関係なく、アスベストの存在を確認するための事前調査と結果の報告が義務付けられています。
一方、解体工事を依頼している施主本人は、解体後1か月以内に「建物減失登記申請」が必要であり、手続きを忘れてしまうと固定資産税が課税され続けたり、銀行からの借り入れが困難になったりするリスクがあります。これらの届出を怠ると、罰則や罰金を科される可能性が高いため、注意しましょう。
ほかにも、「建築物除去届」や「ライフラインの停止」も忘れないようにしてください。これらの手続きは、業者や専門家と相談しながら進めるのがおすすめです。