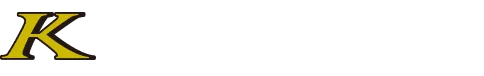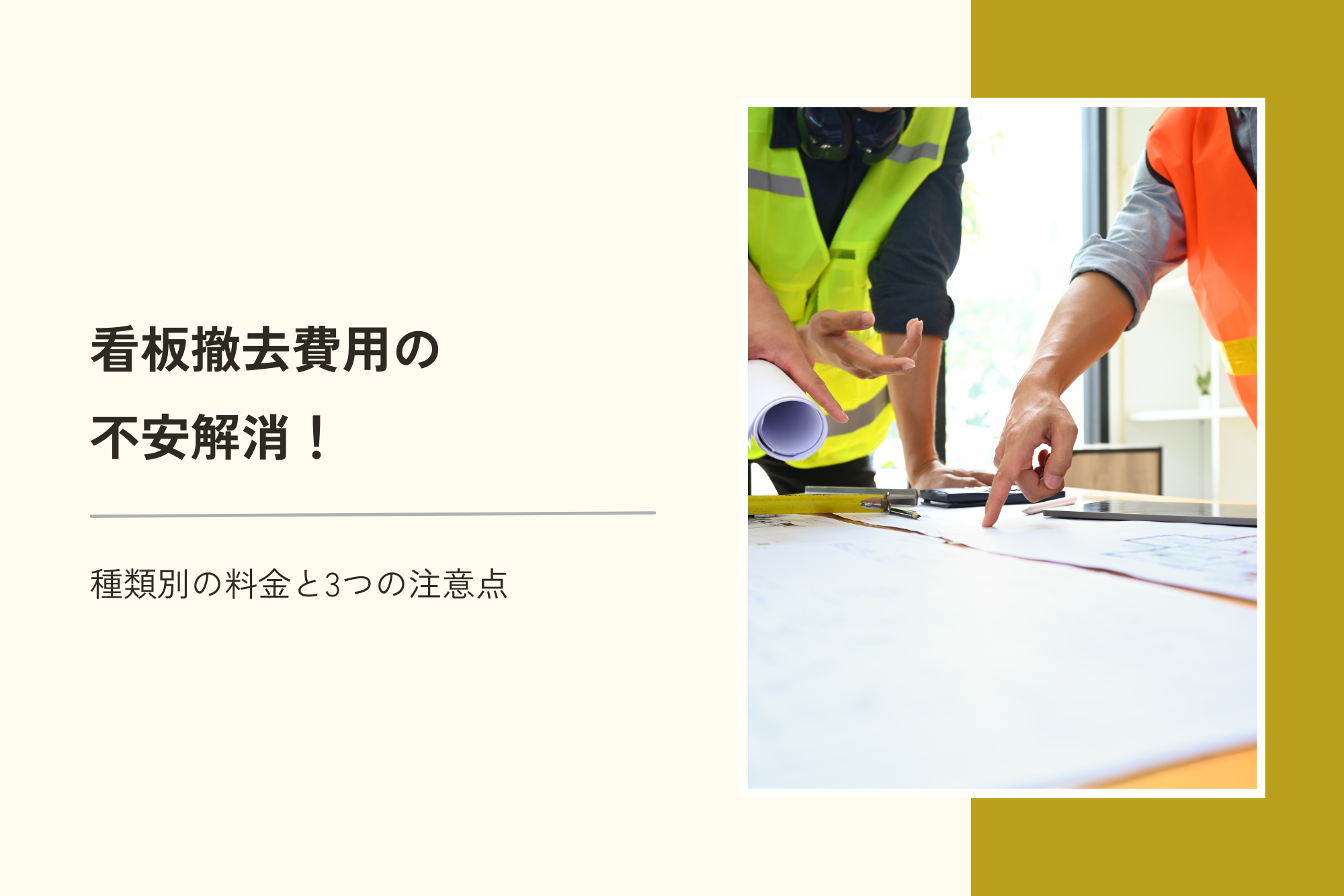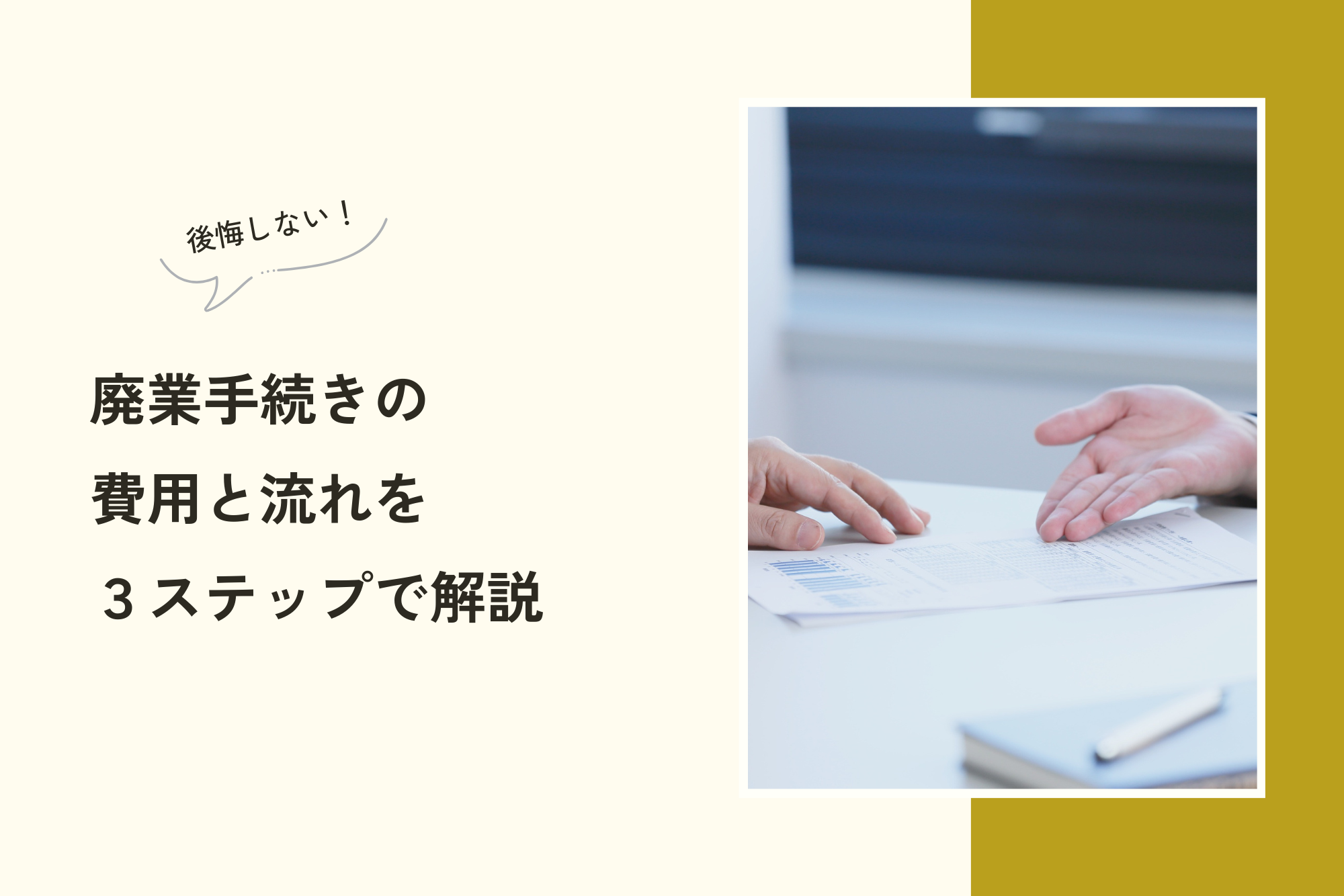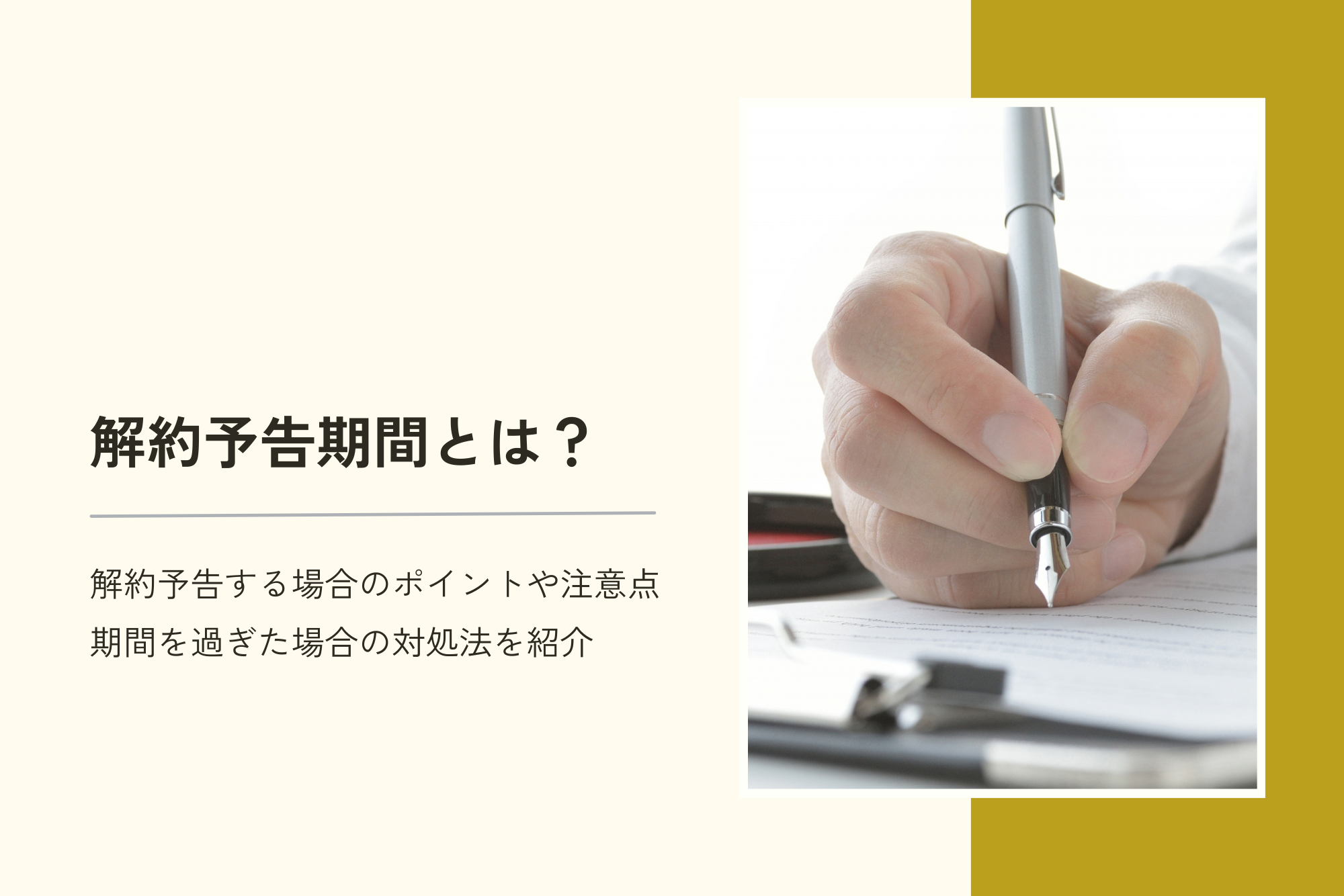
解約予告期間は、借主が物件を退去する際に、事前に通知するための期間として設定されています。解約を検討している場合は、この期間を理解せずに手続きを進めると、トラブルや予想外の費用がかかる可能性が高いため注意が必要です。
本記事では、解約予告期間の概要や解約予告する場合のポイント、注意点、期間を過ぎた場合の対処法をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

解約予告期間とは?

解約予告期間は、物件の賃貸契約において、貸主と賃借人の双方を保護するのが目的です。この期間は、借主が物件を退去する際に、事前に通知するための期間として設定されており、3か月〜6か月が一般的です。
期間内に通知すれば、貸主は新たな入居者を見つけるための時間を確保できます。この仕組みにより、賃貸物件の利用がスムーズに続き、双方の不利益を防げます。

解約予告をする場合のポイント
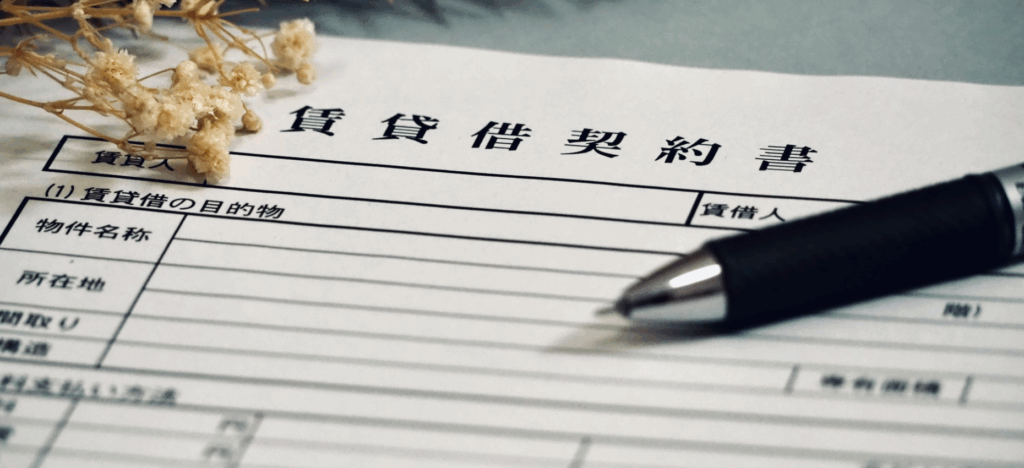
次は、解約予告をする場合のポイントについて解説します。
- 賃貸借契約書を確認する
- 管理会社もしくは貸主へ連絡する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.賃貸借契約書を確認する
「賃貸借契約書」には、解約予告の期限や特記事項が記載されており、物件ごとに異なる場合があります。契約開始から日が浅い場合や、契約更新する場合には、解約に伴う違約金が発生する可能性があります。
トラブルを避けるためにも、事前に契約書の内容をしっかりと確認することが大切です。また、契約期間の定めがない場合でも、3か月前までの予告が必要です。
2.管理会社もしくは貸主へ連絡する
賃貸契約の解約を検討している場合、解約予告期間を確認して、物件の管理会社または貸主に解約の意思を伝えましょう。管理会社に連絡するのが一般的ですが、契約内容や物件の種類によっては、貸主に連絡しなければならない場合もあります。
また、賃貸借契約書に解約に関する連絡先が記載されている場合、その連絡先に電話して解約の手続きを進めるのが望ましいです。

解約予告をする場合の注意点は3つ

次は、解約予告をする場合の注意点について解説します。
- 移転計画を立てる
- 書面で解約予告をする
- 退去日までに原状回復する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.移転計画を立てる
新しいオフィスへの移転を計画する際は、適切な時期に解約予告をしなければ、予定が狂ったり、不必要な費用が発生したりするリスクがあります。たとえば、移転先が人気のエリアの場合、賃貸契約の二重負担が発生する可能性があるため、財務面の調整が必要です。
また、移転先の物件が決まらないまま解約すると、焦って判断ミスをする可能性も高くなるため、移転計画は慎重に進めましょう。
2.書面で解約予告をする
賃貸物件の解約を進める際は、契約書の内容を確認して、定められた解約予告期間内に「解約通知書」を提出しなければなりません。解約通知書は、貸主や管理会社に書面で提出して、必ず控えを保管しておく必要があります。
通知を口頭でしてしまうと、トラブルになる可能性があるため、必ず正式な文書での手続きが求められます。さらに、退去時には原状回復義務が生じ、工事費用も借主の負担となるため、事前に費用を見積もっておくことが大切です。
3.退去日までに原状回復する
「原状回復」は、店内の内装や設備を撤去して、物件を契約前の状態に戻す作業です。原状回復は賃貸借契約書にもとづく借主の義務であり、契約内容に従って進める必要があります。
また、原状回復工事には時間がかかる場合が多いため、余裕を持って計画を立てることが大切です。事前に不動産業者や貸主と必要な工事範囲を確認し、適切に手続きを進めるようにしましょう。
なお、原状回復費用が高すぎる場合の対処法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:原状回復費用が高すぎるときの対処法は3つ|高くなりやすいケースや安く抑えるコツを解説!

解約予告期間を過ぎてしまった場合の対処法

次は、解約予告期間を過ぎてしまった場合の対処法について解説します。
- 貸主に相談する
- 家賃を日割りで支払う
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.貸主に相談する
解約予告期間を過ぎると、違約金が発生する可能性があります。しかし、貸主との信頼関係によっては、短期間の遅延であれば違約金が免除される場合もあります。
ただし、解約予告の期限を守らなかったのは借主の責任であるため、貸主と慎重に交渉しなければなりません。交渉の際は、トラブルを避けるための配慮を忘れないようにしましょう。
2.家賃を日割りで支払う
解約予告期間が過ぎてからの解約手続きとなる場合、過ぎた日数分の賃料を日割りで支払うのが一般的です。しかし、貸主によっては、多少の遅れを考慮してくれる場合もあるため、まずは貸主へ相談しましょう。
また、契約期間の更新時期も影響する可能性があるため、解約予告をする際に、契約の更新時期も確認することが大切です。費用を抑えるためには、計画的に手続きを進める必要があります。

解約予告期間でよくある3つの質問

最後に、解約予告期間でよくある質問について紹介します。
- 質問1.解約予告期間はどこに書いてある?
- 質物2.解約の撤回はできる?
- 質問3.解約予告期間は変更できる?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.解約予告期間はどこに書いてある?
解約予告に関する規定や契約条件はすべて「賃貸借契約書」に明記されています。飲食店やオフィスなどのテナント契約においては、解約予告期間が一般的に3か月〜6か月とされていますが、物件ごとに異なる場合があるため、事前の確認が大切です。
このように、契約を進める際には、賃貸借契約書の内容を十分に理解するようにしてください。
質物2.解約の撤回はできる?
解約予告の撤回が認められるかどうかは、状況によって異なります。たとえば、貸主がすでに次の入居者を確保している場合、解約予告の撤回は困難です。
一方、まだ次の入居者が決まっていない場合は、撤回が可能なケースもあります。このため、解約を取り消したい場合は、できるだけ早く貸主と連絡を取り、状況を確認することが大切です。
質問3.解約予告期間は変更できる?
解約予告期間の変更を希望する際には、必ず合理的な理由が必要です。無条件に変更はできないため、貸主と話し合わなければなりません。
借主としては、解約予告期間が短い方が、引越しや移転にかかるコストを抑えられる可能性が高くなります。貸主との信頼関係が築けている場合、交渉を試みるのも1つの方法です。

まとめ

本記事では、解約予告期間の概要や解約予告する場合のポイント、注意点、期間を過ぎた場合の対処法をご紹介しました。
テナントの解約予告期間は、3か月〜6か月が一般的であり、期間内に通知すれば、貸主は新たな入居者を見つけるための時間が確保できます。もし、解約を検討している場合は、賃貸借契約書に明記されている解約予告期間を確認し、物件の管理会社または貸主に解約の意思を伝えましょう。
また、解約を検討している場合は、移転先や原状回復などの移転計画をしっかり立てた後、書面での解約予告が必須となります。しかし、解約予告期間を過ぎてしまった場合、違約金の発生や、過ぎた日数分の賃料を日割りで支払う可能性があるため、すぐに貸主に相談しましょう。