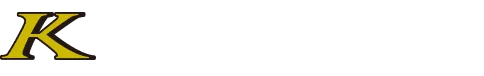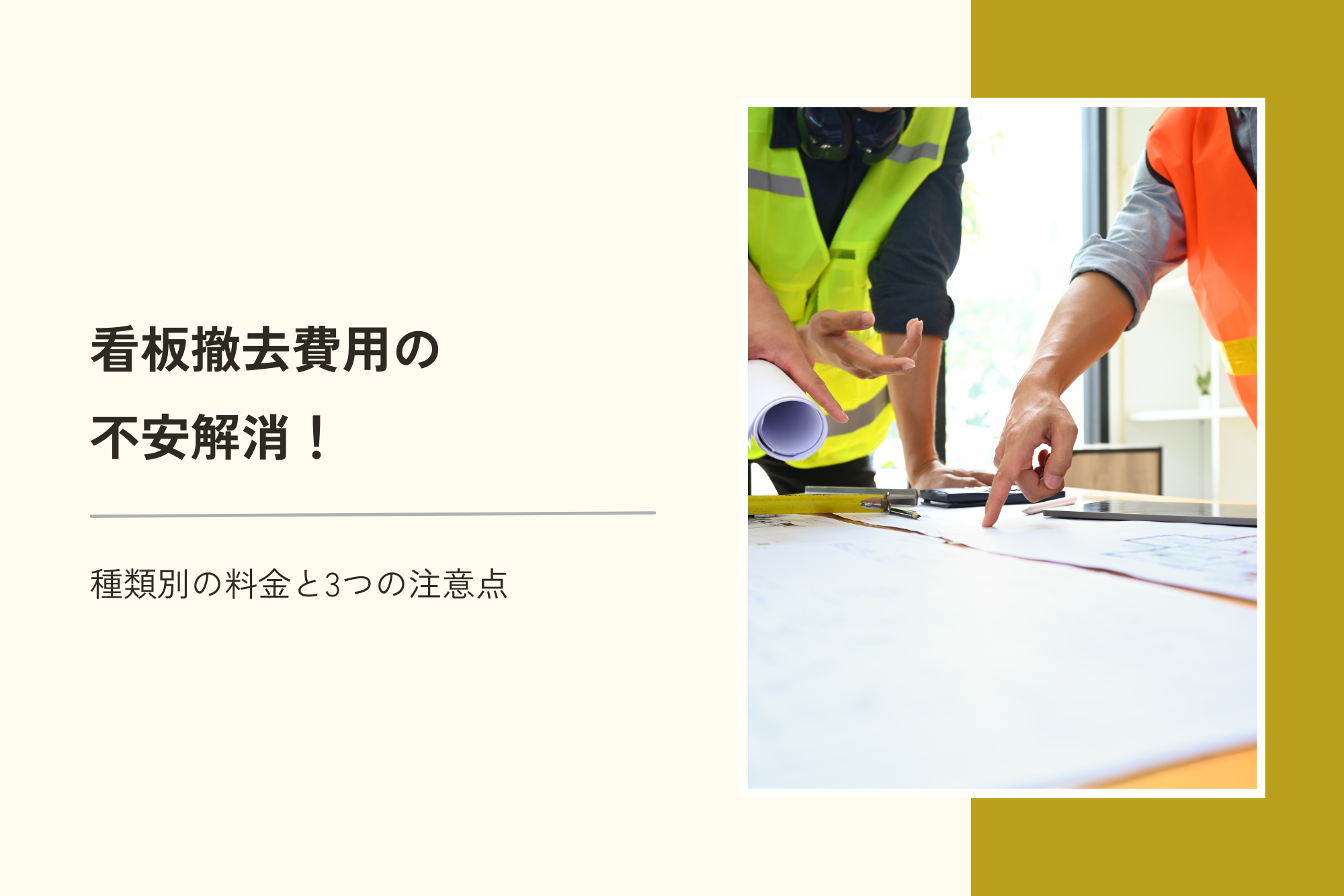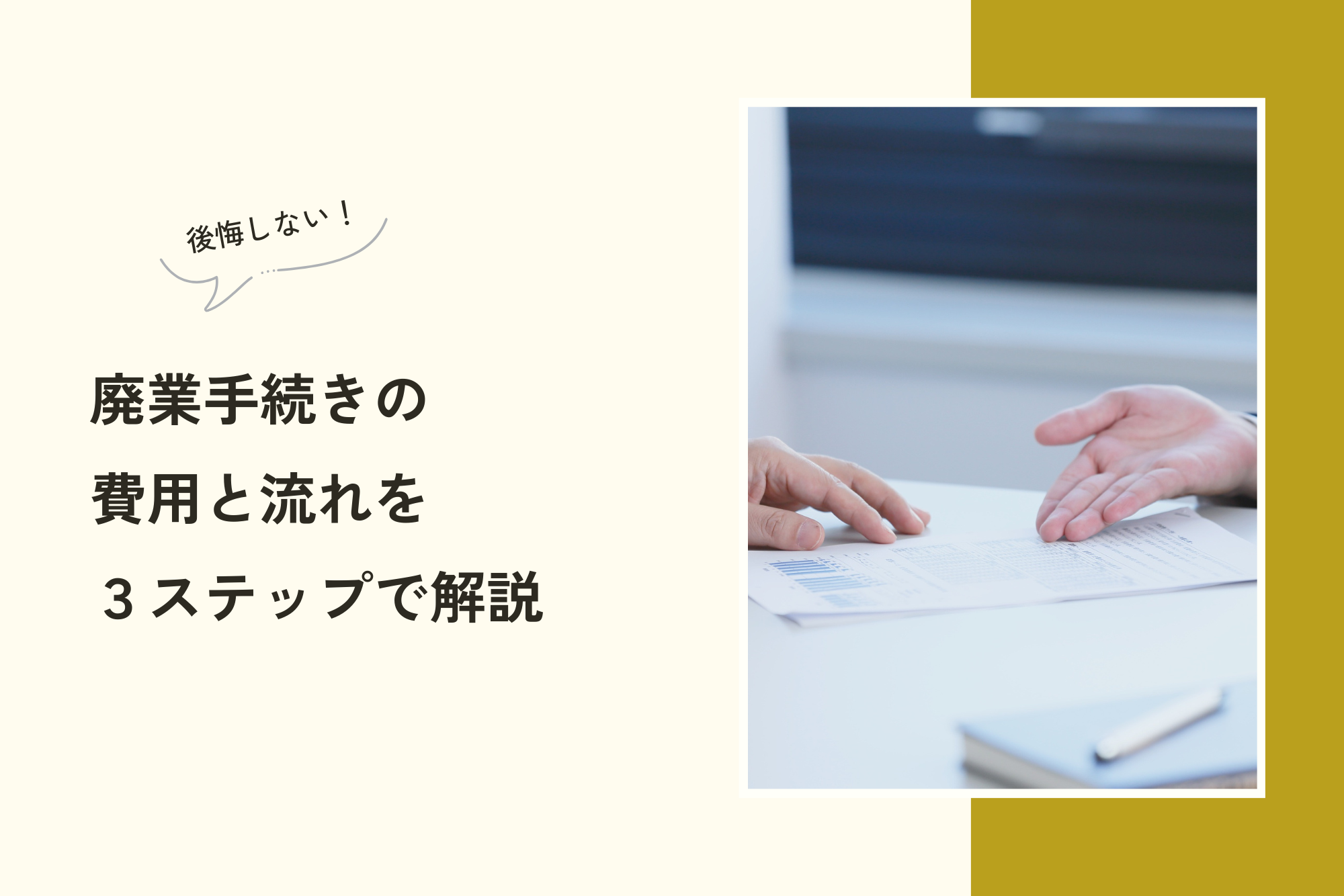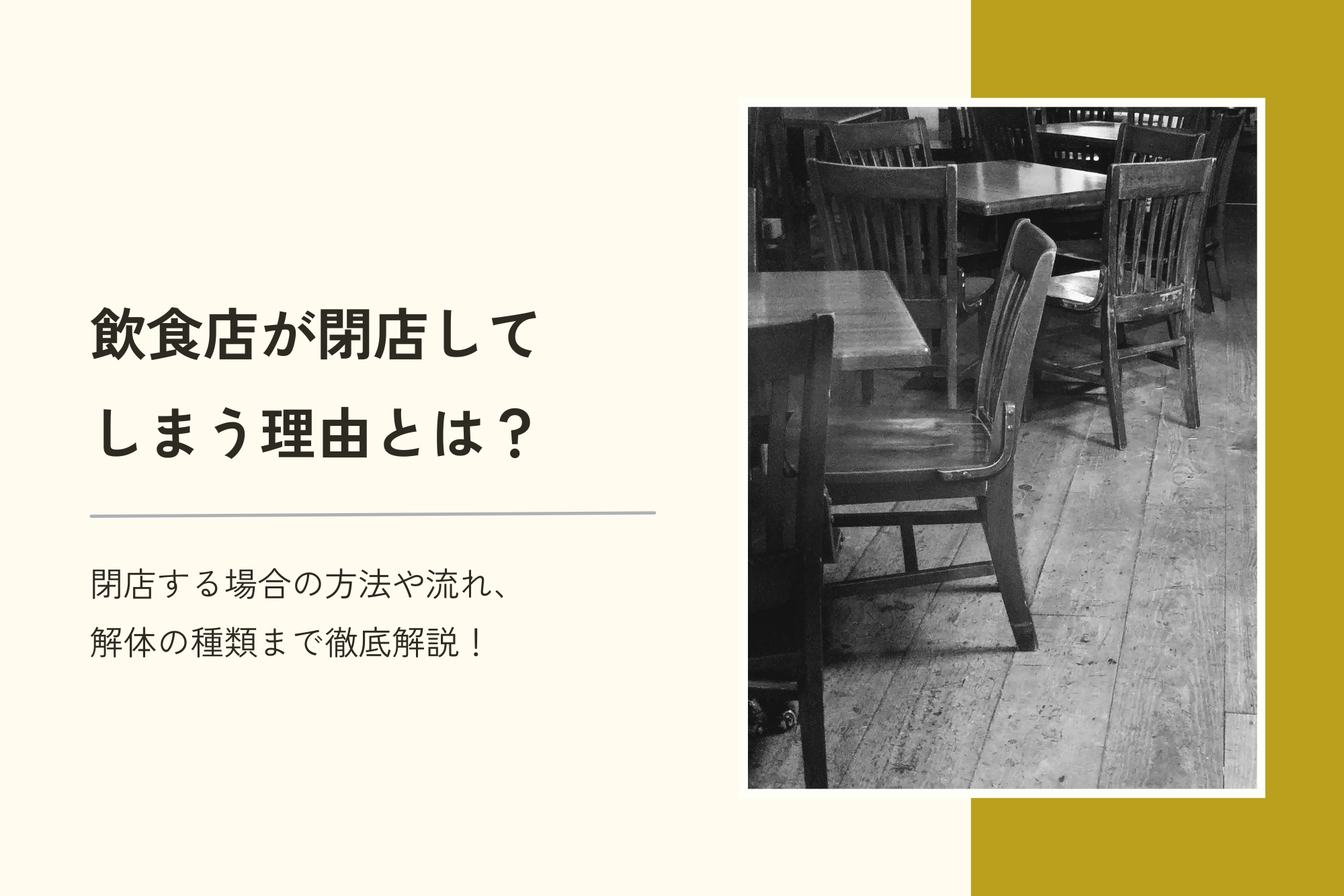
飲食店を経営していると、様々な理由で閉店を検討せざるを得ない時が訪れるかもしれません。実際、多くの飲食店が様々な要因で日々閉店しています。
本記事では、人手不足や資金不足といったよくある閉店理由から、閉店を決断した場合の具体的な手続き、店舗売却・業態変更・業務委託といった選択肢、さらには解体工事の種類まで、閉店に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。

飲食店が閉店してしまう理由とは?

飲食店を経営していく中で、様々な理由により閉店を選択せざるを得ない場合があります。閉店には、事業の継続が困難になるネガティブな理由だけでなく、新たな展開を目指すポジティブな理由も存在します。
店舗の移転による閉店
店舗の移転は多くの場合、経営の向上や新たな機会を追求するために行われます。新しい立地で営業を開始する際、現在の店舗の状況を慎重に整理することが重要です。
特に、原状回復費用や契約上の条件に注意を払い、効率的に移転作業を進めることが求められます。移転先の選定は、立地条件や賃貸契約の詳細を比較検討しながら慎重に行い、経済的な負担を最小限に抑える工夫が必要です。
また、既存の顧客に対して移転情報を的確に伝えることで、サービスの継続利用を促すことが可能です。ポスターやフライヤー、会計時の案内など、多様な手段を活用することで、顧客との信頼関係を維持しつつ円滑な移転を実現できます。
人手不足による閉店
飲食業界では、人手不足が長期的な経営の課題として挙げられます。この問題が進行すると、従業員一人ひとりの業務負担が増大し、働く環境が悪化しかねません。
その結果として従業員の離職率が高まり、新たな人材を確保することがさらに難しくなる悪循環に陥りやすいのです。特に小規模店舗や家族経営の場合、従業員が欠けると、店舗運営自体が厳しくなるケースも見られます。
このような状況を回避するためには、労働環境の改善や柔軟な働き方の導入が必要不可欠です。また、求人募集を行う際には、給与条件や福利厚生を周囲の店舗と比較し、魅力的な労働条件を提示する工夫も重要です。こうした対策を講じることで、安定した店舗運営が期待できます。
運転資金不足による閉店
飲食店の閉店理由として多く見られるのが、売り上げの停滞や資金繰りの悪化による業績不振です。当初の計画通りに売り上げが伸びなかったり、予想以上の運営コストが重なったりすると、資金が不足し、店舗経営が行き詰まる場合があります。
この状況を改善するには、まず運営コストや売上構造の見直しを行い、収支のバランスを整えることが重要です。また、資金不足により取引先への支払いが滞ることは避けなければなりません。
不払いや遅延は信用を損ない、将来的な経営再建の妨げになります。状況を見極めながら早めの対策を講じ、必要であれば専門家のアドバイスを受けることで、経営の立て直しに繋がる可能性があります。
体調不良による閉店
飲食店の経営者が店舗を手放す理由として、健康上の問題が挙げられます。長時間労働や不規則な生活、そして休みが取りにくい環境により、体調を崩してしまうことは少なくありません。
特に、後継者がいない場合やスタッフに頼ることが難しい状況では、営業を続ける選択肢が限られてしまいます。一時的な休業で体調の回復を図る場合もありますが、症状が深刻であれば最終的に店舗の売却や閉店を余儀なくされることもあります。
こうしたリスクを軽減するためには、健康管理を優先することや、適切な労働環境の整備が重要です。また、早い段階で事業継承やサポート体制の構築を考えることが、将来の選択肢を広げる鍵となります。

飲食店を閉店する場合の方法は3つ

飲食店を閉店する理由は様々ですが、閉店を決断した場合、どのような方法があるのでしょうか。代表的な方法を3つご紹介します。
1.店舗を売却する
飲食店の店舗売却においては、居抜きの形式が一般的です。これは、厨房や空調設備をそのまま使用できるため、次のオーナーにとっては初期投資を抑えることができ、売り手側も設備をそのまま引き継いでもらえるというメリットがあります。
しかし、居抜きでの売却を行うためには、貸主からの許可を得ることが必須です。この許可を得ないまま売却を進めてしまうと、最終的には原状回復を行い、設備を取り除いてから売却する形に変更する必要が出てくることがあります。契約前に必ず確認しておくことが重要です。
2.業態を変える
廃業を避ける選択肢として、業態転換を検討する方法があります。昼と夜で異なる業態を運営する形や、完全に新しい業種へと切り替える形など、さまざまな方法があります。
ただし、業態転換には時間や資金が必要であり、準備不足のまま実施すると失敗するリスクが高まります。そのため、転換を決めた場合は、具体的な事業計画を立て、必要な資金を確保した上で実行に移すことが重要です。また、顧客ニーズをよく調査し、それに合った形での転換を進めることが成功への鍵となります。
3.第三者に業務委託する
廃業を避けつつ店舗を維持する方法の一つとして、第三者に運営を委託する選択肢があります。この方法では、店舗運営を専門的な知識や経験を持つ他者に任せることで、自身は別の事業や活動に注力しながら収入を得ることが可能です。
ただし、不動産契約は継続するため、家賃の支払い義務が残り、さらに経営が低迷した場合には委託料が加わり、金銭的負担が増えるリスクもあります。そのため、委託する相手の選定や契約内容の慎重な検討が成功の鍵となります。

飲食店を閉店する際の主な流れ

店舗を閉店する際には、いくつかの重要な手続きを順序立てて進める必要があります。まず、貸主に解約の意思を伝え、従業員や取引先、顧客に閉店の事実を周知します。
その後、行政機関への廃業届や関連書類の提出が必要です。ライフライン契約やリース品などの契約解除も早めに行い、店舗で使用していた不用品や設備については、譲渡やリサイクルを検討し、必要に応じて適切に廃棄処分します。
最終的には、原状回復工事を実施し、鍵を返却することで全ての手続きが完了します。各段階で準備を整え、スムーズな進行を心掛けることが重要です。

飲食店における解体の種類は3つ

飲食店を閉店する際、内装や設備を撤去するために解体工事が必要になります。解体の種類は主に3つあり、それぞれ費用や工期が異なります。状況に応じて適切な解体方法を選択することが重要です。
内装解体
内装解体とは、店舗やオフィスの内装部分を取り除く作業のことで、賃貸物件を退去する際の原状回復作業として行われることが一般的です。
この作業では壁やカウンター、間仕切りなどの内部造作が対象となり、天井や床の主要構造部分はそのまま残されることが多いです。解体範囲については、建物のオーナーや管理者と事前に協議し、具体的な作業内容を決定します。
特に飲食店では、厨房設備だけを撤去する場合もあります。重機を使うことは少なく、基本的に手作業で進められるため、丁寧な作業が求められます。このように、内装解体は次の入居者や建物の用途に合わせた準備の一環として重要な工程です。
スケルトン解体
スケルトン解体とは建物の構造部分を残し、それ以外の内装や設備をすべて撤去する工事を指します。この作業では、天井や壁、床、配管、そして備品類まで取り除き、建物を骨組みだけの状態にします。
内装解体と異なり、より大規模な工事となるため、内部を完全に空にすることが目的です。工事は手作業が中心となりますが、必要に応じて小型重機を使用する場合もあります。
スケルトン解体は、次に使用する目的や用途に応じて柔軟な準備を可能にするため、新たな店舗やオフィスを作る際に欠かせない工程です。
原状回復
賃貸物件の退去時には、原状回復工事を行うことが一般的です。原状回復とは、物件を入居前の状態に戻すことであり、契約内容に基づいて作業が進められます。飲食店の場合、改装して追加した厨房設備や内装はすべて撤去し、借りた当初の状態に戻す必要があります。
一方で、物件に最初から備わっていた設備は残しておくのが通常です。原状回復の範囲は、電気やガス、水道などのライフラインを含め、物件の管理者やオーナーと協議のうえで決定されます。スケルトン状態で借りた場合には、同様の状態に戻すことが求められます。このような工事は、契約内容をしっかり確認しながら進めることが重要です。

岡山の解体工事で「金山株式会社」が選ばれる理由

「金山株式会社」では、長年培ってきた豊富な経験と実績を活かし、周辺環境や近隣に配慮したスムーズで効率的な解体工事を実現しています。また、徹底した安全管理体制により、お客様の安心できるパートナーとして、ご支持をいただいています。
さらに、専門スタッフによるアスベスト調査や除去工事の対応も可能です。岡山県全域でお客様のニーズに合わせた柔軟な対応を心がけ、迅速で信頼性の高いサービスを提供しています。⇒金山株式会社へのお問い合わせはこちら

閉店 理由でよくある3つの質問

飲食店を経営する上で、よくある質問を3つ紹介します。これから飲食店を開業しようと考えている人はもちろん、現在経営している人もぜひ参考にしてみてください。
質問1.飲食業界の廃業率は?
中小企業庁の調査によると、飲食業と宿泊業の廃業率は5.6%と、全業種の中で最も高い水準にあります。1年以内に約30%、10年以内には約90%の飲食店が廃業してしまうとも言われており、業界の厳しさが浮き彫りになります。
この背景には、人手不足や経済環境の変化、世界情勢の影響など、多くの課題が存在します。一方で、飲食業・宿泊業の開業率は17.0%と他業種を大きく上回り、活発な入れ替わりが特徴的です。これらのデータから、飲食業は参入しやすい一方で、継続的な経営の難しさが高い業界であることが伺えます。
関連記事:飲食店の廃業率が高い8つの理由|潰れない店の特徴や回避策、よくある質問まで徹底解説! – 金山株式会社
質問2.飲食店を廃業する際の届け出の提出先は?
飲食店を廃業する際はまず、保健所に廃業届を提出して飲食店営業許可書を返納します。提出期限は一般的に営業終了日から10日以内ですが、地域により異なる場合があるため、事前に確認が必要です。
また、消防署には防火管理者解任届を提出します。これは明確な期限がないものの、営業終了後速やかに行うことが推奨されます。警察署への届出として、アルコール提供店舗は廃止届出書を提出し、風俗営業許可を持つ場合は許可証の返納も必要です。
さらに税務署への手続きでは、個人事業の廃業届や青色申告の取りやめ届など、条件に応じた書類の提出が求められます。これらの手続きは期限が定められているため、速やかに対応することが大切です。
質問3.飲食店を閉店する際の注意点は?
閉店を決定した際には、賃貸契約書を改めて確認することが欠かせません。解約予告期間や原状回復の条件が明記されており、これを踏まえて計画を立てる必要があります。スケジュールを明確にすることで、撤退にかかる費用や時間を最小限に抑えることができます。
また、保証金についても注意が必要です。契約書に「償却分の差し引き」などが記載されている場合や家賃の滞納がある場合、全額返金されないこともあります。返金時期もオーナーによって異なるため、費用計画に影響が出ないよう事前に確認しましょう。
さらに、スタッフへの配慮も重要です。閉店が解雇に直結する場合、心情に寄り添い適切な対応を行うことで、モチベーションの低下を防ぎ、最後まで良いサービスを提供できる環境を整えることが大切です。

まとめ

飲食店閉店の理由は経営状況の悪化や人手不足、オーナーの体調不良など多岐に渡ります。本記事では、閉店理由の解説に加え、閉店する場合の選択肢(売却、業態変更、業務委託)や手続きの流れ、解体の種類についても詳しく説明しました。飲食店経営者の方は、ぜひこの記事を参考に、今後の経営戦略にお役立てください。
「金山株式会社」では、豊富な経験と実績を活かし、周辺環境や近隣に配慮したスムーズな解体工事を実現しています。岡山県全域でお客様のニーズに合わせた柔軟で信頼性の高いサービスを提供していますので、ぜひお気軽にご相談ください。⇒金山株式会社へのお問い合わせはこちら