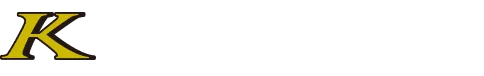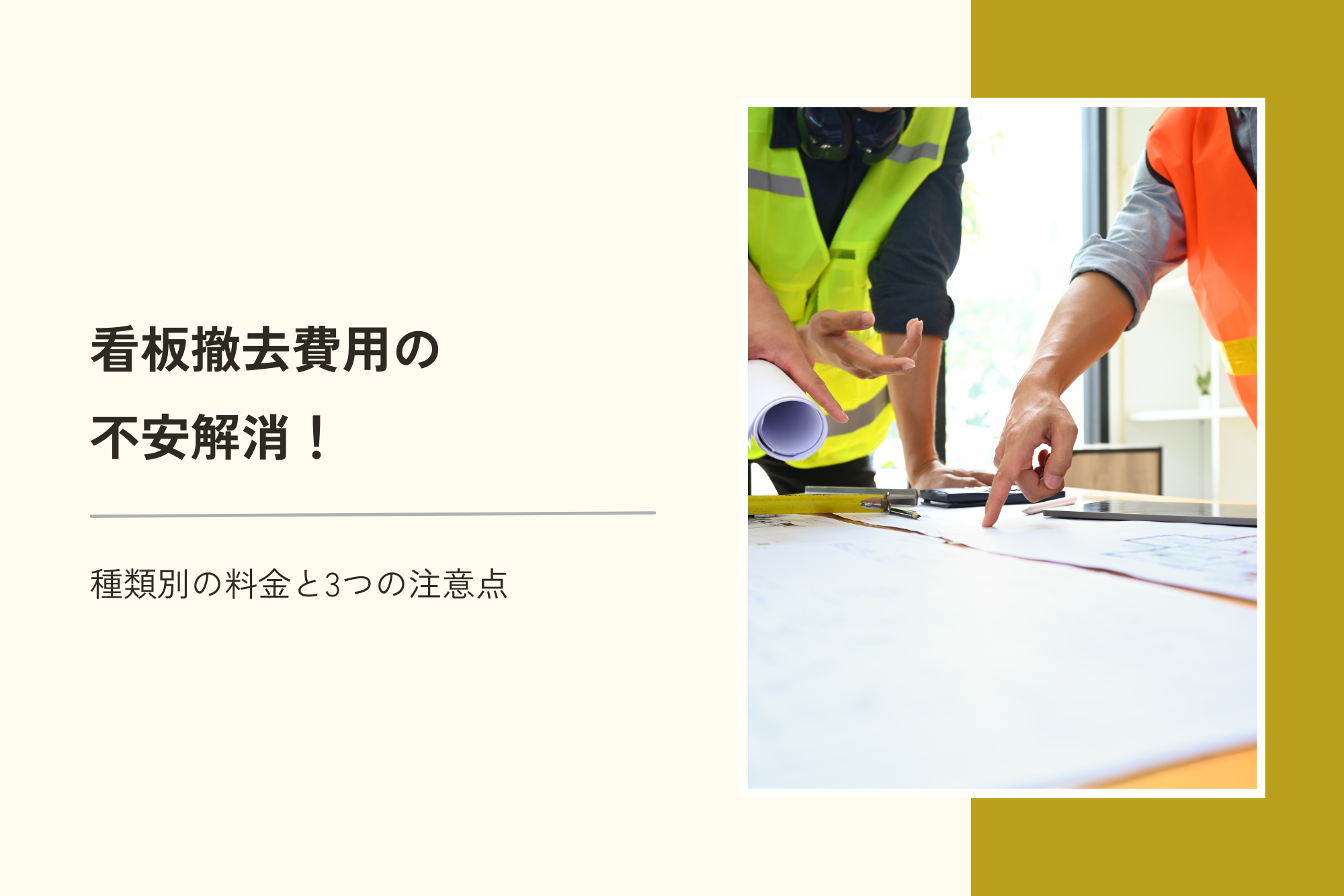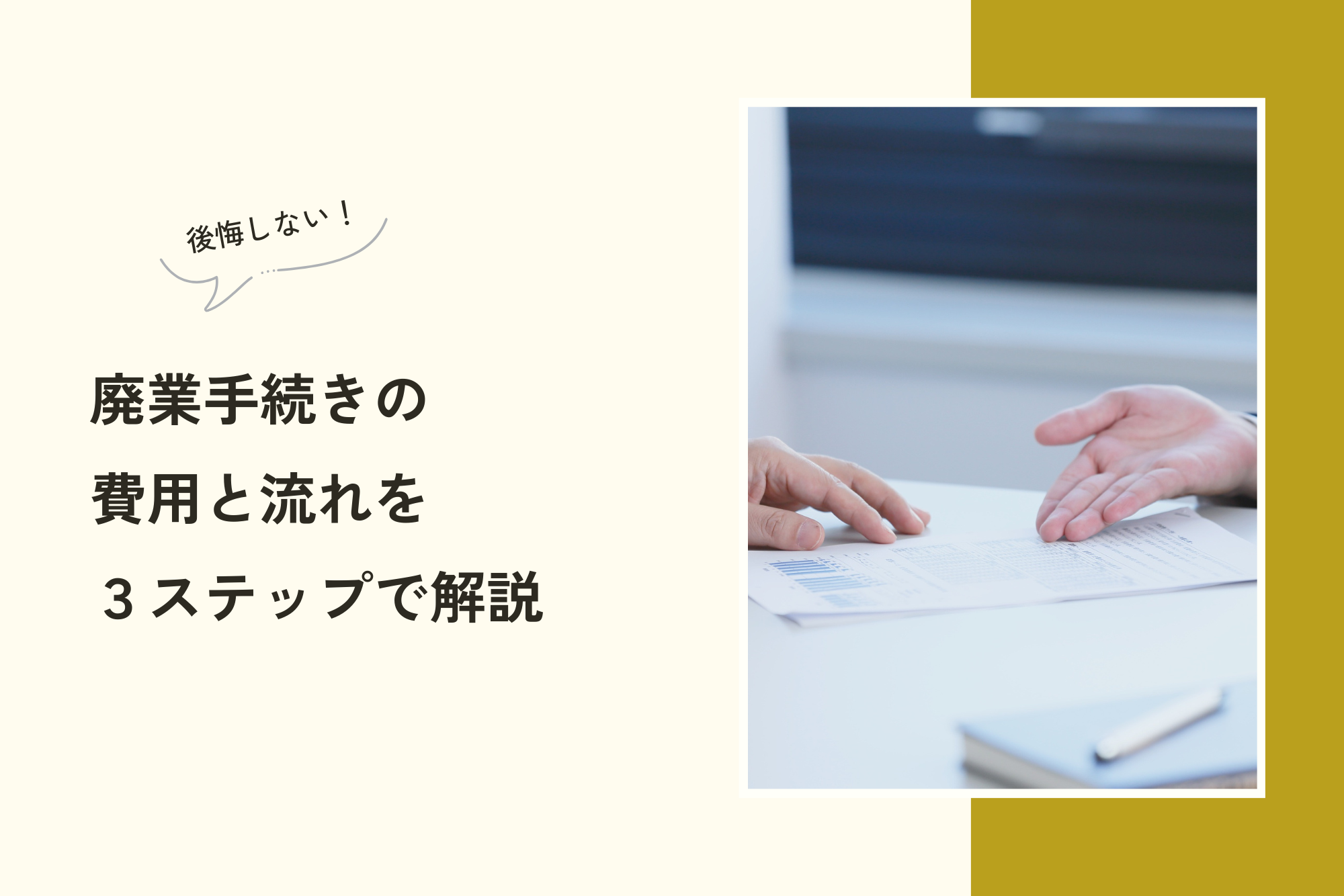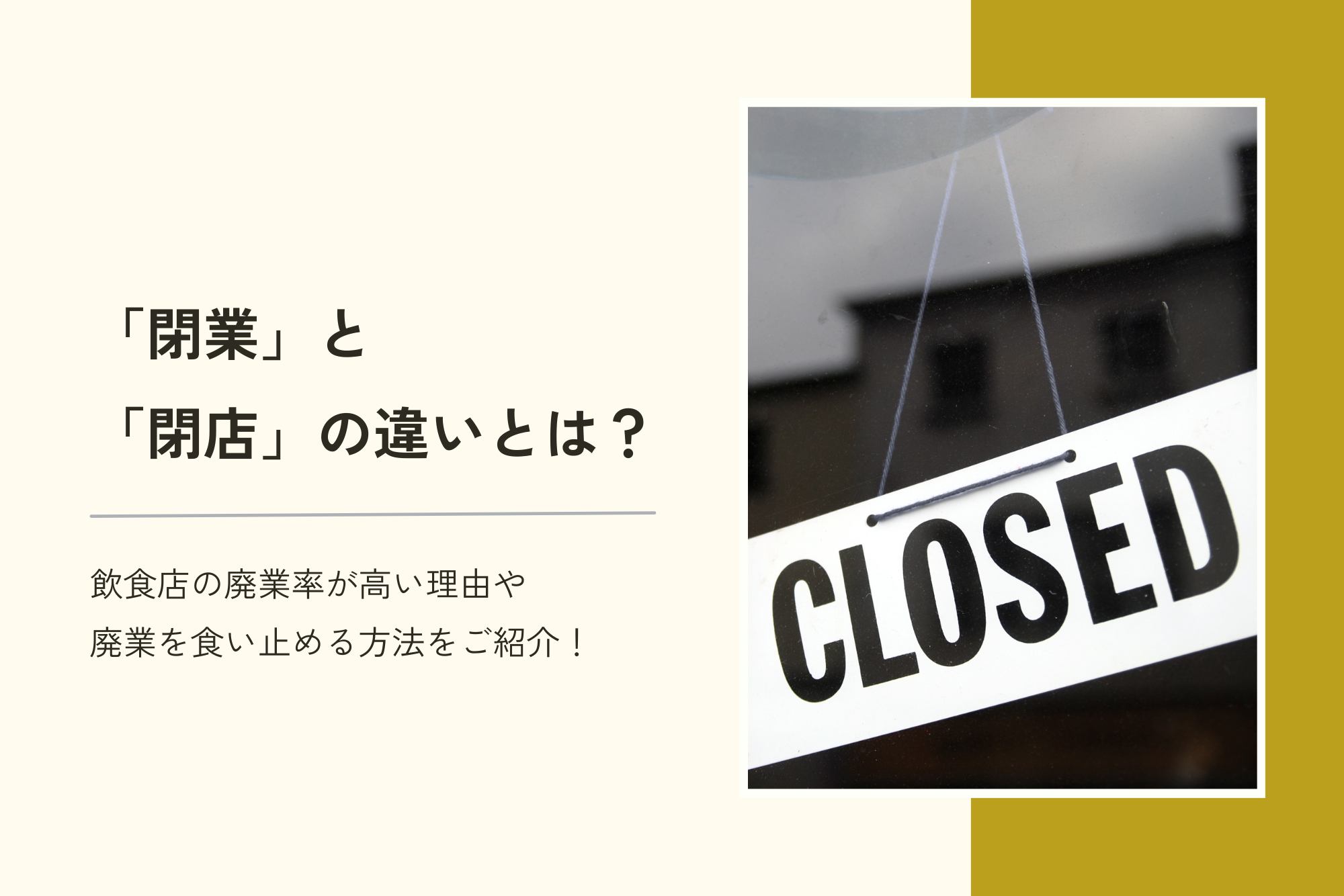
事業を終了する際に耳にする「閉業」「閉店」「廃業」といった用語は一見似ていますが、実際には異なるプロセスや特徴を持つ重要な概念です。
本記事では「閉業」と「閉店」の違いを中心に、飲食店の廃業率の高さやそれを防ぐための方法など、経営者にとって知っておきたいポイントを詳しく解説します。またよくある質問についても回答していますので、ぜひ参考にしてみてください。

「閉業」と「閉店」の違いとは?

「お店がなくなる」という意味で同じように使われる「閉業」と「閉店」。 実は、その意味合いには明確な違いがあります。 それぞれの詳しい内容をみていきましょう。
閉店の定義
閉店とは、店舗を持つ事業がその営業を終了することを指す言葉です。この終了には、一時的なものと永続的なものの両方が含まれます。一時的な閉店は改装や設備点検などの理由で行われることが多く、再開が前提です。
一方、永続的な閉店は店舗運営そのものの終了を意味し、売上不振や経営方針の変更などがその理由となるがあります。このような状況では、閉店後に跡地が他の用途に転用される場合も少なくありません。
閉業と閉店の主な違い
事業の終了には「閉業」と「閉店」という2つの形態があり、それぞれ異なる特徴を持ちます。「閉業」とは会社全体の活動が終了することであり、通常は恒久的なもので、法的手続きや解散の手続きが必要となります。
一方で「閉店」は特定の店舗や営業拠点が業務を停止することを指し、企業全体の活動に直結しない場合が多いのが特徴です。閉店は一時的な戦略として行われることもあり、再開の可能性を含むケースがあります。
これらの違いを理解することは、事業運営や経営判断を行う上で重要であり、適切な対応を可能にします。

「閉業」と「廃業」の違い

「閉業」と「閉店」はどちらも事業活動の終了を指しますが、その範囲や手続きには大きな違いがあります。それぞれの定義や特徴、実務上のポイントを解説します。
廃業の定義
廃業は法人や個人事業主が事業活動を完全に終了し、市場から撤退することを指します。この過程では事業再開の意図がなく、主体そのものが消滅する点が特徴です。
廃業の理由としては、経営上の困難や後継者不足などが挙げられますが、どのような理由であれ、廃業は経営者や従業員にとって大きな転換点となります。
法人が廃業する場合、清算や株主総会の決議といった複雑な手続きが必要で、これには多くの時間と計画が求められます。最終的に法人格が消滅するため、事業者にとっては慎重な判断が不可欠です。
閉業と廃業の主な違い
閉業と廃業は似たような概念ですが、実際には異なる特徴を持つ重要なビジネス用語です。閉業は事業活動の停止を意味しますが、法人自体の存続には影響しない場合があります。
一方、廃業は法人や個人事業主が市場から完全に撤退し、事業そのものが消滅する状態を指します。廃業には、株主総会の決議や解散登記など、より複雑な法的手続きが伴うため、慎重な計画が求められます。
閉業は事業の再構築や戦略的な方向転換の一環として行われる場合が多く、経済的な影響は限定的であることが一般的です。これらの違いを明確に理解することで、経営者は適切な判断を下し、事業終了のプロセスを効果的に進めることができます。

飲食店の廃業率が高い3つの理由

飲食店の廃業率が高いのは初期投資や運転資金の問題、経営者の高齢化など、様々な要因が考えられます。 ここでは、飲食店が廃業に追い込まれる3つの大きな理由について解説します。
1.初期投資額が大きい
飲食店を開業する際には、多額の初期投資が避けられません。物件の賃貸料や内装工事費用、厨房機器の購入費などが主な出費となり、これらはしばしば数百万円から1,000万円近くに達することがあります。
このような初期費用は開業後の収益で回収する必要があり、順調な売上が見込めない場合、経営者にとって大きな負担となる可能性があります。そのため、初期投資を抑える工夫や、効率的な資金計画を立てることが重要です。成功する店舗運営には、資金面でのリスク管理が欠かせません。
2.運転資金が確保できていない
飲食店の開業は夢を叶える第一歩ですが、それに伴う資金計画は非常に重要です。初期費用の準備に加え、開業後の数ヶ月間の運転資金を確保しておく必要があります。
家賃や人件費、食材費といったランニングコストは毎月発生するため、売上が安定するまでの間、資金繰りに苦労する可能性があります。事業を成功させるには、収支計画を細かく立て、開業初期の赤字を想定した十分な資金を準備することが求められます。公共機関からの資金調達や効率的なコスト管理が経営を安定させる鍵となるでしょう。
3.経営者の年齢層が高い
飲食店業界では、経営者の高齢化が進行しており、後継者不足が深刻な課題となっています。特に個人経営の飲食店では、60歳以上の経営者が過半数を占める状況が多く見られ、70歳以上の割合も高まっています。
後継者が確保できている店舗は一部に留まり、多くの経営者が事業継続の見通しに苦慮しているのが現状です。この問題に対処するには、事業承継や売却の計画を早期に立てることが重要です。また、地域活性化や事業再編の取り組みを通じて、後継者候補や新たな事業形態の模索が必要でしょう。

飲食店の廃業を食い止める方法

厳しい状況が続く飲食業界の廃業を防ぐには、顧客ニーズの把握、効果的なマーケティング、そして徹底したコスト管理が不可欠です。具体的な対策方法についてみていきましょう。
1.飲食店の廃業を食い止める
飲食店の運営では顧客のニーズを理解し、それに応える商品やサービスを提供することが重要です。地域の特性や顧客の嗜好を把握するために市場調査を継続的に行い、得られたデータを基にメニューやプロモーションを工夫する必要があります。
最近では「健康志向」や「簡便化」、「経済性」といった消費者の志向が注目されており、特に健康を重視した選択が増加しています。これらのトレンドを踏まえ、ヘルシーなメニューの開発や利便性を高めるサービスを導入することで、競争力を強化できるでしょう。
また、広告やデジタルマーケティングを活用して、効果的に顧客へアプローチすることも欠かせません。
2.人件費を見直しする
飲食店経営において、人件費は経費の中で特に大きな割合を占めます。そのため、効率的な経費管理が必要です。
具体的には客数の動向を分析し、利用頻度が低い時間帯に対応したスタッフ配置の見直しや営業規模の調整を行うことで、無駄なコストを削減できます。また、業務の効率化も重要です。たとえば、POSレジやハンディ端末を導入することで注文の正確性を高めたり、厨房や洗い場で自動化機器を活用して作業の負担を軽減したりすることで、生産性の向上とコスト削減を同時に図れます。

閉業と閉店の違いでよくある3つの質問

飲食店の閉業に関するよくある3つの質問について解説します。閉業手続きをスムーズに進めるためもせひ参考にしてみてください。
質問1.飲食店の廃業時に必要な手続きや届け出は?
飲食店を廃業する際には、開業時と同様に各種行政機関への手続きが必要となります。まず税務署では「個人事業の開業・廃業等届出書」や「消費税の事業廃止届出書」などを提出します。
これらは廃業後すぐ、または1か月以内に対応が求められます。警察署への届け出は、深夜営業を行っていた店舗の場合に必要で「廃止届書」を廃業日から10日以内に提出します。
さらに、保健所では「廃業届」と共に営業許可書の返納が求められます。消防署への防火管理者解任届や、雇用保険に関連したハローワークでの手続きも重要です。これらの手続きは期日が定められている場合が多く、忘れずに進めることが求められます。
質問2.居抜き売却とは?
居抜き売却とは、店舗を退去する際に内装や厨房設備をそのまま次のテナントに譲渡する方法です。この仕組みを利用すれば原状回復工事の必要がなく、退去費用を大幅に削減できます。
また、解約予告期間内に新しいテナントに引き渡せれば、家賃の負担を避けることも可能です。さらに、譲渡する造作に対して造作譲渡料を受け取ることで、退去に伴う経済的なメリットも得られる場合があります。
ただし、この手続きには貸主の承諾が必要です。交渉が難しい場合や手続きをスムーズに進めたい場合には、専門の業者に相談することが有効な手段です。
質問3.飲食店は廃業率は?
飲食業は他の業界と比べて廃業率が高く、2022年度版の中小企業庁の調査によるとその数値は5.6%に達しています。これは全産業平均の3.3%を大きく上回り、非常に高い水準です。
さらに、飲食業は開業率も17.0%と全産業中で最も高く、業界内の入れ替わりが激しいことが特徴です。このような状況は、競争の激しさや経営の難しさを反映しており、新規参入の多さと同時に、経営継続の難易度が高いことを示しています。

まとめ

「閉業」「閉店」「廃業」は、いずれも事業の終了を意味する言葉ですが、その内容は異なります。閉業は事業全体の活動停止、閉店は事業拠点の営業停止を指し、廃業は事業の完全な終了と市場からの撤退という意味です。
特に飲食店は初期投資や運転資金の確保が困難で、廃業率が高い傾向にあります。顧客ニーズを的確に捉え、マーケティングとコスト管理を徹底し、廃業を防ぎましょう。