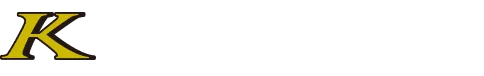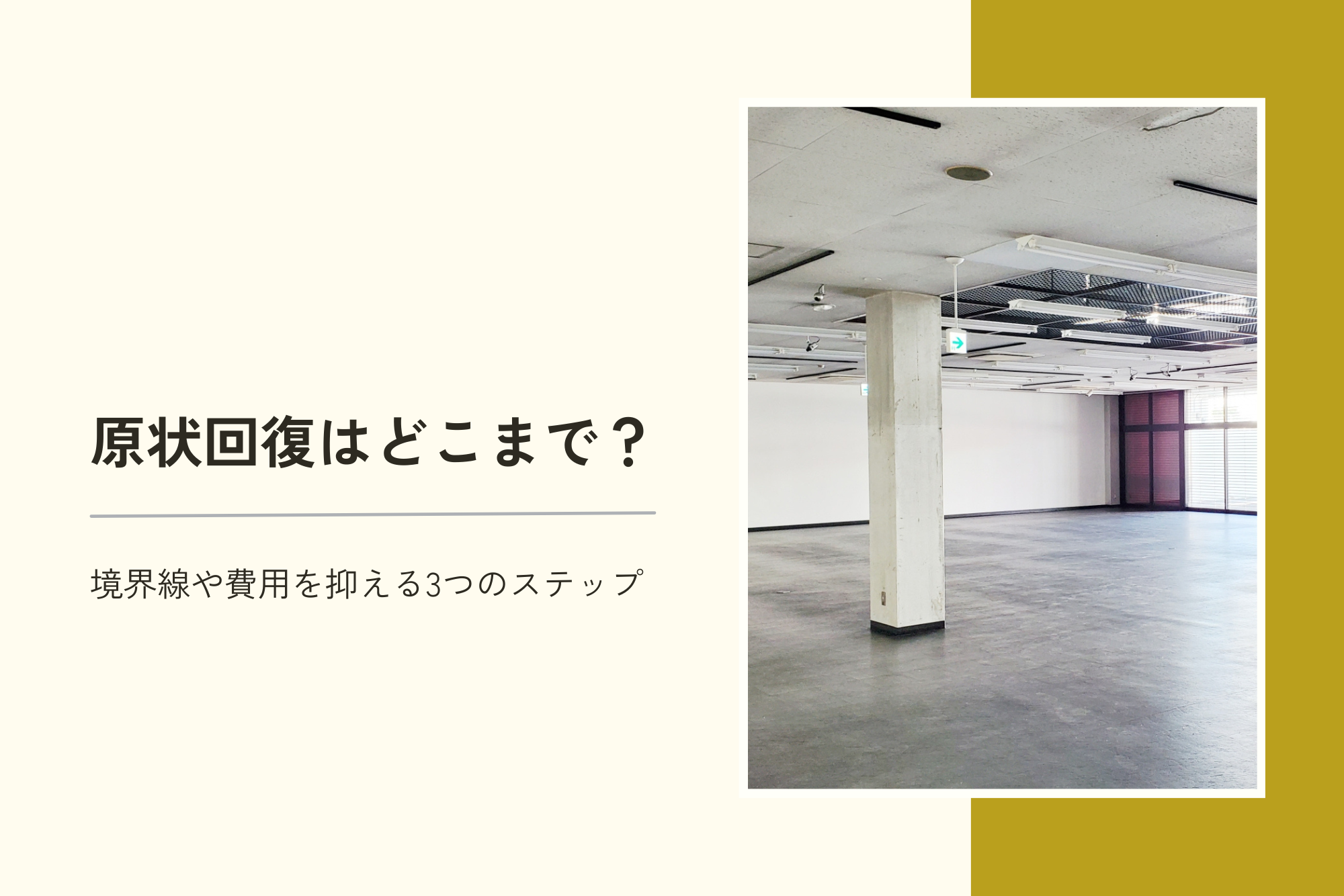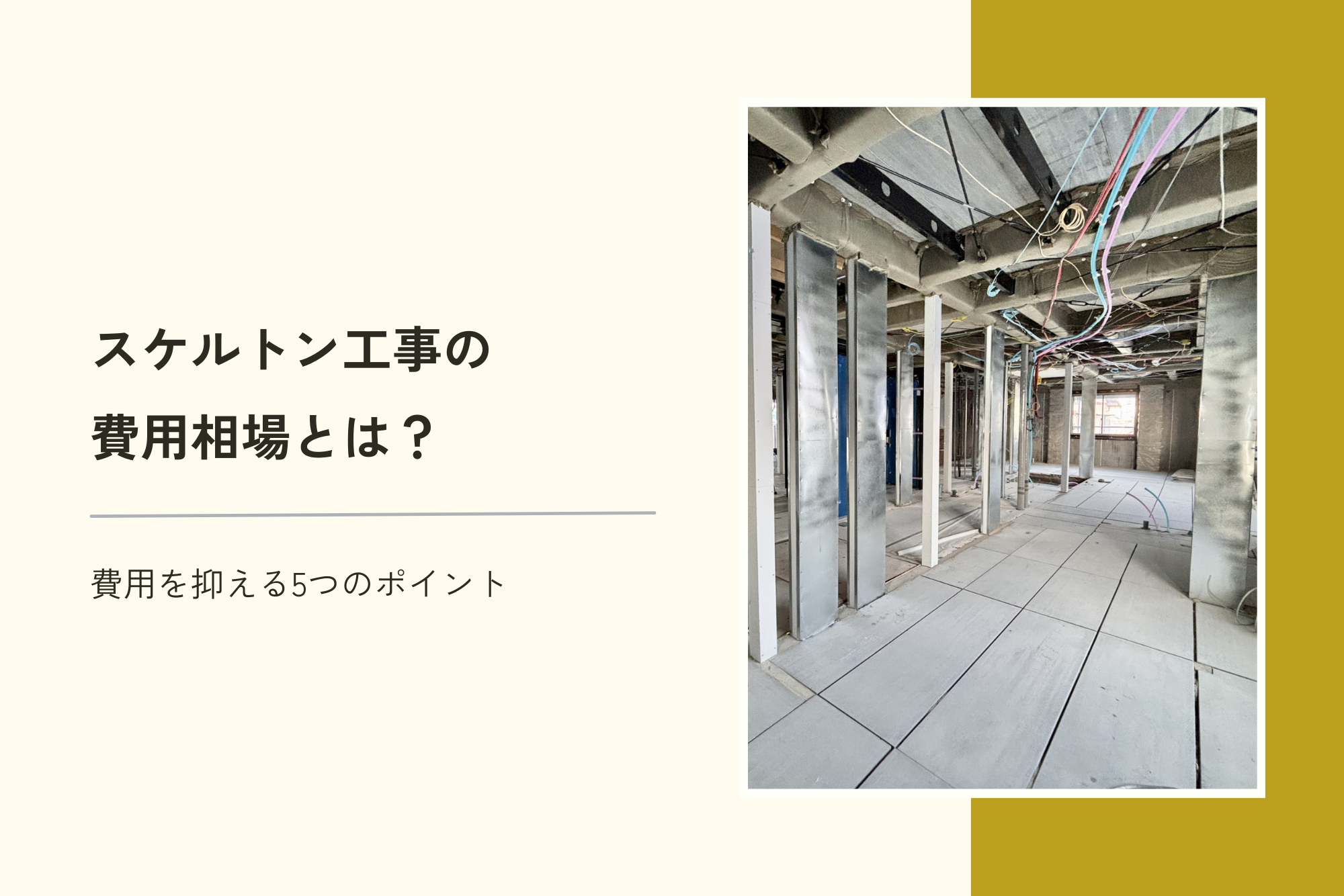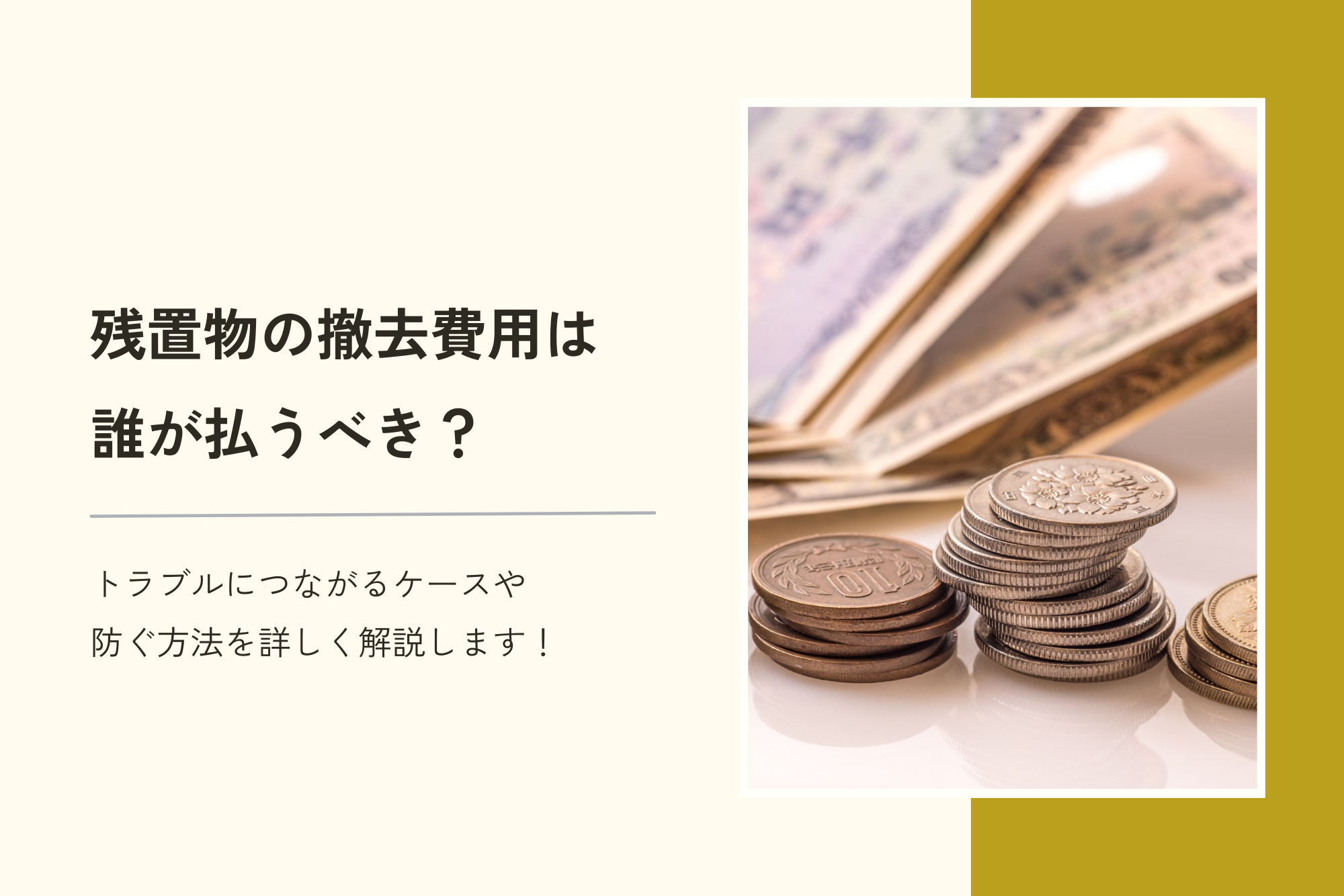
残置物の撤去費用の支払い義務について、誰が払うべきなのか気になっている方もおられるのではないでしょうか。残置物の撤去費用を巡るトラブルも少なくないため、正しい知識を身につけておくことが大切です。
本記事では、残置物の撤去費用は誰が払うべきかやトラブルにつながるケース、防ぐ方法をご紹介します。また、よくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

残置物の撤去費用は誰が払うべき?

残置物の処理費用は、貸主(大家さん)が負担するのが一般的です。これは、残された物の所有権が貸主にあると考えられるためです。
また、借主(前入居者)が事前の承諾なしに置いていった場合でも、一般的には貸主がその費用を支払う義務があります。しかし、所有権の受託に合意している場合は、借主(前入居者)が費用を負担する場合もあります。
残置物の所有権の受託を合意した場合
借主が残置物の所有権を引き受ける際には、解体費用と修繕費用の負担が発生します。この合意は、契約書の一部として締結され、物件を契約する際に署名されるのが一般的です。
契約書には「残置物の所有権は借主に移行する」と明記されており、借主がサインすれば、合意が成立します。もし、契約書に残置物の所有権に関する記述がなければ、貸主が引き続き所有権を持ち、解体費用や修繕費用を負担しなければなりません。

残置物がトラブルにつながる3つのケース

次は、残置物がトラブルにつながるケースについて解説します。
- 所有権
- 補償にかかる費用負担
- 原状回復の範囲
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.所有権
無断で退去した借主が設備や備品を残した場合、所有権の問題がトラブルを引き起こします。残置物があると、所有権が借主に残るため、貸主が勝手に処分するのは法的に認められていません。
もし、違法に処分した場合、刑事責任や民事責任が生じる可能性があります。また、残置物がある限り次の借主を迎えられないため、貸主は撤去や所有権の譲渡を求める必要があり、解決には時間と費用がかかります。
2.補償にかかる費用負担
物件の賃貸契約において、前借主が残した設備や備品が存在する場合、所有権は一旦貸主に移ります。契約を結ぶ際に、残置物の管理責任や修繕費用の負担について明確に定めておかないと、トラブルになる可能性があります。
また、新たな借主が残置物を使用していて故障が発生したケースを想定し、修理費用をどちらが負担するかを契約で明示することが大切です。
3.原状回復の範囲
賃貸借契約の締結においては、退去時の原状回復に関する条項を詳細に定めることが大切です。居抜き物件の場合、前賃借人が残した設備や物品の扱いについて明確にしておかなければ、費用負担を巡るトラブルが発生する可能性があります。
たとえば、貸主が前借主の残置物を新借主に貸与する場合、設備がすぐに故障した場合でも、修繕の責任が誰にあるのかを事前に取り決めておかなければ、双方にとって不利益な状況が生じかねません。

残置物によるトラブルを防ぐ方法は3つ

次は、残置物によるトラブルを防ぐ方法について解説します。
- 退去時の立会いは必ず実施する
- 貸主所有の設備をリストアップする
- 造作譲渡契約を締結する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.退去時の立会いは必ず実施する
退去手続きにおいては、物件の状態を確認し、残置物がないか確認するまで鍵の受け取りを避けなければなりません。鍵を受け取ると、物件が適切に返還されたと見なされるため、原状回復が完了するまで、借主と連絡を密に保ち、設備や残置物が撤去されているか自分の目で確認しましょう。
このため、提携している産業廃棄物の回収業者や設備工事の業者があれば借主に紹介し、借主がスムーズに退去できるよう支援するのがおすすめです。
2.貸主所有の設備をリストアップする
賃貸借契約を結ぶ前には、貸与する物件や設備、備品に関する詳細を具体的にリスト化しておきましょう。それぞれの設備や備品の修理や撤去が必要になった場合、どちらが費用を負担するか、退去時の原状回復がどの程度求められるかについて、借主と合意した内容を記録する必要があります。
また、契約開始前の設備の状態を写真や文章で記録して、新借主と共有するのもおすすめです。これらの記録は、契約書作成やトラブル防止に役立つため、細心の注意を払って作成しなければなりません。
3.造作譲渡契約を締結する
居抜き物件の賃貸借契約を締結する際には、賃貸契約に加えて造作譲渡契約の締結が必要です。造作譲渡は、前借主が設置した内装や設備を、そのまま新借主へ引き継ぐ方法です。
たとえば、店内の内装や備品には、壁や床、天井、テーブル、椅子、厨房機器などが含まれます。しかし、前借主の残置物の状態が不明瞭な場合、無償で譲渡される可能性もあります。
このため、修理費用や退去時の原状回復についても、契約書に明記することが大切です。
なお、造作譲渡については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:造作譲渡とは?メリット・デメリットや円滑に進める方法を詳しく解説します!

残置物の撤去費用は誰が払うでよくある3つの質問

最後に、残置物の撤去費用は誰が払うでよくある質問について紹介します。
- 質問1.設備と残置物の違いは?
- 質問2.残置物の撤去費用の相場は?
- 質問3.残置物の撤去業者を選ぶポイントは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.設備と残置物の違いは?
店舗を借りる際に、エアコンやガスコンロ、トイレの温水洗浄便座など、あらかじめ設置されている設備があります。これらは「残置物」とは区別されず、「設備」として認識されます。
万が一、これらの設備が故障した場合、貸主が修繕の義務を負うのが一般的です。しかし、残置物については、修繕義務が貸主か借主のどちらにあるかは、契約内容によって異なる可能性があります。
質問2.残置物の撤去費用の相場は?
残置物の撤去費用は、内容や量によって大きく変動しますが、業者に依頼した場合、1㎥あたり3,000円〜5,000円程度が相場です。
この費用には、人件費や車両費、分別作業から搬出、運搬、処分までの一連の作業が含まれます。また、家具や家電のような粗大ごみや、薬品、バッテリーなど特別管理が必要な産業廃棄物の処理は、専門業者を通じて実施する必要があります。
これが、撤去費用を増加させる要因となる場合もあるため、撤去を依頼する際には、これらの要素を考慮したうえで業者を選ぶことが大切です。
質問3.残置物の撤去業者を選ぶポイントは?
残置物の撤去業者を選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
- 原状回復工事も対応可能
撤去だけでなく、原状回復も可能な業者に依頼すると、退去時の手続きを一本化できるため、効率的な処理が期待できる
- ビフォーアフターのサポートが充実している
残置物の一時保管や買取、クリーニングなど、多様なサポートを提供する業者を選べば、コストを抑えつつ、多くのメリットがある
- 見積もりが明確である
見積もりの内容が詳細で、追加料金の発生しない透明性の高い業者が信頼できる
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を持っている
法的な許可を持ち、産業廃棄物マニフェストを発行できる業者を選べば、違法な処理を避けられる
- 不用品買取資格を持っている
古物商許可証といった、不用品の買取資格を持つ業者に依頼する場合は、売却も可能であり、結果的に見積もりが抑えられる可能性がある

まとめ

本記事では、残置物の撤去費用は誰が払うべきかやトラブルにつながるケース、防ぐ方法をご紹介しました。
残置物の撤去費用の負担は、所有権と契約内容にもとづいて決定されますが、貸主の負担になるのが一般的です。また、残置物が原因でトラブルが生じる主なケースは、所有権や補償費用の負担、そして原状回復の範囲に関する認識の違いがあります。
これらのトラブルを防ぐためには、退去時の立会いを徹底し、貸主所有の設備を明確にリストアップしておく方法や造作譲渡契約を締結するなどの方法が有効です。これらの対策を講じておけば、トラブルを未然に防ぐことができ、双方にとって公平な解決を実現できます。