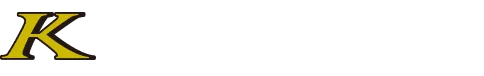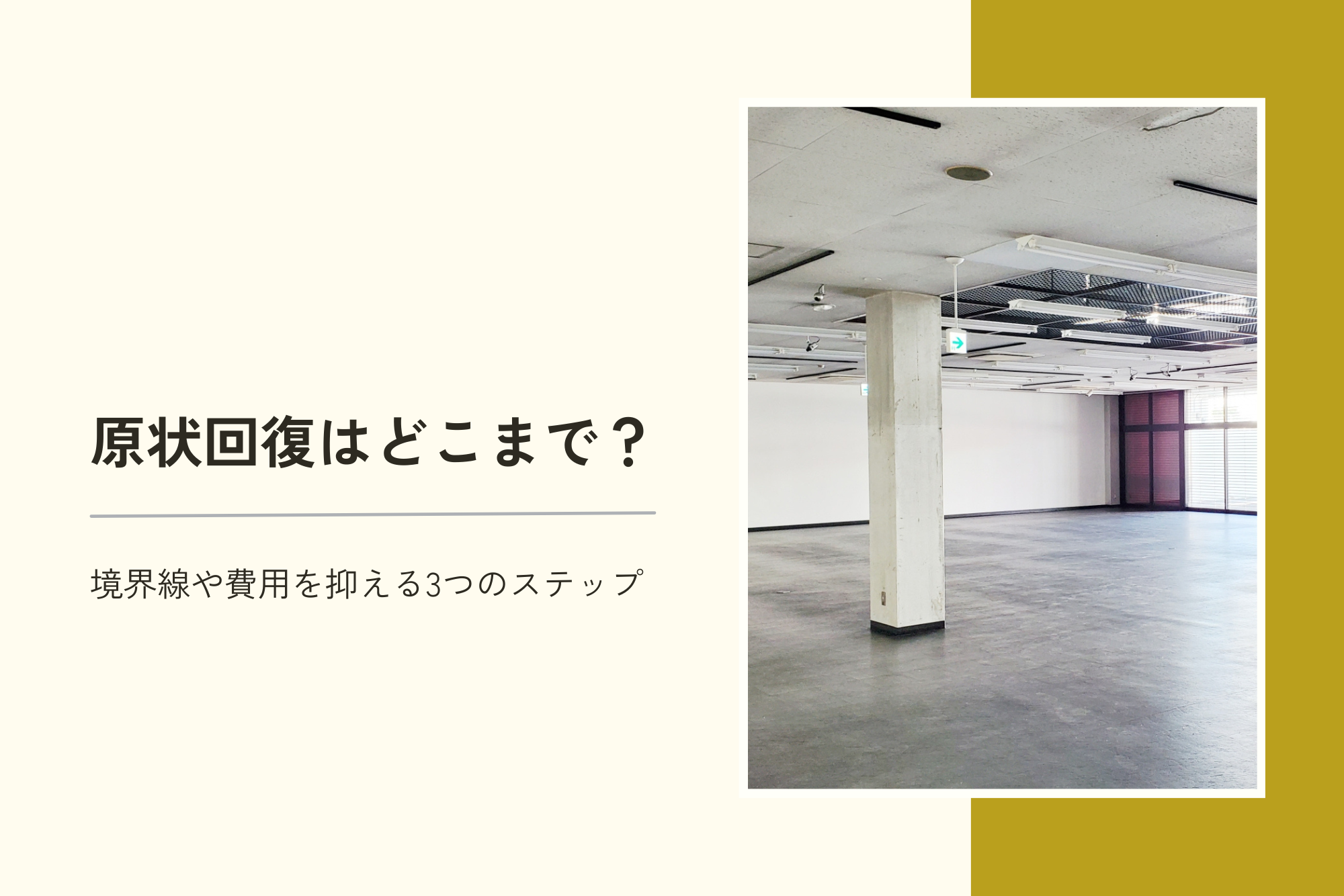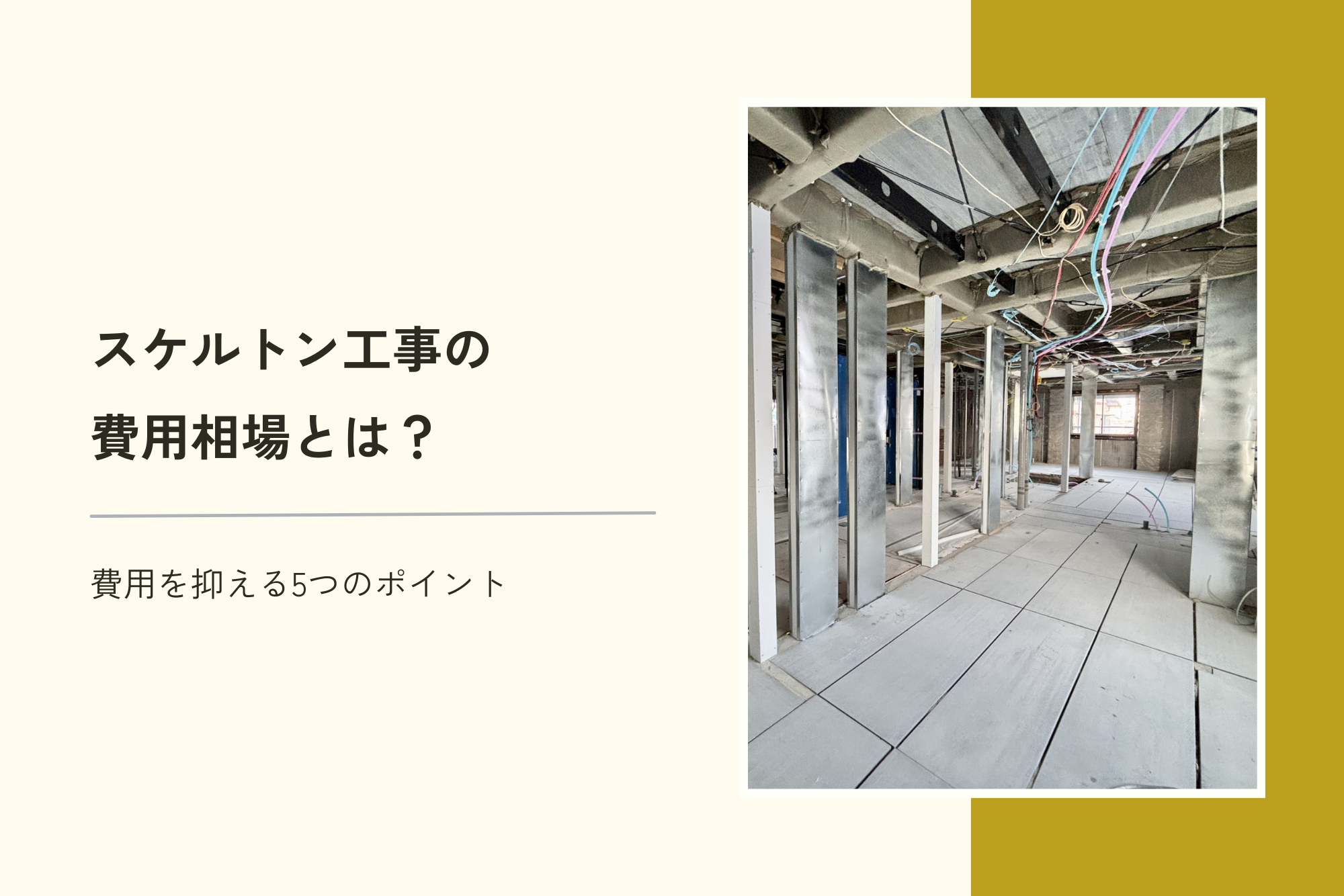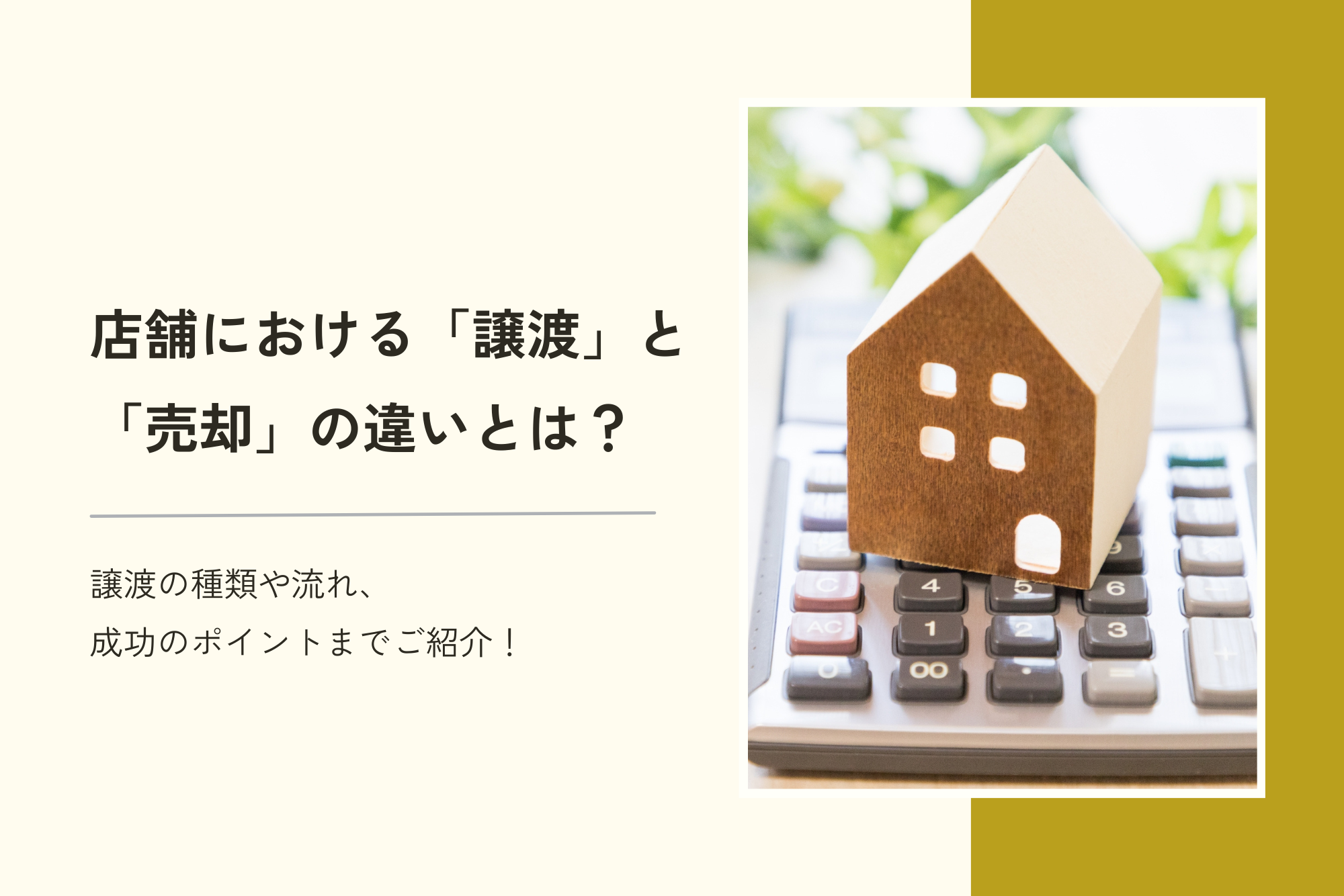
店舗における「譲渡」と「売却」は、どちらも店舗を他者に引き継ぐ方法ですが、意味や手続きが異なります。さらに、譲渡にはさまざまな種類があるため、詳しく知りたいという方もおられるのではないでしょうか。
本記事では、店舗における「譲渡」と「売却」の違いについてご紹介します。また、譲渡の種類や流れ、成功のポイントも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

店舗の「譲渡」とは?

譲渡は一般的に売却を指しますが、売却は金銭のやりとりを伴う有償の取引であるのに対し、譲渡には無償の取引も含まれます。そのため、権利や財産、法律上の地位などを譲り渡す行為を譲渡と呼びます。
また、法律や税金に関する条文では譲渡が用いられ、売却は使用されません。具体的に、土地や一戸建て、マンションなど不動産の譲渡とは、権利を有償で譲るという意味です。
「譲渡」と「売却」の違い
譲渡とは、所有資産の移転全般を指し、売買や贈与、交換、公売、財産分与などの行為が含まれます。不動産の譲渡においては、有償・無償を問わず権利の移転を意味しますが、一般的に「売却」との違いに注意が必要です。
売却は対価を受け取って資産を売り渡す行為であり、有償での取引を意味するため、無償での譲渡を含む譲渡全般とは異なります。不動産の交換も譲渡に該当し、譲渡所得税の対象です。
「譲渡」と「贈与」「相続」「交換」の違い
贈与とは、ある人が無償で他人に財産や物品を渡す行為です。贈与を受けた人は、贈与税を支払わなければなりません。
一方、相続とは、所有権を持っていた人が亡くなった際に、所有権が別の人に移るケースを指します。これは「無償譲渡」ともいえますが、主に遺産相続の文脈で使用される言葉です。また、交換は金銭以外の物品を譲渡の対価として受け取る行為を指します。

譲渡(売却)の種類は3つ
の種類は3つ-1024x468.png)
次は、譲渡(売却)の種類について解説します。
- 造作譲渡
- 事業譲渡
- 株式譲渡
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.造作譲渡
造作譲渡とは、店舗の内装や設備をそのまま次のオーナーに譲渡する方法です。店舗の閉店時には、賃貸借契約に基づいて物件を借りる前の状態に戻すために、スケルトン工事が求められるのが一般的です。
スケルトン工事は、撤退にかかるコストを削減する手段として用いられています。この方法を利用すると、閉店時の高額な工事費用を節約できるだけでなく、場合によっては譲渡益を得られます。
また、次のオーナーにとっても、開業コストを抑え、短期間での開業が実現できるため、両者にとってメリットが大きいです。そのため、撤退の負担を軽減し、スムーズな店舗運営の移行を支援する有効な手段です。
なお、造作譲渡については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:造作譲渡とは?メリット・デメリットや円滑に進める方法を詳しく解説します!
2.事業譲渡
事業譲渡は、飲食店の経営に関わるすべてをオーナーに引き継ぐことを指します。店舗そのものや内装、厨房設備といった物理的な資産だけでなく、経営ノウハウやブランド力などの無形資産も含まれます。
後継者が見つからない場合でも店舗を存続できたり、採算の取れない部門のみを整理したりできるのがメリットです。経営層の高齢化が進むなか、事業譲渡は飲食業界全体の発展に貢献する手段として注目されています。
3.株式譲渡
株式譲渡は、飲食店の株主が保有する株式をすべて、または一部をほかの法人や個人へ譲渡する方法です。この手法は法人化された飲食店に限られ、個人事業主は利用できません。
経営者自身が株主である場合、売却により得られた利益は経営者のものとなります。株式の移動とともに、会社の債権や負債も譲渡先に移るため注意が必要です。

店舗の譲渡(売却)にかかる主な税金は3つ
にかかる主な税金は3つ-1024x468.png)
次は、店舗の譲渡(売却)にかかる主な税金について解説します。
- 譲渡所得税
- 法人税
- 印紙税
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.譲渡所得税
譲渡所得税は、個人事業主の飲食店オーナーが店舗を売却した際に発生する税金で、売却益に対して課されます。この税金に含まれるのは、「所得税」「住民税」「復興所得税」の3つです。
まず、売却時の利益を計算し、その金額に応じた税率を適用して納税額を算出します。利益の計算方法は、売却価格から不動産の購入費用や売却にかかる費用を差し引いて求められます。
詳細な計算方法や税率は、国税庁のホームページで確認しましょう。また、一定の条件を満たす場合に適用される「特別控除額」が存在し、税負担を軽減できる場合があります。
2.法人税
法人税とは、企業が法人として登記されている場合に課される税金です。飲食店などの事業活動から得られる収益や、店舗譲渡による売却益も法人の「収入」として計上されます。
これらの収入は合算して法人税が計算されるため、譲渡所得税のように個別に計算されるわけではありません。法人税の税率は年間収益に応じて異なり、一般的に事業年度終了後2か月以内に納付する必要があります。
たとえば、資本金1億円以下の企業の場合、収益が800万円以下であれば15%、それを超える部分には23.20%の税率が適用されます。
3.印紙税
印紙税は、特定の書類に課せられる税金であり、不動産取引などの契約書に対して適用されます。たとえば、「不動産売買契約書」や「不動産売渡証書」などの文書1通ごとに印紙税が必要です。
個人事業主や法人は、この税金を負担する義務があります。契約金額によって印紙税の額は異なるため、該当する収入印紙を購入し、契約書に貼付するのが納税手続きです。

【種類別】譲渡(売却)の流れ
の流れ-1024x468.png)
次は、種類別の譲渡(売却)の流れについて解説します。
- 造作譲渡
- 事業譲渡
- 株式譲渡
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.造作譲渡
造作譲渡の流れは、以下のとおりです。
- 契約内容のチェックと貸主への確認
店舗物件の契約書には、解約予告期間や原状回復工事についての記載があり、原状回復義務が含まれている物件は居抜き売却ができない。しかし、貸主に相談や交渉して、居抜き譲渡が可能になる場合もある
- 造作譲渡の専門業者への相談
店舗の契約内容を確認後、業者に相談し、造作譲渡の概要や希望を伝え、不安や悩みを相談する。仮査定してくれる業者も多いため、複数の業者に問い合わせて、自分に合った業者を選定する
- 業者が現地調査を行い査定
実際の店舗の立地や内装、外装の状態を確認し、譲渡価格を算出する。また、譲渡する備品や設備のリストも作成するため、レンタルやリース品は明確にしておく
- 買い手探しと内覧
専門業者は専用サイトに情報を掲載したり、内覧会などで購入希望者を探す。内覧では、譲渡する物件の内容を再確認してもらい、トラブル回避につなげる必要がある
- 売却条件の交渉・契約締結
交渉は業者を仲介するため、購入希望者が多いほど優位な交渉が可能。交渉が完了し買い手が決まれば、造作譲渡契約を締結する
- 賃貸借契約の解約と引き渡し
売り手は賃貸借契約を解約し、買い手が新たに貸主と契約を結ぶ。支払いが完了し、引き渡しが問題なく済んだ後、業者から売却益が振り込まれて譲渡が完了する
2.事業譲渡
事業譲渡の流れについては、以下のとおりです。
- 譲渡予定の事業の価値を算出
マーケットアプローチやコストアプローチを用いて、業界の動きや情勢も考慮して価格を決定する。専門的な知識や情報が必要なため、M&Aを得意とする仲介業者に相談し、プロのサポートを受けるのがおすすめ
- 譲渡先を探し交渉
M&A仲介業者やサイト、人脈を活用して事業譲渡の取引先を探す。後継者を探しながら、事業承継までに自社や現経営者である自分が何をするかをまとめたロードマップ「事業承継計画表」を作成する必要がある
- 基本合意書の作成と締結
基本合意書に、譲渡する事業の内容や譲渡額、引き継がれる従業員について詳細に記載する。意向表明書と基本合意書は法的効力を持たないが、双方の認識を一致させるのに有効
- デューデリジェンスの実施
デューデリジェンスは適正評価手続きで、譲受側が譲渡事業のリスクや価値、リターンを調査する。譲渡側は質疑応答に対応し、必要な書類やデータを提出する
- 取締役会での決議と事業譲渡契約
デューデリジェンスの結果をもとに、取締役会で事業譲渡内容を確認し、決議を実施する。不備があれば修正し、契約を締結する
- 報告書の提出と株主総会での決議
事業譲渡契約締結後、報告書を提出する。さらに、臨時報告書の作成や公正取引委員会への届け出もしなければならない
- 手続き
資産や権利関係の移転手続き、届出、許認可手続きを実施する。譲受側が主体となって実施するが、譲渡側も協力して手続きを円滑に進める
###3.株式譲渡
株式に譲渡制限がある場合の株式譲渡の流れについては、以下のとおりです。
- 価値算定と買い手探し
取引先などに譲渡候補がいる場合、その経営者に打診するのもひとつの方法。また、M&Aを支援する機関に相談するのもおすすめ
- 株式譲渡の承認請求と取締役会・株主総会
譲渡制限がある株式の場合、承認請求が必要。株式譲渡の承認請求書を作成し、提出して承認決議を行う
- 株式譲渡の契約締結
株式譲渡契約書を作成し、支払い期日や譲渡日、表明保証、譲渡側の会社情報や株式情報などを記載する。取引内容に応じて必要な項目が変わるため、専門家のチェックを受けるのが望ましい
- 株主名簿の書き換え請求や株主名簿記載事項証明書の交付請求と交付
契約締結後、株主名義書換請求書を提出し、株主名義の変更を依頼する。その後、株主名簿記載事項証明書を交付する
- 譲渡の公表と引き継ぎ
従業員や取引先の金融機関に株式譲渡を公表し、譲渡先には技術やノウハウの引き継ぐ
なお、飲食店の経営権の譲渡については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:飲食店の経営権を譲渡する株式譲渡とは?メリット・デメリットを詳しく解説します!
店舗の譲渡(売却)を成功させるためのポイントは3つ
を成功させるためのポイントは3つ-1024x468.png)
次は、店舗の譲渡(売却)を成功させるためのポイントについて解説します。
- 譲渡の目的を明確にする
- 貸主の承諾とリース契約を確認する
- 譲渡・売却の専門家へ相談する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.譲渡の目的を明確にする
店舗の譲渡(売却)を成功させるためには、譲渡の目的を明確にしましょう。譲渡の方法には、造作譲渡や事業譲渡、株式譲渡の3種類があり、それぞれに対象や範囲が異なります。そのため、売却や譲渡の対象や範囲を明確にすると、優先すべき行動が見えてきます。
たとえば、一部の事業を切り離して経営を継続するのか、物件そのものを譲渡するのかによって、準備や手続きが異なるため、目的の明確化が不可欠です。
2.貸主の承諾とリース契約を確認する
賃貸契約書を見直し、解約予告期間や原状回復義務についてしっかり把握しましょう。さらに、設備や機器のリース品とその契約期間についても、事前に確認しておくことが大切です。
これらの準備を怠ると、貸主や買い手との間でトラブルが発生する可能性があります。そのため、契約内容の確認と関係者との情報共有は十分にしなければなりません。
3.譲渡・売却の専門家へ相談する
飲食店の譲渡・売却を検討する際は、専門家のサポートを受けるのがおすすめです。専門家に相談すると、買い手の募集や交渉、価格の設定、譲渡のタイミングなど、専門的な視点からアドバイスを受けられます。
たとえば、M&A仲介業者やビジネスブローカーは、飲食店の譲渡に詳しいため、適切な買い手を見つけるサポートを提供してくれます。弁護士や会計士も、法律や税務の観点からアドバイスしてくれるため、譲渡に伴うリスクの軽減が可能です。

譲渡と売却の違いでよくある3つの質問

最後に、譲渡と売却の違いでよくある3つの質問について紹介します。
- 質問1.不動産の長期譲渡と短期譲渡の違いは?
- 質問2.廃業のために必要な手続きは?
- 質問3.店舗の閉店に必要な撤退コストの内容は?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.不動産の長期譲渡と短期譲渡の違いは?
譲渡所得税は、不動産の所有期間によって税率が変わる仕組みです。所有期間が5年以下の場合、「短期譲渡所得」として課税され、税率は通常より高くなります。
一方、5年を超えて所有していた不動産を譲渡する場合は、「長期譲渡所得」として扱われ、税率は低くなります。この違いにより、不動産の売却タイミングが税金に大きな影響を与えるため、売却計画を立てる際には、所有期間を十分に考慮しなければなりません。
質問2.廃業のために必要な手続きは?
飲食店を閉店する際には、譲渡手続きと共に廃業の届け出を行う必要があります。廃業に際して提出しなければならない主な書類は以下の3つです。
これらの書類は、すべて国税庁のウェブサイトからダウンロードが可能です。
- 個人事業の開業・廃業等届出書
個人事業主が廃業する際に必要であり、廃業日から一か月以内に税務署と都道府県税事務所に提出しなければならない
- 事業廃止届出書
課税事業者が廃業する場合に、消費税関連で提出しなければならない。この書類は廃業後、すみやかに税務署に提出する必要がある
- 所得税の青色申告の取りやめ手続き
青色申告の承認を受けていた事業者が取りやめる際に提出が必要で、取りやめる年の翌年3月15日までに提出しなければならない
質問3.店舗の閉店に必要な撤退コストの内容は?
飲食店舗の閉店に必要となる費用としては、以下があげられます。
- 賃貸借契約の解約までの料金
- 店内の設備や備品のレンタル、リースの費用
- 従業員への給与
- 退去するまでの水道光熱費
- 原状回復工事の解体工事費
- 廃棄物の処理や不要な道具を処分する費用
法人が廃業する場合には、以下の費用も発生します。
- 解散や清算人、清算結了の登記費用
- 官報での広告費
- 登記やその他の法手続きの依頼費用
原状回復工事の費用は多額になる場合が多いため、事前にしっかりと準備しておきましょう。

まとめ

本記事では、店舗における「譲渡」と「売却」の違いや譲渡の種類、流れ、成功のポイントをご紹介しました。
譲渡とは、有償・無償を問わず、所有資産の移転全般を含み、売買や贈与、交換、公売、財産分与などの行為を指します。一方、売却は、対価を受け取って資産を売り渡す行為であり、有償での取引のみです。
また、譲渡には、造作譲渡や事業譲渡、株式譲渡などの種類があります。それぞれ目的や手続きが異なるため、しっかりと理解して進めなければなりません。
専門的な知識や書類が必要となるため、M&Aコンサルティングや弁護士などに相談するのがおすすめです。