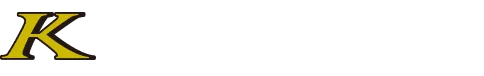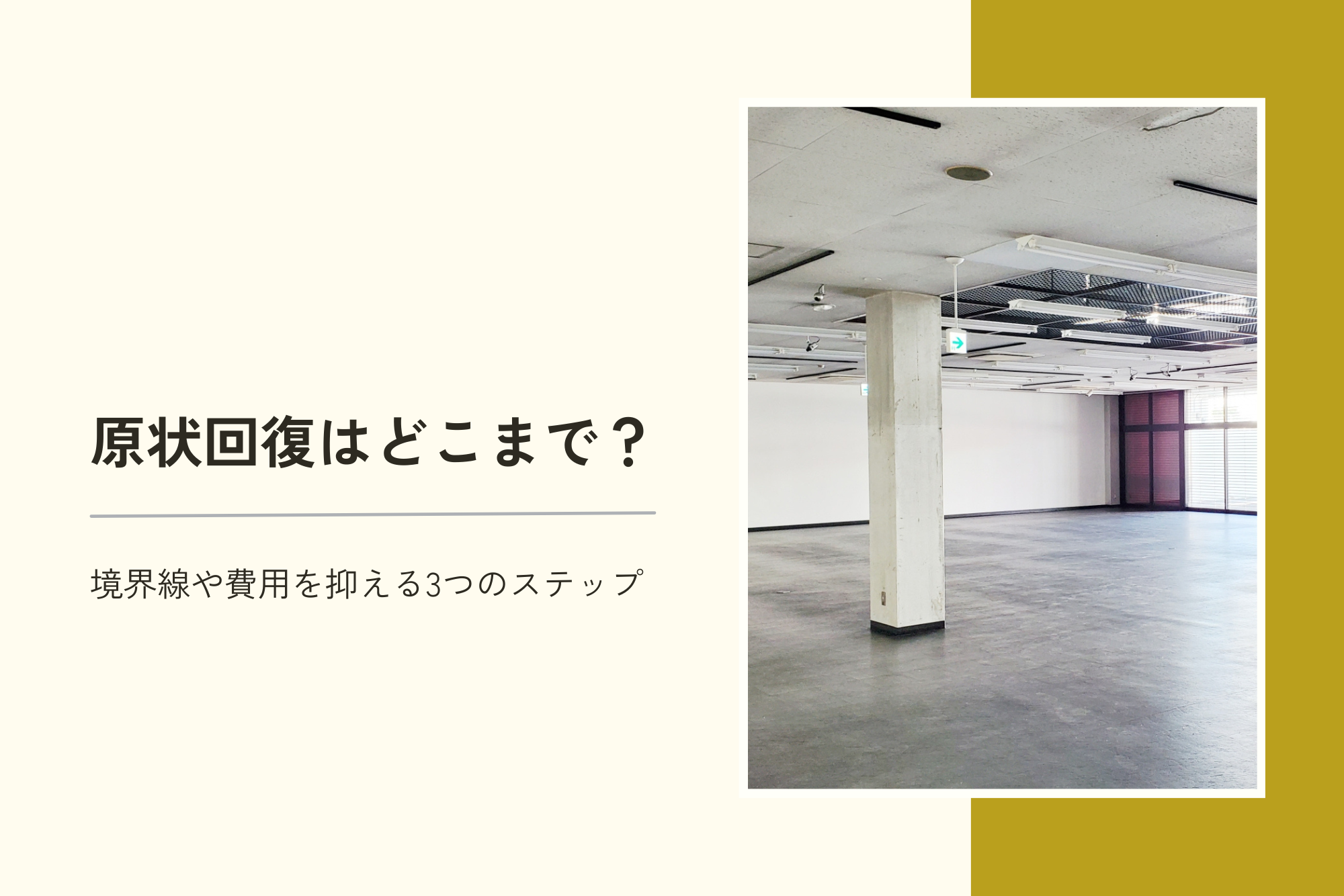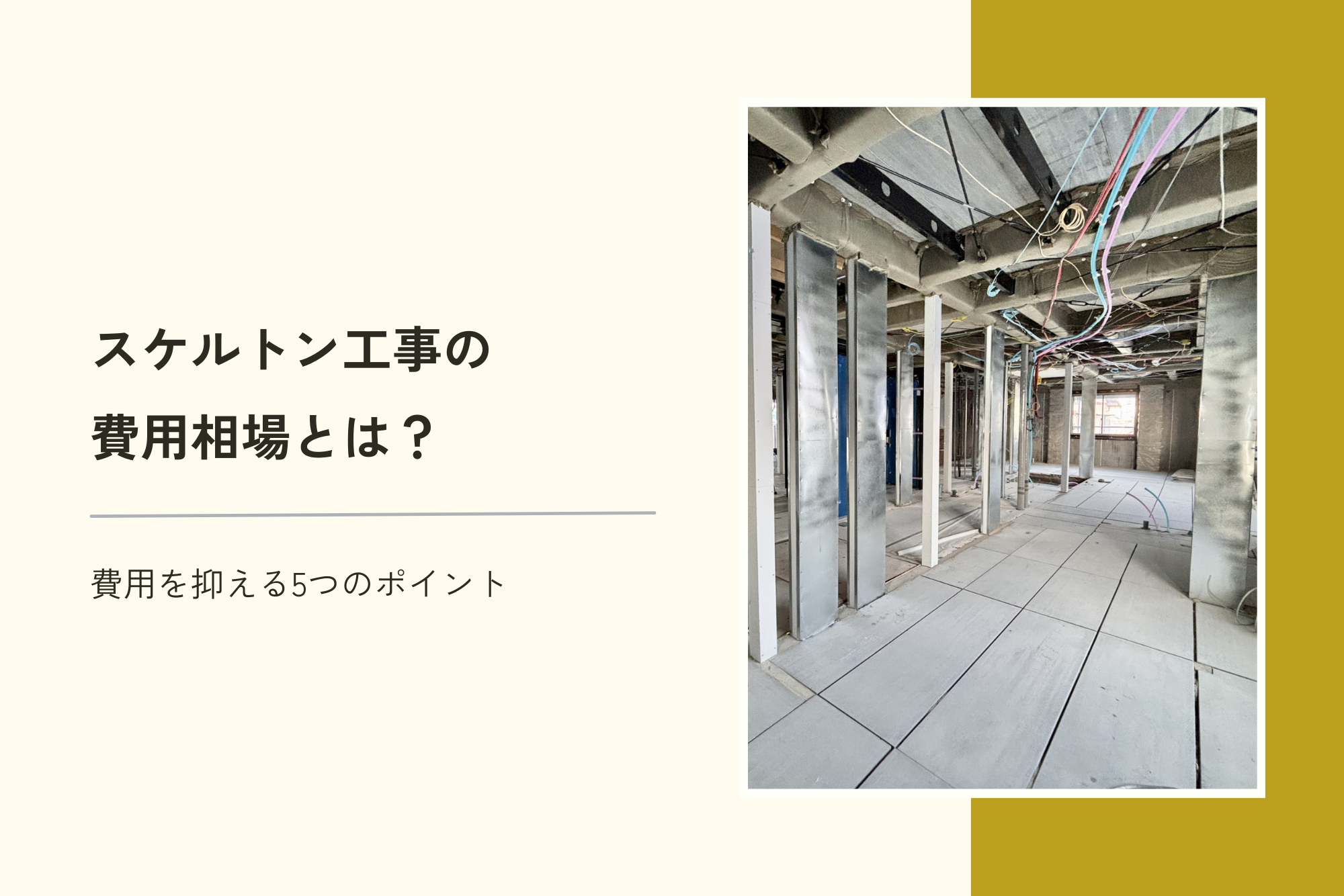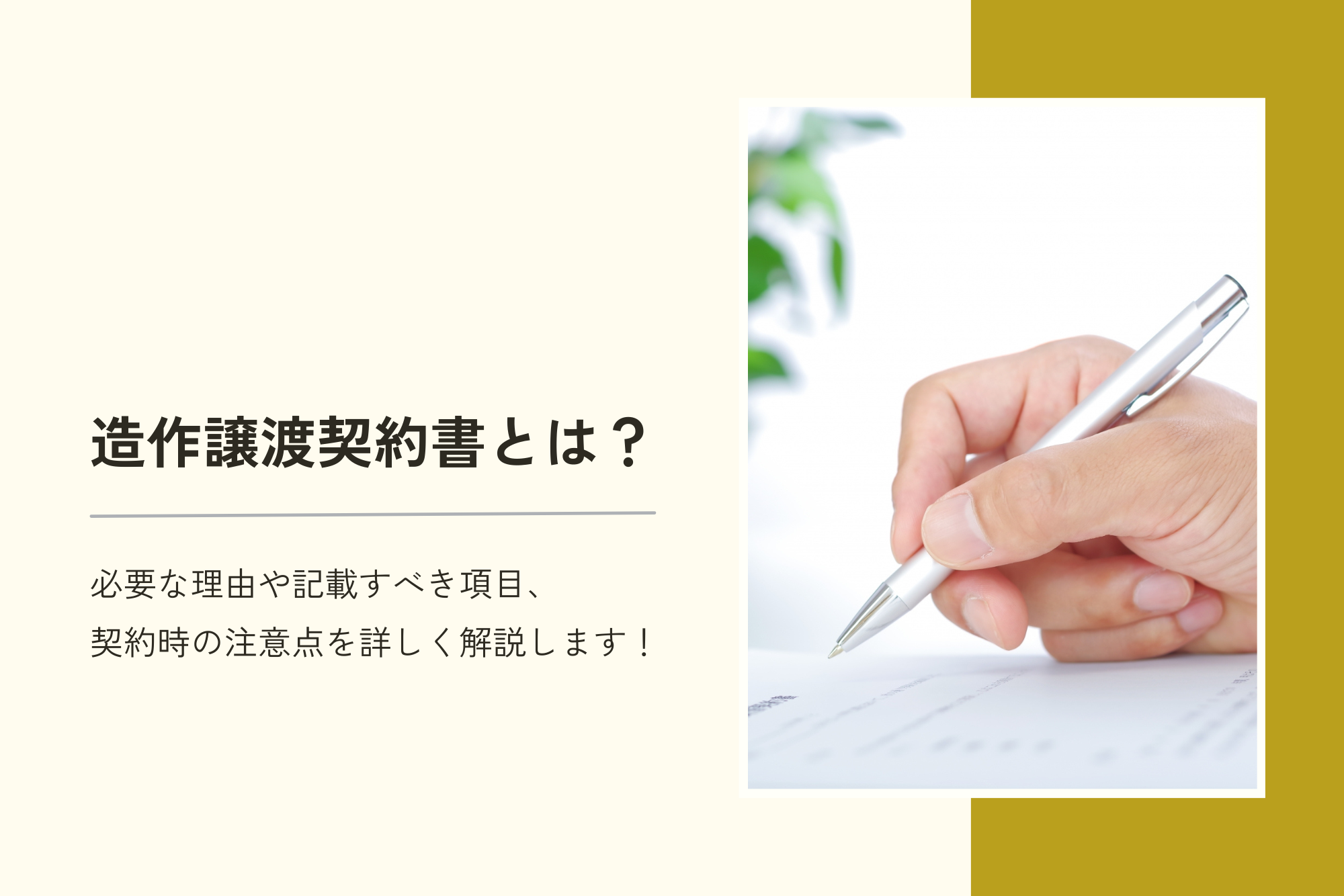
造作譲渡契約は、居抜き物件の前の借主が設置した設備や内装などを新たな入居者に引き渡す際に結ばれる契約です。この契約は、双方が合意した内容を正式に記録するもので、トラブルの防止には欠かせません。
本記事では、造作譲渡契約書の概要や必要な理由、記載すべき項目をご紹介します。また、契約時の注意点やよくある質問についても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

造作譲渡契約とは?

造作譲渡契約は、居抜き物件の前の借主が設置した設備や内装などを新たな入居者に引き渡す際に結ばれる契約です。この契約は、双方が合意した内容を正式に記録し、不必要なトラブルを防ぐ役割があります。
居抜き物件は、前の借主が使用していた厨房機器や食器、調理器具などの備品がそのまま残っているため、新規開業する際の初期投資を大幅に削減できるのがメリットです。
なお、造作譲渡のメリット・デメリットについては、こちらで記事でも詳しく解説しています。
関連記事:造作譲渡とは?メリット・デメリットや円滑に進める方法を詳しく解説します!

造作譲渡契約書が必要な理由

次は、造作譲渡契約書が必要な理由について解説します。
- 譲渡価格と譲渡項目を明確化するため
- 契約不適合責任を明確化するため
- 原状回復義務を明確にするため
- 固定資産として計上するため
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.譲渡価格と譲渡項目を明確化するため
造作譲渡契約書は、譲渡される設備や内装の詳細なリストと価格設定などを定める「譲渡項目書」を作成する際に重要な役割を果たします。譲渡項目書には、無償で譲渡される造作物、有償での譲渡が決まっている造作物、譲渡されない造作物が含まれており、所有権を明確にします。
また、契約書には支扡い期日や、引き渡し期日を遵守できなかった場合の契約解除条件やキャンセル料に関する条項も不可欠です。
2.契約不適合責任を明確化するため
ガス設備や水道設備などの重要な設備については、不具合が生じた場合の責任を明確にしておく必要があります。2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保(かしたんぽ)責任」から「契約不適合責任」へと変更され、売主の責任の範囲が明確化されました。
この改正により、引き渡された設備が使用できなかったり、性能が契約内容に適合していなかったりする場合、売主が対応する義務があります。
3.原状回復義務を明確にするため
一般の賃貸物件を契約する際、入居者は空の物件を借りて自ら設備や内装を整えます。この場合、退去時には原状回復が求められ、設備や内装をすべて撤去し、元の状態に戻す必要があります。
しかし、造作譲渡契約を結ぶと、原状回復義務の引き継ぎが可能です。そのため、造作譲渡契約書には、退去時に原状回復が誰に課されるかを明確に記載しなければなりません。
4.固定資産として計上するため
造作譲渡契約書は、譲渡された設備の価値を正確に記録し、新借主が減価償却の基準として使用するための証明書となります。居抜き物件から譲渡される空調設備などの固定資産は、耐用年数に基づいて減価償却が必要です。
また、固定資産の評価額以上に設備を売却した場合、前借主の所得となるため、計上にも関連します。

造作譲渡契約書に記載すべき項目

造作譲渡契約書に記載すべき重要な項目は、以下のとおりです。
- 譲渡する造作物の詳細リスト(造作物に対する金額、有償や無償の区別の記載)
- 支払い方法、支払い期日
- 引き渡しの期日
- 支払いが遅延した場合の対処方法
- 造作物についての契約不適合責任(売主の債務不履行責任)
- 退去時の原状回復の有無や、原状回復を求める範囲
- 契約解除条件
- 物件所有者・貸主からの承諾の有無
譲渡する造作物が多岐にわたる場合には、売主が契約書と別に譲渡項目書を作成するケースもあります。

造作譲渡契約時の注意点は3つ

次は、造作譲渡契約時の注意点について解説します。
- 物件の管理者から承諾を得る
- 不用品の処分負担を明確にする
- リース品の有無を確認する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.物件の管理者から承諾を得る
居抜きでの退去を希望する場合は、事前に管理者の承諾を得て、内容を造作譲渡契約書に明記しましょう。また、契約書で定められた原状回復の範囲についても、具体的な内容を把握し、どのぐらいの回復が必要か事前に話し合い、合意する必要があります。
この過程で疑問点があれば明確にし、契約書に反映させておきましょう。このような慎重な対応が後のトラブル防止につながります。
2.不用品の処分負担を明確にする
契約に含まれる造作物が借主にとって不必要である場合、処分にかかる費用の責任者を特定し、契約書に記載する必要があります。たとえば、譲渡リストに「給湯設備一式」と記されている場合、具体的な内訳が不明なため、後になって不用品と判明するケースもあります。
このような状況を防ぐため、契約時には具体的な品目リストと状態を詳細に確認し、不用品が含まれているかどうかを確認しましょう。不用品の処分に関しては、譲渡者と受け取り側で協議して、最終的な合意内容を契約書に明記すると、引き渡し後のトラブルを未然に防げます。
3.リース品の有無を確認する
リース会社と事前に連絡を取り、リース品の譲渡や引き継ぎが可能か確認しましょう。新しい借主にリース品を引き継ぐ場合、状態を詳しく確認し、契約書に「リース品」と明記します。
しかし、手続きを怠ると、リース会社がリース品を撤去しなければなりません。また、リース契約の内容や取引の種類によっては、税務上の処理が必要となる場合があります。
そのため、減価償却に必要な法定耐用年数や取得価額などの確認や契約書に詳細な記録が必要です。

造作譲渡契約書でよくある3つの質問

最後に、造作譲渡契約書でよくある質問について紹介します。
- 質問1.造作譲渡契約をスムーズに結ぶコツは?
- 質問2.造作譲渡のメリットは?
- 質問3.造作譲渡のデメリットは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.造作譲渡契約をスムーズに結ぶコツは?
造作譲渡契約をスムーズに結ぶコツは、以下のとおりです。
- 具体的な使用イメージを持つ
居抜き物件を見学する際は、事前にそのスペースで何をしたいか具体的にイメージし、必要なレイアウト変更やコストを考慮する
- 専門の不動産エージェントを利用する
造作譲渡契約の知識や実績のある不動産エージェントを活用すれば、適切な物件選びや契約をスムーズに進められる
- 契約内容を書面に残す
すべての合意事項を契約書に記載すれば、将来的なトラブルを防止できる
- 価格交渉する
提示された価格が適正でない場合、造作物の状態や追加負担を理由に価格交渉を試みる
質問2.造作譲渡のメリットは?
造作譲渡のメリットとしては、以下が挙げられます。
- 売却コストの削減
造作譲渡を利用すると、原状回復の工事費用を削減できる。内装や設備が良好な状態で譲渡する場合、追加の売却価値が見込める可能性もある
- 営業継続期間の延長
原状回復工事が省けるため、閉店までの期間を短縮せずに最後まで営業が可能となる。これにより、営業からの収益を保持しつつ、店舗の売却準備ができる
- 資源の有効活用
飲食店の場合、設備や内装に愛着があるオーナーにとって、それらが次のオーナーの手によって活かされるのは大きな満足感につながる
質問3.造作譲渡のデメリットは?
造作譲渡のデメリットは、以下が挙げられます。
- 貸主の承諾が必要
造作譲渡するには、貸主からの承諾が必須で、原状回復義務は新借主への引き継ぎが必要となる。さらに、貸主が物件を異なる用途で再貸しする意向がある場合、承諾が得られないリスクがある
- トラブルのリスク
造作譲渡の範囲や内容についての認識が両方の当事者間で異なる場合、契約後にトラブルが発生する可能性がある。このため、契約前には造作物のリストやその状態を明確にし、両方の当事者が合意に至る必要がある
- 隠れたコスト
譲渡される造作物の維持やアップグレードには追加の費用がかかる。受け取る側は、譲渡される設備の状態を詳細に検査し、必要な修理や更新にかかる費用を見積もる必要がある

まとめ

本記事では、造作譲渡契約書の概要や必要な理由、記載すべき項目、契約時の注意点をご紹介しました。
造作譲渡契約書は、前の借主と新しい借主との間で譲渡価格と譲渡項目や契約不適合責任の所在、原状回復義務を明確化するために必要になります。さらに、居抜き物件から譲渡される空調設備などの固定資産は、耐用年数に基づいて減価償却が必要なため、造作譲渡契約書が保証書の役割もあります。
また、居抜きでの退去を希望する場合は、事前に物件の管理者から承諾を得て、内容を造作譲渡契約書に明記しましょう。不用品の処分、リースの有無も確認しておく必要があります。