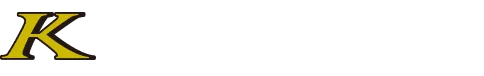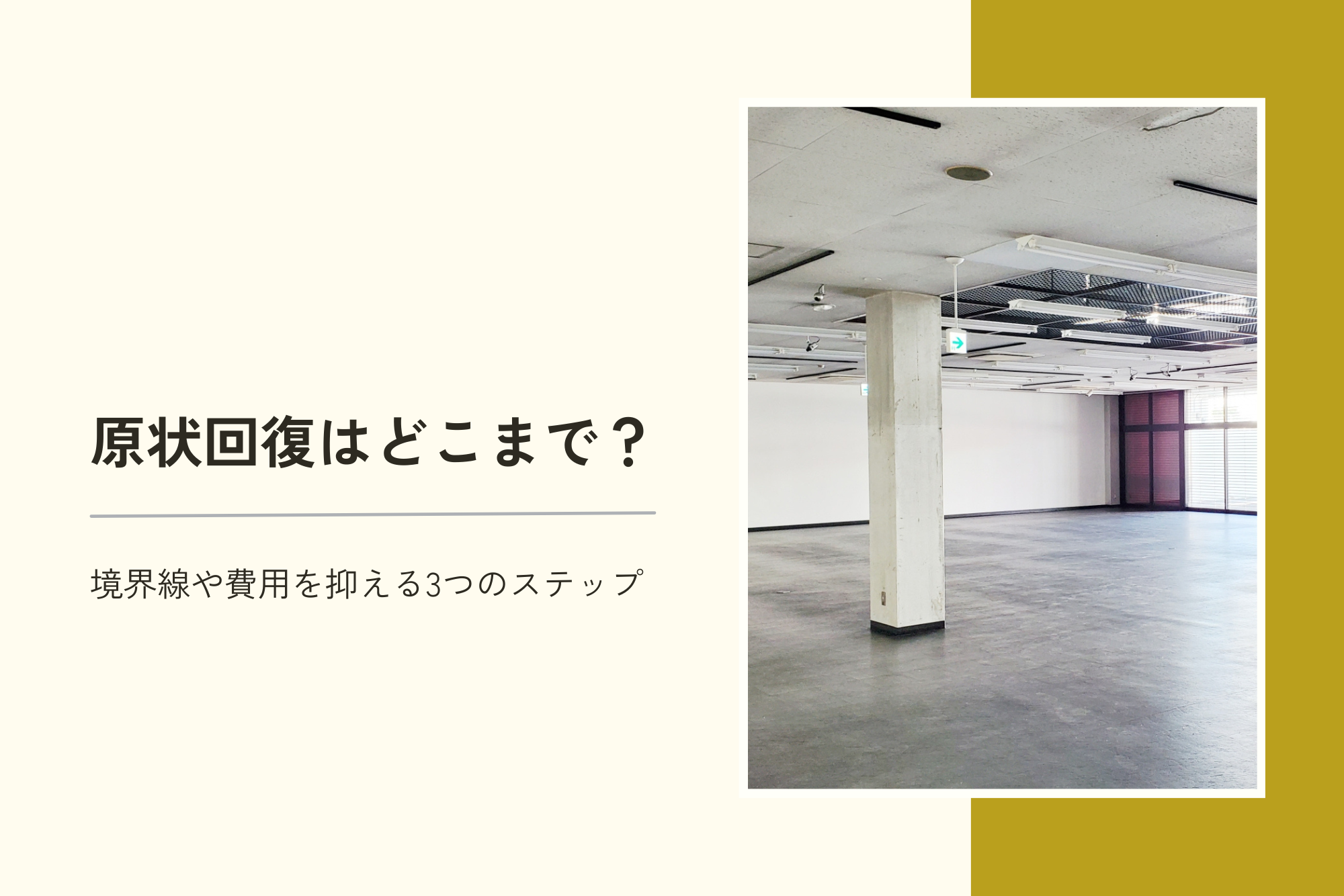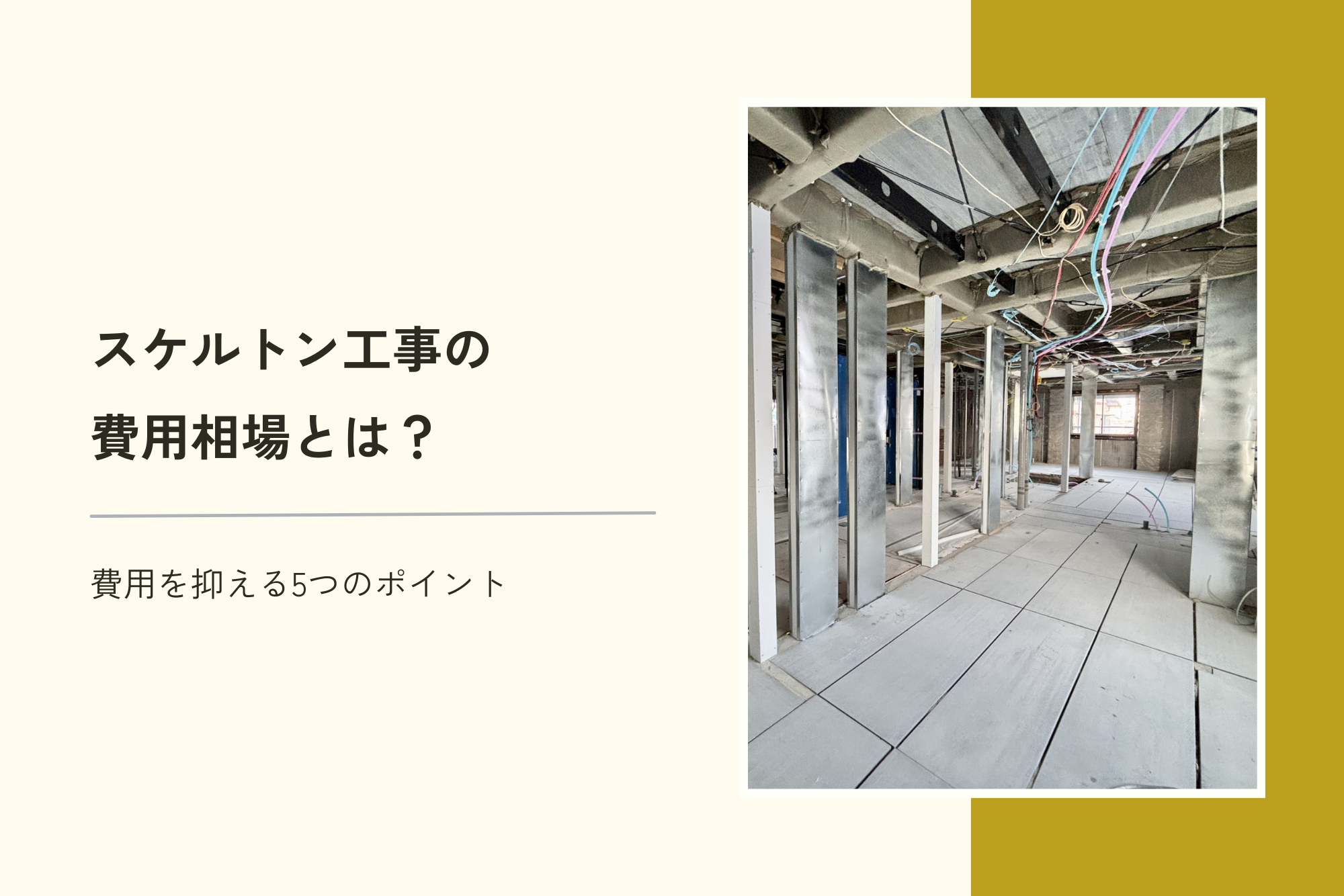内装の解体工事について「何からはじめていいのかわからない」「費用が心配」という方も多いのではないでしょうか。店舗やオフィスの移転、リフォームする際には、内装工事が不可欠です。
本記事では、内装解体の概要や解体工事のステップ、費用相場をご紹介します。また、安く抑えるためのポイントやよくある質問も解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

内装解体とは?

内装の解体は、建物の内装部分のみを解体する工事で、建物自体の構造は残します。主に、テナント物件を退去する際の原状回復工事として実施されるのが一般的です。
また、飲食店やオフィスなどで設置した内装設備(壁、床、棚、カウンター、厨房設備など)を解体し、必要に応じて補修して、物件を元の状態に戻します。また、アパートやマンションのリフォームやリノベーションの際にも内装解体が必要です。
スケルトン工事
スケルトン工事とは、建物の構造部分だけを残し、内装や設備をすべて取り除く作業です。具体的には、床や天井、壁、電気配線、水道配管、エアコンなどを完全に撤去します。
撤去後、建物はコンクリート打ちっぱなしの状態となり、文字通りのスケルトン状態になります。この工事は、テナントやマンションの改修やリノベーションの際に実施されるケースが多いです。
また、スケルトン工事には、内装のみを撤去する工事と、建物の骨組み以外をすべて撤去する工事の2種類があります。
なお、スケルトン解体については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:【プロが教える】スケルトン解体とは?メリットや費用相場、安く抑えるコツを徹底解説!
原状回復
原状回復工事とは、物件を退去する際に、入居前の状態に戻すための工事です。たとえば、天井や壁、床を新設した場合、退去時にはそれらを解体して元の状態に戻す必要があります。
また、入居中に内装を傷つけたり壊したりした場合も、解体してから元のきれいな状態に戻します。さらに、スケルトン状態で借りた物件の場合、退去時もスケルトン状態に戻さなければなりません。
一方で、設備や柱がある状態で借りた場合、それらを残してほかの部分を解体します。原状回復工事の内容はオーナーや管理会社が決めるため、入居者はその指示に従って工事を実施します。

内装解体が行われる主な建物

内装解体工事はさまざまな建物で実施されますが、主な建物としては以下が挙げられます。
- 飲食店(居酒屋・レストランなど)
- リラクゼーションサロン
- ヘアサロン
- テナントビル
- 事務所・オフィス
- 小売店・アパレルショップ
- 居住用賃貸物件
これらの運営には、撤退や移転がつきもののため、テナントや店舗を返却する際には、必ず契約書の条件を確認し、スケルトン工事と原状回復工事のどちらで返却しなければならないか理解しておいてください。

内装解体工事のステップは7つ
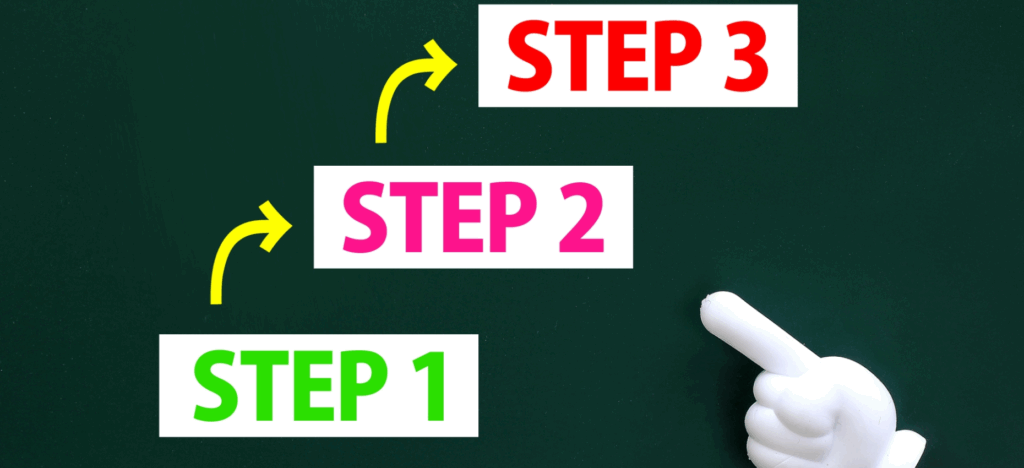
次は、内装解体工事のステップについて解説します。それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
ステップ1.解体内容や契約の打ち合わせ
内装解体工事を進める際には、借主と貸主の綿密な打ち合わせが不可欠です。契約内容を明確にし、解体の詳細や期間、費用、イレギュラーな事態への対応方法まで、双方が納得する形で合意することが大切です。
また、建物の所有者である賃貸人と建物の一部を借りている賃借人の同意が必要であり、これを怠るとトラブルの原因になる可能性があります。スケルトン工事や原状回復工事のような大規模な工事では、業者選びからオーナーが関与する場合もあります。
ステップ2.解体業者の選定
解体業者の選定には、信頼性や実績、費用の透明性、対応の迅速さなどを考慮することが大切です。複数の見積もりを比較し、詳細な説明を受けると、適正な価格やサービス内容を把握できます。
さらに、解体業者が過去に手がけた工事事例を確認しましょう。また、貸主が業者選定に関わる場合もあるため、打ち合わせの段階で業者選定についても協議しておくとスムーズです。
ステップ3.解体業者による現地調査
口頭や書面で内装の状況を伝えても、認識のズレが生じる可能性があるため、現地調査は欠かせません。調査では施主も立ち会い、広さや内装の状態を詳細に確認しましょう。
また、追加工事や余分な費用の発生を防ぐためにも、実際の現場を見て状況を把握することが大切です。近隣の状況を調べ、重機の搬入ルートや作業の影響を最小限に抑えるための対策も考えましょう。
さらに、同じ建物内にほかのテナントが入っている場合、営業時間を避けたスケジュール調整や隣接する店舗への配慮が求められます。
ステップ4.近隣への挨拶
解体工事をはじめる前には、同じ建物に入っている店舗や近隣住民への挨拶回りが欠かせません。工事に伴う騒音や振動について、事前に理解を得るのがトラブルを未然に防ぐポイントです。
店舗が入居している建物では、近隣の営業に影響を与える可能性があるため、工事の概要や期間を丁寧に説明しましょう。また、オーナーが事前に連絡している場合もありますが、直接挨拶する方が信頼関係を築けます。
ステップ5.残置物・残留物の処分
店舗やオフィスには、什器やテーブル・椅子、オフィス家具など多くの物品が設置されています。これらを解体業者に一緒に撤去してもらうと「残置物撤去費」が高額になる可能性があります。
このため、内装解体が始まる前に、自身で処分できるものを確認し、可能であれば事前に撤去しておくことがおすすめです。また、不用品のなかには買取が可能なものもあるため、思いがけず利益を得られる場合もあります。
しかし、予定外の作業が発生すると、工期や費用に影響をおよぼしかねません。このため、内装解体をスムーズに進めるためには、不用品について一度見直ししてから、適切な処理をするようにしましょう。
なお、残置物については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:賃貸物件における「残置物」とは?トラブルにつながりやすいケースや防止策を徹底解説!
ステップ6.ライフラインの契約停止
内装解体工事の開始前に、電気やガス、水道、インターネットなどのライフラインの停止やケーブルの撤去手続きが必要です。工事は建物内部だけでなく、設備部分の撤去も含まれるためです。
ライフラインの停止手続きは、工事が開始する1週間前までには完了させましょう。しかし、以下のようなケースではライフラインを停止しないほうがよい場合もあります。
- 建物全体でオーナーがライフラインを契約している場合
- 解体後に新たなテナントがすぐに利用する予定がある場合
- 解体工事中に業者がライフラインを使用する必要がある場合
これらの例外があるため、関係各所と連携をしっかり取るようにしてください。事前の打ち合わせを通じて、ライフラインの停止手続きも確実に進めるようにしましょう。
ステップ7.内装解体工事
すべての準備が整ったら、内装解体工事が始まります。以下は工事のステップです。
- 足場や養生の設置
埃や粉塵が周囲に飛散しないよう、足場や養生シートを設置する。外周だけでなく、エレベーターや廊下などの共用部分も養生する
- 内装の解体と撤去
照明器具や設備を撤去した後、壁紙やガラス、ドア、天井などの内装材を解体・撤去する。作業中は埃や粉塵が発生しやすいため、マスクやゴーグルの装着が必要になる
- 床材の撤去
素材によって接着剤が異なるため、適切な方法で取り除く必要がある。コンクリート製の床の場合、ハンマーで解体する「斫り(はつり)」作業を実施する
- 産業廃棄物の処理
「廃棄物の処理および清掃に関する法律」にもとづき、産業廃棄物を適切に処理する。不法投棄を防ぐため、業者には廃棄物処理の流れや業者名が記載された書類「マニフェスト」を提出してもらう必要がある
- 室内清掃やリフォーム
解体工事と廃棄物処理が完了したら、細かなゴミや塵を掃除する。必要に応じてリフォームを実施して、次の利用者に気持ちよく使用してもらえる状態にする

内装解体工事の費用相場

内装解体の費用は、物件の面積や立地、階数、エレベーターの有無などによって異なります。建物やテナントの種類ごとの坪単価の相場は、以下のとおりです。
| 建物やテナントの種類 | 坪単価(相場) |
| マンション | 15,000~35,000円 |
| オフィス、事務所 | 13,000~37,000円 |
| 飲食店 | 15,000~40,000円 |
| 美容室 | 15,000~42,000円 |
| 一般的な店舗 | 13,000~42,000円 |
設備や備品、間仕切りが多い業種では、内装解体の坪単価が高くなる傾向があります。

内装解体工事を安く抑えるためのポイントは3つ

次は、内装解体工事を安く抑えるためのポイントについて解説します。
- 残置物は自分で処分する
- 複数の業者から見積もりを取得する
- 解体業者に直接依頼する
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
1.残置物は自分で処分する
解体業者に不用品を処分してもらうと、産業廃棄物として処理されるため、コストが高くなる場合があります。また、残置物があると工事の開始が遅れるだけでなく、運搬や処分にかかる費用も追加で発生する可能性が高いです。
見積もりの前に掃除をしておくとよいですが、店舗の場合は難しい場合も少なくありません。見積もりの際に自分で片づける範囲を伝えて、どれくらい費用を削減できるか確認するのもおすすめです。
2.複数の業者から見積もりを取得する
業者ごとに工事のやり方や範囲が異なるため、金額だけで決めるのは避けましょう。それぞれの業者の見積もりを比較すれば、金額の適正さや工事内容の確認ができます。
また、不動産業者が退去時の内装解体業者を指定している場合でも、ほかの業者からも見積もりを取っておくと、不要な工事のチェックや交渉によるコストダウンが可能です。見積もりを取る際には、工事の期間や工法、打ち合わせ時の対応なども考慮して、信頼できる業者を選びましょう。
3.解体業者に直接依頼する
不動産業者が解体業者を紹介する場合、中間マージンが発生し、全体の費用が割高になります。しかし、業者へ直接依頼する場合は、中間マージンが削減でき、コストを抑えられます。
また、直接依頼する場合、自分で複数の解体業者に見積もりを依頼し、比較検討することが大切です。ただし、解体業者とのやり取りに時間を割けない場合や、次の店舗設営に集中したい場合は、不動産業者が紹介する業者を利用する方法もあります。
この場合、一括で手続きを進められるため手間が省けますが、見積もりの詳細をよく確認して、不要なコストが含まれていないかチェックすることが大切です。

内装解体でよくある3つの質問

最後に、内装解体でよくある質問について紹介します。
- 質問1.内装解体にかかる日数はどのくらい?
- 質問2.内装解体工事の注意点は?
- 質問3.内装解体工事で足場が必要な条件とは?
それぞれの詳しい内容についてみていきましょう。
質問1.内装解体にかかる日数はどのくらい?
内装解体工事の所要時間は、工事面積に大きく依存します。たとえば、10坪前後の工事の場合、一般的には2~3日で完了しますが、30坪以上の場合には1週間程度を見込む必要があります。
さらに、より広い建物の解体作業の場合、20日〜1か月程度を要するケースが多いため、十分な余裕を持ったスケジュールを設定しなければなりません。このため、計画を立てる際は、工事規模に応じた時間を確保し、予期せぬ遅延にも対応できるよう心がけましょう。
質問2.内装解体工事の注意点は?
内装解体工事の注意点は、以下があげられます。
- スケジュール管理
テナント物件の場合、次の入居者との調整があり、返却期限が明確に定められているため、工期の遅れは許されない。そのため、余裕を持ったスケジューリングが求められる
- 不用品処分の段取り
店舗や会社が営業を続けるなかで解体工事を進める場合、不用品の処分や撤去作業の段取りを事前に組んでおけば、スムーズに工事へ移行できる
- 準備段階での詳細の把握
それぞれの工事内容を事前に把握し、適切な計画が立てられれば、スムーズな内装解体が実現できる
質問3.内装解体工事で足場が必要な条件とは?
内装解体工事における足場の設置が必要な条件としては、以下のとおりです。
- 床から手が届かない天井の解体工事が広範囲にわたる場合
- 吹き抜け天井の解体工事
また、足場の設置には専門知識が必要であり、適切な設置が実施されないと作業員の安全が確保できません。さらに、内装解体工事の費用に加えて、足場の設置や撤去にかかる費用が必要となります。
このため、事前に専門業者と詳細な打ち合わせを実施して、見積もりを確認しましょう。

まとめ

本記事では、内装解体についてや解体工事のステップ、費用相場、安く抑えるためのポイントをご紹介しました。
内装解体とは、テナントや飲食店など建物の内部を解体して、元の状態に戻す作業です。内装解体には、建物の骨組みだけを残して、すべてを撤去する「スケルトン工事」とテナントなどの賃貸物件を契約時の状態に戻す作業の「原状回復工事」があります。
費用相場は、工事の規模や内容によって異なるため、複数の業者から相見積もりを取って比較検討しましょう。さらに、解体業者が残置物を処分する場合は、コストが高くなる傾向にあるため、可能な範囲で自ら処分するのがおすすめです。