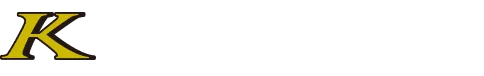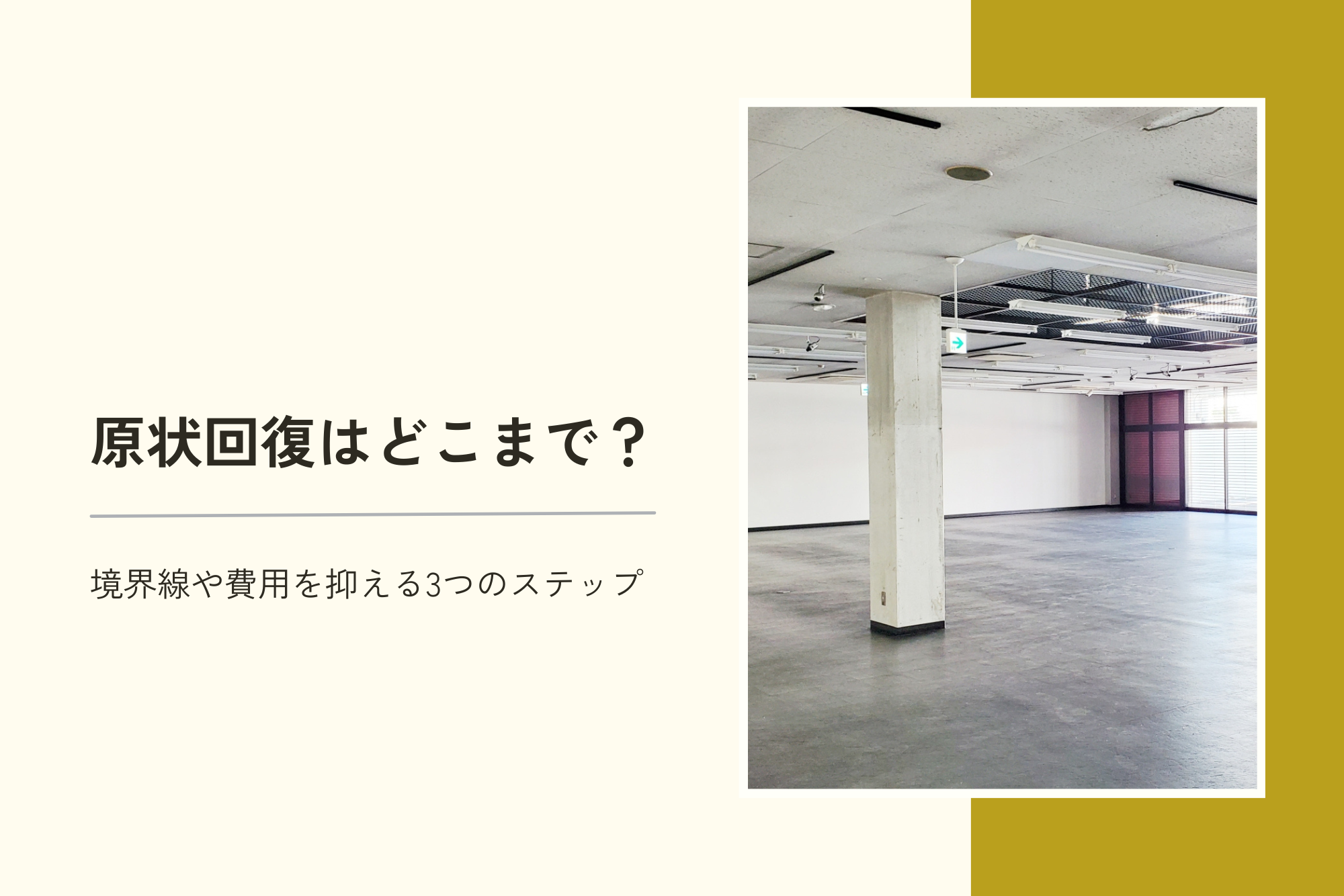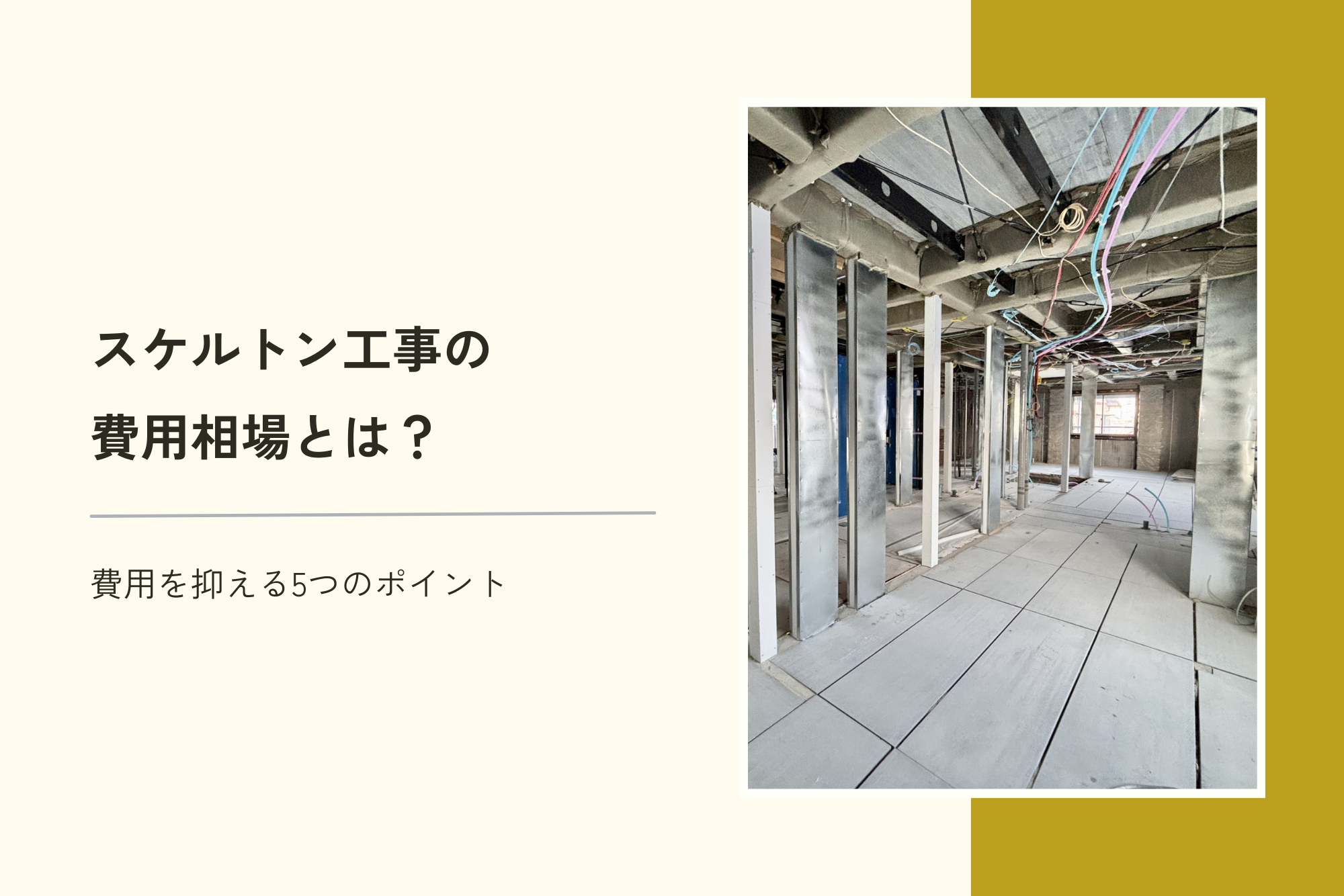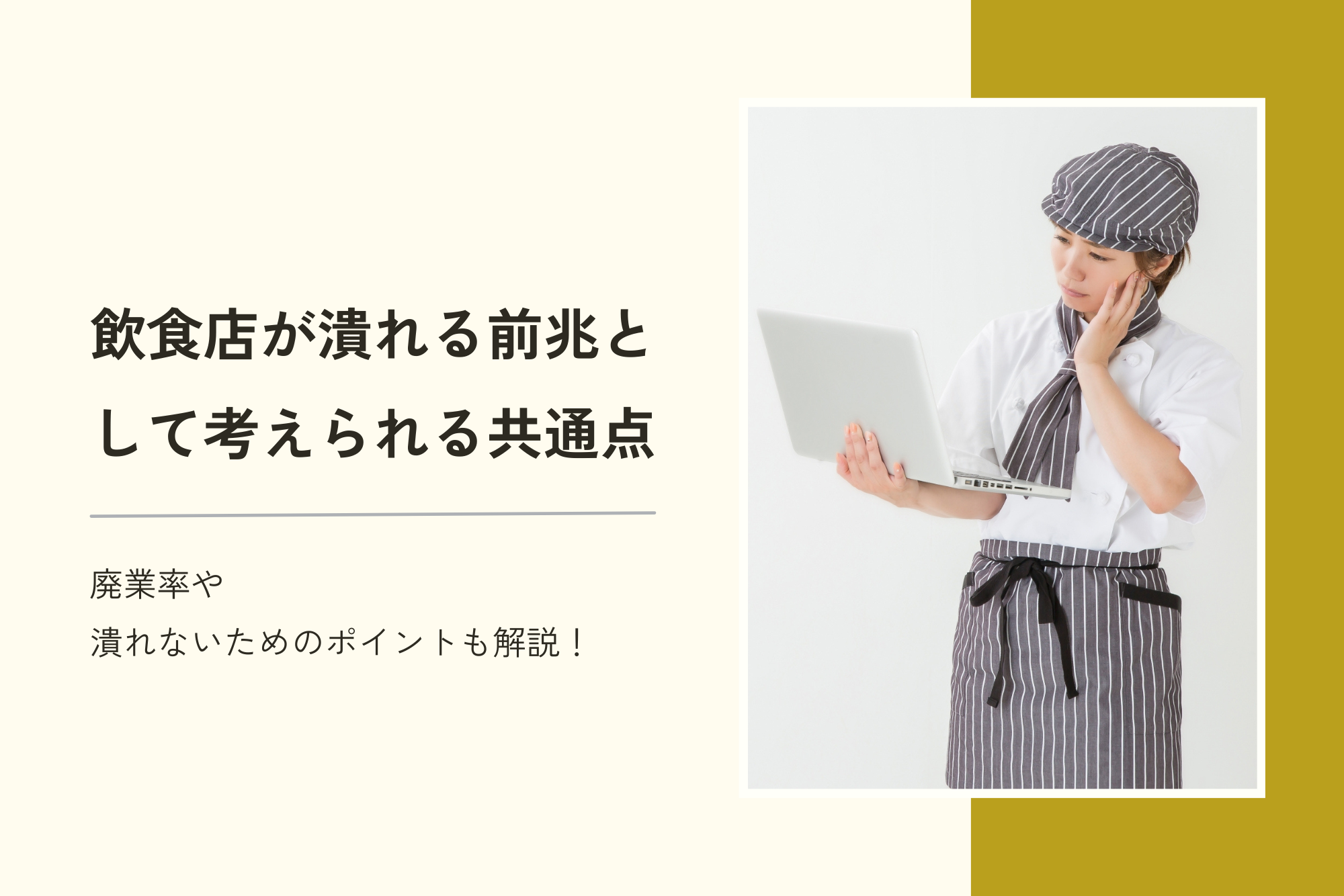
飲食店を経営されている方で、厳しい経営状況に直面している方もおられるのではないでしょうか。飲食店を潰さないためには、緻密な資金計画や効果的な集客が欠かせません。
本記事では、飲食店の廃業率や飲食店が潰れる前兆として考えられる共通点について解説します。また、飲食店が潰れないためのポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

飲食店の廃業率

中小企業庁の「2022年版 小規模企業白書」によると、飲食店は全業種中で最も高い廃業率5.6%を記録しています。この業界では、1年以内に約30%、10年以内に約90%の事業が廃業に至るとされており、人手不足や世界情勢の変化など、多くの課題に直面しています。
また、飲食業の開業率は17.0%と非常に高く、業界内で入れ替わりが激しいのが実情です。これらの課題と高い廃業率は、経営者が日々の営業活動において注意深く舵取りする必要があることを示しており、顧客数の減少やそのほかの経営指標に対する警戒の必要性を明らかにしています。
なお、飲食店の廃業率については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
関連記事:飲食店の廃業率が高い8つの理由|潰れない店の特徴や回避策、よくある質問まで徹底解説! – 金山株式会社

飲食店が潰れる前兆として考えられる10の共通点

次に、飲食店が潰れる前兆として考えられる共通点を紹介します。それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.料理の提供に時間がかかる
料理の提供時間が遅いと、顧客の満足度が著しく低下する可能性があります。また、提供時間の遅れは、店舗の回転率を悪化させ、売上の低下にもつながります。
そのため、スムーズに料理が提供できるように心がけ、顧客のお店に対する期待値を守るようにしましょう。顧客の待ち時間が以前に比べて長くなっていないか、現場が人手不足になっていないかなど定期的な確認も不可欠です。
2.お店のコンセプトが曖昧である
飲食店は立地によって潜在的な客層が限られるため、リピーターの確保が継続的な経営には欠かせません。顧客に「また来たい」と思ってもらうためには、その店ならではの個性や看板メニューが必要です。
たとえば、「メニューは豊富だが、味や価格は平均的」というお店は、同じくらいの価格でより多くのメニューを提供するチェーン店に敗れるケースが多いです。つまり、飲食店の経営を成功させるには、明確なコンセプトのもとで、商圏や顧客ニーズに合わせた戦略が求められます。
3.Webサービスを運用できていない
SNSやホームページ、グルメサイトなどのWebサービスは、現代のネットワーク社会において欠かせない集客手段です。これらのツールは、飲食店を検索する顧客が頻繁に利用しており、定休日や営業時間、メニューなどをチェックする貴重な情報源です。
そのため、Webサービスの更新をルーティン化し、最新の情報を発信し続けることが、新規顧客の獲得につながります。
4.テナントの入れ替わりが激しい
テナントの入れ替わりが激しい物件には注意が必要です。このような物件は、人目に付きやすい一等地であるケースがほとんどですが、これらの物件は総じて家賃が高く、狭小物件である場合が多いです。
そのため、利益を出すには回転率を高めるか、利益が出やすいドリンクやお酒を提供するなどの工夫が欠かせません。
飲食店を開業する際は、「立地」だけでなく、客単価や席数、回転率を慎重に見積もり、黒字経営が可能かどうか判断することが大切です。安易に一等地での契約に走ると、赤字経営に陥るリスクが高まります。
5.不衛生で清掃が行き届いていない
不衛生で清掃が行き届いていない飲食店では、たとえ質の高い料理を提供していても低評価を受ける可能性が高いです。とくに、お店の出入り口やトイレは顧客に与える印象が大きいため、入念なチェックが欠かせません。
また、トレーや部屋の隅など、細かな部分の清掃も重要です。年季が入った店舗でも、徹底的な清掃がされていれば清潔感を保つことが可能ですが、掃除の手抜きが見透かされると、顧客は二度と来店しません。
6.割引やキャンペーンの頻度が多すぎる
料理の割引やキャンペーンは、お得においしい料理を楽しむチャンスとして喜ばれるため、効果的な宣伝手法です。しかし、これらのキャンペーンの「頻度」には注意が必要です。
頻繁にキャンペーンを行うと、「すぐに割引になりそうだから、次の機会に行けばいい」と感じるようになります。これは、特別感が薄れるだけでなく、通常価格で来店した場合に割高感を与えてしまう要因です。
7.看板メニューの注文が少ない
飲食店が直面する重大な問題の1つは、「看板メニューの注文数の減少」です。看板メニューの注文数が減少している場合、これは飲食店が潰れる前兆として見落としてはいけないシグナルです。
注文数が減っている理由としては、顧客に飽きられている、または味のクオリティが下がっているなどの原因が考えられます。さらに、流行に左右されるメニューの場合は、市場の変化についていけていない可能性も考えられます。
このような問題に対応するためには、看板メニューのマンネリ化を防ぐ対策や新メニューの開発などの工夫が欠かせません。
8.来店客数が明らかに減っている
顧客の減少は売上の低下に直結し、お店が潰れるリスクを高めます。とくに、顧客が1人も来店しない日が続き始めると、流行っていないお店というネガティブな印象を与えてしまいます。
顧客が来店しない理由として考えられるのは、接客態度の悪さ、立地の不便さ、メニューの質の低さなどです。これらの問題をしっかり分析し、効果的な解決策を検討するようにしてください。
9.スタッフの離職が多い
スタッフの退職率が増加すると、サービスの質に大きく影響します。とくに、長年在籍したスタッフが辞めてしまうと、安定したサービスが提供できなくなり、お店全体のサービス低下につながりかねません。
もし、退職するスタッフが多い場合は、お店の運営に対する不満などが考えられます。定期的に、スタッフとお店や勤務方法などについて、話し合う機会を設けるようにしましょう。
10.顧客の固定化が起きている
顧客の固定化が著しい場合も、注意が必要です。常連の顧客も大切な存在ですが、新規の顧客が増加しない場合、お店の成長が望めない状況に陥っている可能性があります。
このような状況を感じた場合は、看板やポップ、のぼりなどを活用し、商圏で活動している人々へのPR活動を実施してください。開店当時の初心に帰り、新規の顧客を引き付けるためのアピールを継続しましょう。

飲食店が潰れないためのポイントは5つ

次に、飲食店が潰れないためのポイントについて解説します。
- 緻密な資金計画を立てる
- ニーズに沿ったコンセプトに転換する
- スタッフを育成する
- ホームページやSNSを活用する
- 他店との差別化を図る
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.緻密な資金計画を立てる
飲食店が早期に潰れる場合は、開業時の準備不足が影響しているケースが多いです。開業にあたり、投資計画では何にいくらお金をかけるのか、売上計画ではいつまでにいくら売れるのかを明確にしましょう。
また、損益計画でいつまでにどれくらい儲かるか、返済計画で借りたお金をどのように返すかの検討も大切です。さらに、経営が軌道に乗るまでの運転資金も考慮し、準備資金も余裕を持って準備するようにしましょう。
2.ニーズに沿ったコンセプトに転換する
店舗のコンセプトが問題を抱えていると、集客や利益の向上が難しくなるため、ターゲット層をまず明確に定めることが大切です。メインのターゲットがはっきりすれば、店舗のコンセプトも打ち出しやすくなり、どのようなメニューを揃えるべきか、どのように集客するかが見えてきます。
たとえば、ファミリー層をターゲットにする場合は、「子どもとゆっくりくつろぎながら食事を楽しめる空間」をコンセプトに考えることができます。座席をパーティションで半個室に区切ったり、ゆったりとくつろげる大型ソファを設置するなど、ターゲットのニーズに合わせた店舗設計を心がけましょう。
3.スタッフを育成する
飲食店経営では、立地や料理の味だけでなく人材育成や接客態度も重視することが大切です。近年は人材育成で苦労する飲食店も多く、質の高い接客を提供できる人材の育成が欠かせません。
たとえば、お金を触った後に食器を触らないような衛生管理も顧客に評価されるポイントです。また、味がよくても接客態度が悪いと再訪したいと感じる人は少ないため、接客に問題がないか定期的に見直すようにしましょう。
4.ホームページやSNSを活用する
ホームページやSNSを利用した情報発信は多くの人々にリーチできる手段です。とくに、SNSでの写真を使った投稿は全国各地からの集客効果が見込めます。
ただし、利用するSNSの種類はターゲットの年代や宣伝方法によって異なるため、自分のお店のコンセプトに合わせた適切なSNSプラットフォームでの宣伝を心がけましょう。
5.他店との差別化を図る
競合他社との差別化に成功している飲食店は潰れにくいです。飲食店は全国各地に多数存在しており、似たコンセプトの店舗も少なくありません
メニューの工夫や料理の味付け、SNSの活用、他店にないサービスなど、多角的なアプローチで差別化を検討しましょう。また、顧客が求める要素を提供できれば、より多くの顧客獲得が期待できます。

飲食店の潰れる前兆でよくある3つの質問

最後に、飲食店の潰れる前兆でよくある質問を紹介します。
- 質問1.飲食店が潰れる原因となる「外的要因」とは?
- 質問2.お店が潰れる前兆に心当たりがある場合はどうするべき?
- 質問3.飲食店経営者の頭を悩ませている課題とは?
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.飲食店が潰れる原因となる「外的要因」とは?
飲食店が潰れる前兆には「外的要因」が関与している場合もあります。飲食店が潰れる主な外的要因としては、食材の高騰が挙げられます。
食材の仕入れ値の上昇は、原価率を高め、経営を圧迫する要因の1つです。食材の価格は時期によって変動するため、価格の変動に応じてメニューの変更や価格の見直しが欠かせません。
また、飲食店の周辺環境の変化が影響をおよぼすこともあります。たとえば、近隣に大型商業施設が新設されたことにより、商店街が寂れてしまうなど、環境面のマイナスの変化が経営に大きな打撃を与えるケースもあります。
質問2.お店が潰れる前兆に心当たりがある場合はどうするべき?
お店が潰れる前兆に心当たりがある場合は、お店を継続するか閉店するかの検討が必要です。継続する場合は、現在の業態を維持したまま経営するほかに、お店の業態を変更する方法も効果的です。
業態を変更する場合や閉店する場合は、店舗を売却するための手続きやコストがかかります。このような場合は、店舗の居抜き売却により、余計なコストをかけずに次のステップに進みやすくなります。
質問3.飲食店経営者の頭を悩ませている課題とは?
厚生労働省の「飲食店営業(一般食堂)の実態と経営改善の方策」によれば、多くの飲食店経営者が直面している収益悪化の主な原因は「原材料費の上昇」です。
ついで、「客数の減少」が約50%、「水道・光熱費の上昇」が約45%、「施設・設備の老朽化」が約37%、「人手不足・求人難」が約33%と続いています。
個人経営の飲食店では、「客数の減少」が約63%と最も深刻な問題とされており、「原材料費の上昇」の約54%を上回っています。これらのデータから、個人事業主にとっては集客が大きな課題となっていることが明らかです。
参考:飲食店営業(一般食堂) の実態と経営改善の方策|厚生労働省

まとめ

本記事では、飲食店の廃業率や飲食店が潰れる前兆として考えられる共通点、飲食店が潰れないためのポイントについて解説しました。
飲食店は、さまざまな業種のなかで最も高い廃業率を記録しています。この業界では、1年以内に約30%、10年以内に約90%の事業が廃業に至るとされているため、入れ替わりの激しい厳しい業界であることは間違いありません。
しかし、開業当時から緻密な資金計画を立てている飲食店や、ホームページやSNSでの情報発信に成功しているお店は、差別化に成功し、安定した店舗経営を実現しています。
ぜひ、この記事で紹介した飲食店が潰れないためのポイントを参考にして、お店の経営を黒字回復させてください。