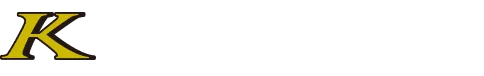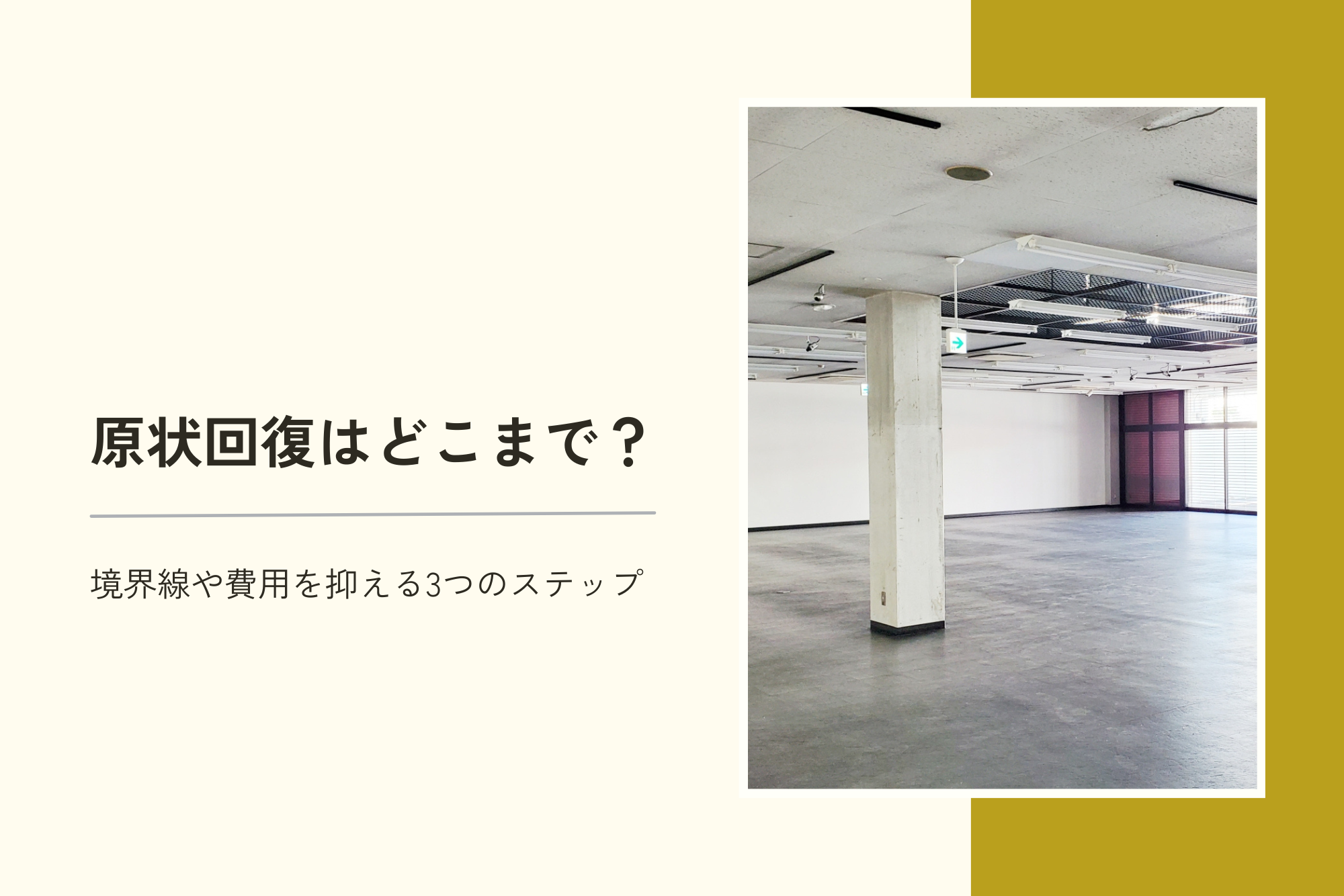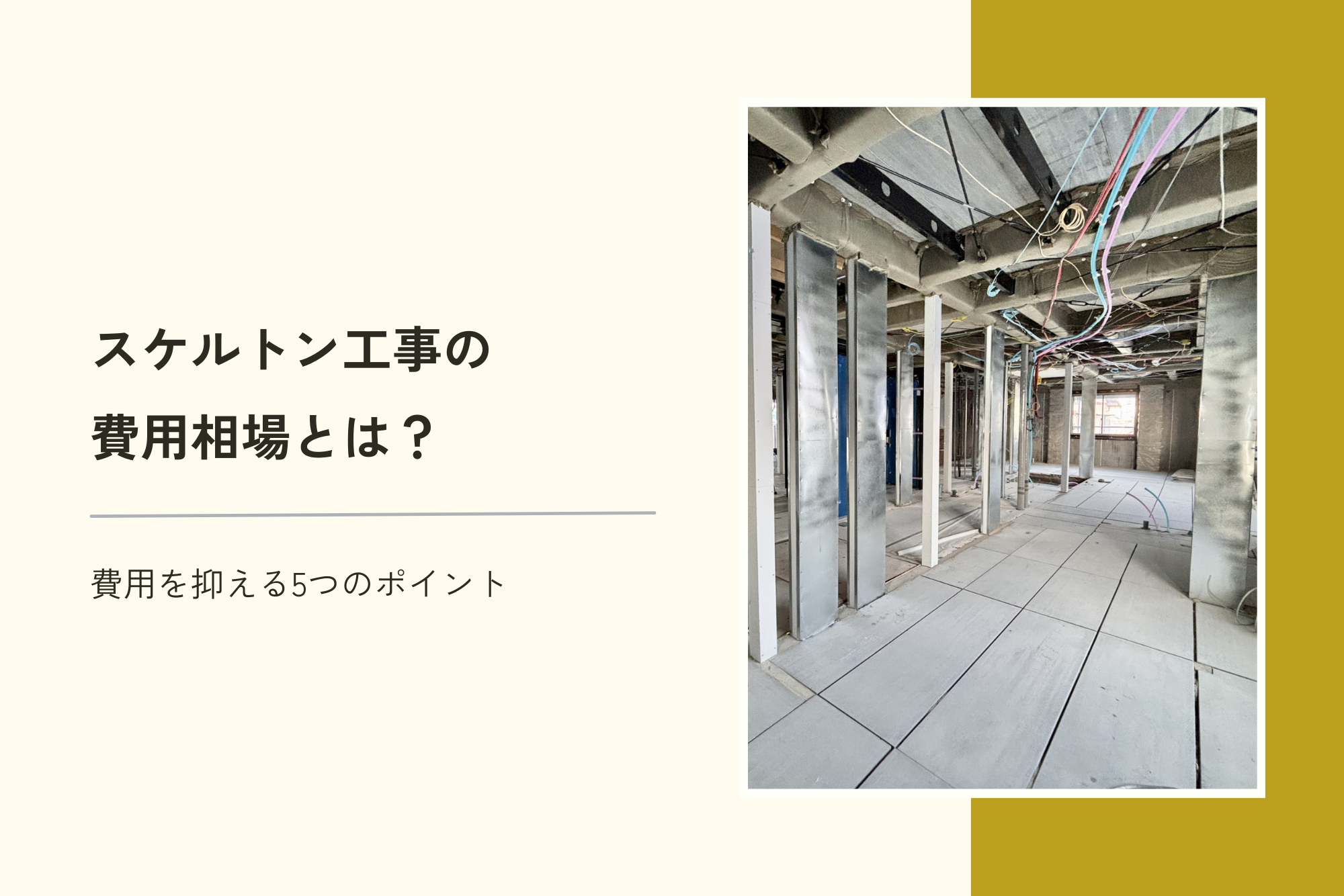店舗や事業所の引き継ぎにおいて、造作譲渡は重要な選択肢の1つですが、具体的にどのような制度なのかわからないという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、造作譲渡の概要や平均相場、メリット・デメリットについて解説します。また、造作譲渡を円滑に進めるポイントについても解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

造作譲渡とは?

造作譲渡とは、不動産の賃貸契約において、テナントが建物内に設置した内装や設備(造作)を、新しいテナントや家主に譲渡することを指します。これにより、テナントは退去時に造作の撤去費用を削減でき、新しいテナントは初期投資を抑えられます。
また、造作譲渡には、譲渡条件や価格の交渉が必要であり、双方の合意が不可欠です。さらに、契約書にて詳細な取り決めを交わす必要もあります。このような譲渡は、商業施設やオフィスビルでよくみられます。

造作譲渡に該当するものとしないもの

造作譲渡に該当するものは、テナントが設置した内装や設備です。具体的には、カウンターや棚、エアコン、照明器具、厨房設備、間仕切り、床材などが含まれます。これらは一般的に、賃貸借契約終了時に次のテナントに譲渡されるケースが多いです。
一方で、造作譲渡に該当しないものは、不動産の所有者が設置した設備や建物の構造部分です。具体的には、壁や天井、配管、電気設備、給排水設備、建物の基礎部分などが含まれます。これらは不動産の一部とみなされ、テナントが自由に取り外しや変更を行うことはできません。
また、テナントが設置したものであっても、一時的な装飾や持ち運び可能な家具も造作譲渡の対象外になります。

造作譲渡料の平均相場

造作譲渡料の平均相場は、設置された造作の種類や状態、立地条件、物件の種類により大きく異なります。一般的には、造作譲渡料は数十万円〜数百万円程度とされていますが、高級な内装や特殊な設備がある場合はさらに高額になるケースもあります。
なお、最終的な造作譲渡料は、テナントと新しい入居者または家主との交渉によって決まるため、市場の需要と供給のバランスや物件の具体的な条件により異なるケースがほとんどです。適正な価格を設定するためには、専門家の意見を参考にするようにしましょう。

造作譲渡のメリットは3つ

次に、造作譲渡のメリットについて解説します。
- 売却コストを軽減できる
- 内装や設備を廃棄しなくてよい
- 閉店までの時間を短縮できる
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.売却コストを軽減できる
造作譲渡の大きなメリットの1つは、売却コストを軽減できる点です。一般的に、テナントが退去する際には、設置した内装や設備を撤去し、原状回復する必要があります。
これには多大な費用と時間がかかりますが、造作譲渡をすれば、新しいテナントや家主にそのまま内装や設備を引き継ぐことが可能になり、撤去費用や手間を省けます。また、造作譲渡により、内装や設備の価値を譲渡料として回収することも可能です。
2.内装や設備を廃棄しなくてよい
造作譲渡のメリットの1つは、内装や設備を廃棄しなくてよい点です。新たな借主が前の借主の内装や設備を引き継ぐことで、改装工事や設備の撤去が不要となり、時間と費用の節約が可能になります。
また、廃棄物の削減により環境負荷を軽減し、持続可能な社会にも貢献できます。とくに、飲食店や美容院など、専門的な設備が必要な店舗では、新規開業の準備期間が短縮でき、スムーズな開店が可能です。
3.閉店までの時間を短縮できる
造作譲渡のメリットの1つには、閉店までの時間が短縮できるという点もあります。一般的に、店舗を閉店する際には内装や設備の撤去、原状回復作業が必要ですが、これには多くの時間と労力が必要です。
しかし、造作譲渡を利用すれば、これらの作業を省略できるため、閉店までのプロセスを大幅に短縮できます。たとえば、内装や設備をそのまま次の事業者に引き継ぐ場合、撤去作業の日程調整や施工期間を考慮する必要はありません。

造作譲渡のデメリットは3つ

次に、造作譲渡のデメリットについて解説します。
- 認識の相違によるトラブルが生じる可能性がある
- 貸主の承諾が必要になる
- 次のテナントとの契約に時間がかかる場合がある
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.認識の相違によるトラブルが生じる可能性がある
譲渡元と譲渡先の間で、内装や設備の状態に対する期待や認識が一致しない場合、さまざまな問題が発生する可能性があります。
たとえば、譲渡元が内装や設備の状態を良好と説明していても、譲渡先が実際に使用した際に不具合が発生するケースがあります。このような場合、譲渡元が意図的に状態を隠していたのか、それとも単なる認識の違いだったのかを巡って、争いに発展するケースも少なくありません。
このような問題を防ぐには、事前の詳細な説明や文書による明確な契約が不可欠です。譲渡元と譲渡先の双方が内装や設備の現状を正確に把握できれば、認識の相違によるトラブルを最小限に抑えられます。
2.貸主の承諾が必要になる
造作譲渡する際には、物件所有者や貸主の承諾を得なくてはなりません。前借主は物件所有者や貸主に対する原状回復義務があり、これを新借主に引き継ぐことになるため、事前の承諾が不可欠です。
また、物件所有者や貸主が次回も飲食店として貸し出す意思があるかどうかの確認も欠かせません。承諾を得るまでに時間がかかる場合や、了承が得られない可能性がある点を理解しておきましょう。
3.次のテナントとの契約に時間がかかる場合がある
造作譲渡では、内装や設備の評価額について譲渡元と譲渡先で意見がわかれるケースが多く、交渉が長引く可能性があります。
さらに、次のテナントの具体的なニーズに合わせた調整に時間を要する場合もあります。このため、次のテナントが見つかるまでの間、空き物件としての固定費が発生し、コストの増加やビジネスの停滞につながるリスクがゼロではありません。

造作譲渡を円滑に進めるポイントは3つ

次に、造作譲渡を円滑に進めるポイントについて解説します。
- リース品の有無や設備の状態を確認する
- 譲渡内容や処分方法を明確にする
- 信頼できる業者へ依頼する
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
1.リース品の有無や設備の状態を確認する
造作譲渡では、お店の設備にリース品が含まれているかどうかの確認が欠かせません。もし、リース品がある場合は、その契約状況についても確認が必要です。リース品を譲渡する場合、そのリース契約も一緒に引き継がれるため、確認を怠らないようにしてください。
また、譲渡品をリストアップしておけば、譲渡品の認識違いによるトラブルを防止できます。さらに、譲渡品の状態についても注意を払い、故障や大きな傷、汚れがないか確認してリストに追記しておきましょう。これにより、譲渡後のトラブルを防止できます。
2.譲渡内容や処分方法を明確にする
譲渡元は、店舗にあるすべての造作物を譲渡の対象にする必要はありません。引き取りたいものは対象から外せるため、譲渡元と譲渡先の間で認識の相違がないように、譲渡するものを明確にするようにしましょう。
たとえば、造作譲渡契約書に「一式」とひとくくりに書いてしまうと、曖昧さが残り、トラブルの原因になりかねません。契約締結前に、譲渡元と譲渡先の間で譲渡内容を明確に確認し、譲渡対象外となるリース品や不用品についても、扱いや処分・修理費用の負担などを明記するようにしてください。
3.信頼できる業者へ依頼する
造作譲渡を円滑に進めるためには、信頼できる業者への依頼が欠かせません。信頼できる業者は、豊富な経験と知識を持っているため、取引の各ステップをスムーズに進行させられます。
また、業者は市場の動向やテナントのニーズに詳しいため、最適な譲渡先をスムーズに見つけるサポートも提供できます。さらに、契約内容の詳細な確認や調整も専門業者に任せれば、双方が納得できる形で契約を締結できる可能性が高いです。

造作譲渡とはでよくある3つの質問

最後に、造作譲渡とはでよくある質問をご紹介します。
- 質問1.造作譲渡契約書は誰が作るもの?
- 質問2.造作譲渡料はどのように決まるの?
- 質問3.造作譲渡の進め方は?
それぞれの内容について詳しくみていきましょう。
質問1.造作譲渡契約書は誰が作るもの?
造作譲渡契約書は、一般的に弁護士や不動産業者、専門のコンサルタントなどの専門家によって作成されるものです。これらの専門家は法律や契約に関する知識と経験を有しており、契約書の内容が適法であり、両当事者の権利と義務が明確に記載されていることを保証します。
なお、契約書には、譲渡する内装や設備の詳細、譲渡価格、支払条件、譲渡の時期や方法、保証に関する事項などが含まれています。
質問2.造作譲渡料はどのように決まるの?
造作譲渡料は、内装や設備の価値、耐用年数、市場の需要などを総合的に評価して決まります。まず、内装や設備の購入価格や使用期間を基に減価償却を考慮し、現在の価値を算出します。
また、同様の物件や設備の市場価格を参考にすることも大切です。さらに、譲渡先がどれだけその内装や設備を利用できるか、需要が高いかどうかも評価に影響します。
これらは、専門の不動産業者やコンサルタントが査定するのが一般的であり、公平な価格設定によって、適正な譲渡料が決まります。
質問3.造作譲渡の進め方は?
造作譲渡を検討する際には、まず契約書を確認し、物件の貸主の承諾を得なければなりません。早い段階での承諾が得られれば、余裕を持って計画を進められます。
もし、交渉や手続きに不安がある場合は、専門の会社に相談するのがおすすめです。契約内容や店舗の内装、設備の譲渡対象、リース品の内容や期限などについても、専門家と一緒に確認しながら進めれば、抜けや漏れのない対応が可能です。

まとめ

本記事では、造作譲渡の概要や平均相場、メリット・デメリット、造作譲渡を円滑に進めるポイントについて解説しました。
造作譲渡は、店舗や事業所の内装や設備を次のテナントに譲渡する方法です。まず、造作譲渡に該当するものとしては、家具、備品、内装などが挙げられますが、賃貸借契約に基づくリース品は該当しません。
また、造作譲渡料の平均相場は物件や設備の状態により異なりますが、市場価格に基づく評価が一般的です。造作譲渡のメリットには、売却コストが軽減できる点や閉店までの時間が短縮できる点が挙げられます。
一方で、認識の相違によるトラブルが発生するリスクはゼロではありません。造作譲渡を円滑に進めるためには、リース品や設備の状態を確認し、譲渡内容を明確にする必要があります。さらに、信頼できる業者への依頼も成功のポイントです。